日本を離れ派遣教師として子どもを教えるということ~チェコ共和国・プラハより~

世界には在外教育施設派遣教師として、異国の日本人学校で教壇に立つ先生方が数多くいます。なぜ日本人学校の教師に? 赴任先の教育現場はどんな感じ? 日本の教育事情との違いは? ここでは、現地で活躍している先生の日々の様子をお伝えします。今回登場するのは、チェコ共和国・プラハで子どもたちに指導をしている八神進祐先生。海外で教職の研さんを積みたいと考えているあなたへ、先輩教師からのメッセージです。
執筆/プラハ日本人学校教諭・八神進祐
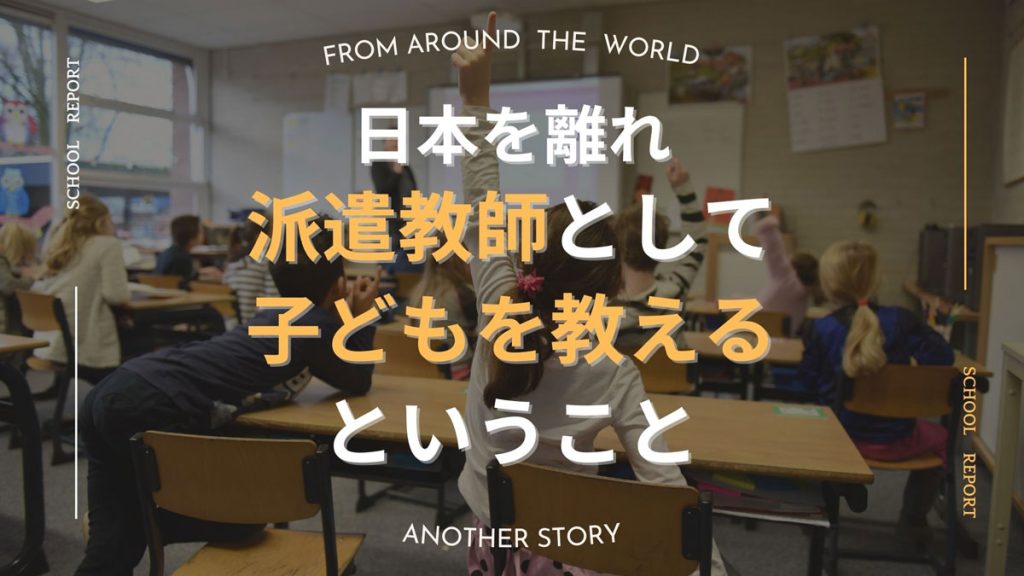
目次
先輩から「キミなら活躍できる」と背中を押されて
在外教育施設の存在は以前から知っていましたが、その詳細についてはあまり理解していませんでした。それまでの私は、海外で生活する子どもたちは大変恵まれており、何不自由なく過ごしていると思っていました。しかし、書籍を読むと、「親の都合で友達と別れ、現地になじめない子や、日本人としてのアイデンティティが確立できずに悩む子もいる」と書かれていました。
自分のイメージと異なるその内容に驚き、在外教育施設では子どもたちに寄り添う心がとくに重要だと感じました。実際、子どもの心に寄り添う教師像は、在外教育施設に限らずどこでも求められるものであり、私は日本で働く中でも、そのような教師をめざしてきました。
その後、在外教育施設で教師をしていた同僚から、当時の経験談を詳しく聞く機会がありました。「キミなら在外教育施設で活躍できる」とその先生に背中を押されたことが、応募を決意する大きなきっかけとなりました。10年以上の教育経験を積み、多様な仕事をこなせるようになった今、海外に住む日本の子どもたちの力になるという選択肢が自然と芽生えました。
在外教育施設で働くことを決意した私は、まず家族にそのことを伝えました。以前から派遣制度について話していたため、妻や両親から賛同を得ることができました。その後、文部科学省の「CLARINET(クラリネット)」というサイトを中心に情報収集を行いながらも、万が一、日本にいる家族が倒れた場合の対応など、さまざまなシナリオを考えながら準備を進めました。
次に、学校長に応募の意志を伝え、選抜試験を受けさせていただくことになりました。その後も、在外教育施設で働く上で重要な資質である「協調性」を意識し、同僚や子どもたちとの関係を大切にしました。
そして幸運にも、試験に合格することができ、チェコ共和国のプラハ日本人学校に赴任することになりました。人事に関することなので、クラスの子どもたちや同僚には派遣のことは知らせることができませんでした。ですが、人事異動の新聞発表後、卒業生や担任していた子どもたちが学校にあいさつに来てくれました。そのときのやり取りは今でも心の支えとなっています。
学校行事のなかにはチェコと日本の絆を深めるイベントも
日本では小学校教諭として10年以上働いていましたが、今はプラハ日本人学校・中学部の担任で、中学1~3年の理科と保健体育科を担当しています。このようなマルチな働き方は在外教育施設の特徴の一つであり、また、私自身の幅を広げてくれたように思います。教材研究にしても、授業スタイルにしても、小学校勤務のときとは異なります。新たな経験のおかげで視座を高めることができました。そして、各都道府県から赴任してきた先生方の実行力と行動力の高さには驚かされます。職員間でも切磋琢磨するなかで、教育観をアップデートすることができました。
本校の全児童・生徒数は90名で、各クラス10名前後と小規模のため子ども同士とても仲がよいです。また、在外教育施設は転・出入する児童・生徒が多く子どもたちは「出会いと別れ」を経験する機会が多いのも特徴です。このことが、彼らの精神的な成長に大きく寄与しているように思います。そのため、一日一日を大切に過ごす様子が見られ、人とのつながりや一期一会の大切さを日々学んでいるように思います。

チェコに来たばかりの子に対しては、とくに丁寧に気持ちをくみ取りながら接していくように心がけています。異国の地に来て、とても不安な気持ちがあると思います。そこに共感しながらも、チェコ文化のよさや生活のコツなどを前向きに明るく話します。日を増すごとに不安が解消され、表情が明るくなっていく子どもたちを見ることが、この仕事の最大のやりがいの一つとなっています。
日本人学校では基本的に日本のカリキュラムに沿った授業が行われますが、行事はその国ならではの特色があります。遠足や修学旅行では、チェコの鉱山や音楽家ドヴォルザークに関連する場所を訪れたり、隣国ドイツのベルリンへ行ったりと、歴史的・文化的に価値のある場所を訪れる機会が豊富にあります。これは非常に刺激的で、子どもたちにとっても貴重な経験となります。
とくに、年に一度の「チェコ日本新年コンサート」では、現地校の生徒やチェコのオペラ歌手、さらには日本大使館の大使と一緒にチェコや日本の歌を歌う機会があります。そこには人種や国籍など関係なく、参加されるすべての人の心が一つになるのを感じることができます。

また、日本的な行事も多くあります。運動会や和太鼓演奏会などが開催され、異国の地で日本文化を感じられる素晴らしい機会となっています。ほかにも、年に5~10回程度、ゲストティーチャーを招いて学ぶ機会もあります。ゲストティーチャーによる授業では例えば、和太鼓演奏家の方から直接指導を受けたり、チェコの国技であるアイスホッケーで活躍する日本人選手から「感謝しながら挑戦する心」をテーマにお話を伺ったりしました。

先日も侍ジャパンの日本代表の選手が来校し、日本を背負って戦う誇りや国際大会の意義について考える貴重な機会がありました。また、WBCチェコ代表の主将ペテル・ジーマ選手によるミニ野球教室が開催されたときは子どもたちは大興奮で、今後生きていくうえで大きな学びを得ることができました。WBCで生まれたチェコと日本の友情は、今まさにホットな話題となっています。

日本の学校と異なる点として、給食はありません。保護者が用意するお弁当が基本です。教師もお弁当を持参します。初めは大変でしたが、次第に慣れてきて、子どもたちと一緒に食べるお弁当の時間が毎回楽しみになっています。
また、総合学習の一環として「チェコ文化理解(CZ)」という授業があります。この授業は、現地採用の先生が担当しています。チェコ語やチェコの歴史・文化について学び、子どもたちはどんどんチェコが好きになっています。

