特別な教育的支援を必要とする子供を生かすとは? 【伸びる教師 伸びない教師 第44回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

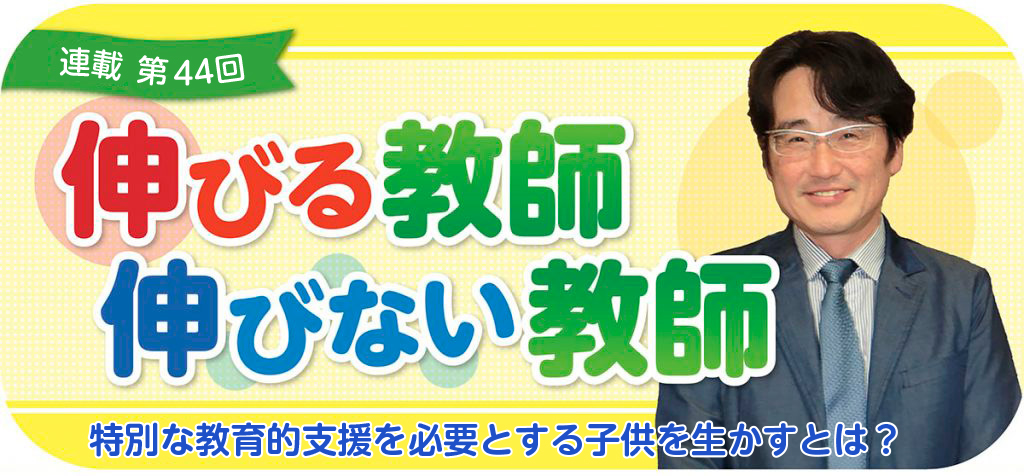
豊富な経験によって培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載。今回のテーマは、「特別な教育的支援を必要とする子供を生かすとは?」です。授業中、自分の知っていることを大きな声で話し始める子供をどのようにして学級で生かすようにしたかという話です。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県公立小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を務める。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
目次
注意を受けるストレスからパニックに
文科省の「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」によると、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒は、小中学校では8.8%という報告がありました。35人学級で言うと、3人に相当します。
ある学級で、教師がひとこと言うと、「それ、ぼく知ってる!」と自分の知っていることを大きな声で話し始める男の子がいました。授業が中断してしまうので低学年のころから担任に何度も注意されていましたが、変わることはありませんでした。
4年生になると、毎日のように注意を受けているストレスからか、たびたびパニックを起こすようになりました。パニックになると友達や教師に暴言を吐いたり、机やいす、壁をけったりするなどの行為が見られるようになってきました。そんなときは、保護者に連絡して迎えに来てもらいました。
そんなことが毎日のようにあったため、周りの子供たちも落ち着かなくなり、けんかが後を絶ちませんでした。4年生の終わりの頃には、いつの間にか互いを信じ合えない集団になっていました。

男の子の意見を全体の話合いに生かす
5年生になって担任が40代半ばの男性に変わりました。児童数35名、ぎりぎりの1学級です。ルールや秩序、信頼が失われ、互いを信じ合えなくなった集団の統率は思った以上に厳しく、ベテランで力のある教師でも最初の1か月は手を焼いていました。中でも授業中、男の子の話をどう止めたらよいか悩んでいました。
はじめは、話をさせないよう注意をしたり約束をしたり、いろいろなことを試しましたが、一向によくなりませんでした。むしろ、注意をすればするほど、男の子は反抗的になっていき、友達とトラブルを起こすこともありました。
1か月が過ぎたころ、その教師は、授業中、その男の子が話し始めたら注意をするのではなく、逆に「○○さんはこう言っているけど、みんなはどう思う?」「○○さんの言っていることは本当なのかな~」と話に乗ってみることにしました。
授業中にその男の子が話す内容の多くは、その授業に関わっていることに気付いたからです。その男の子は知識が豊富なので、実に深いところまで考えていることもあります。そうした男の子の意見をうまく全体の話合いに取り入れ、生かしていこうとしたのです。その男の子の意見を生かすということは、その子を生かすことにつながります。
「あーそう考えるんだね」と流したり、授業に関係のない話をしたときは反応しなかったり、すべての話を受け入れるわけではありませんでした。また、担任は、その男の子に対して、できるのにやらないこと、友達を傷付ける言動については厳しく指導していました。ただ、「自分ではやろうと思ってもできないこと」に対しては、教師が方法を変え、対応していました。それがこの男の子で言えば「授業中に話をしてしまうこと」でした。
男の子にとっては、一部の話は反応されなくても、今まで注意を受けていた自分の話が学級全体で考えを深めるきっかけになったり、黒板に自分の意見が書かれたり……、それだけで十分だったのだと思います。
やがて、友達とのトラブルは減っていき、5年生が終わる頃にはパニックをほとんど起こさなくなっていました。その男の子の落ち着きとともに学級全体も落ち着いていきました。

