ウェルビーイングを学校でつくる! ~SDGsの授業プラン #24 「Goal 12 つくる責任 つかう責任」を学ぶ授業|宗實直樹 先生


全国各地の気鋭の実践者たちが、SDGsの目標に沿った授業実践例を公開し、子どもたちの未来のウェルビーイングをつくるための提案を行うリレー連載。今回からは「つくる責任 つかう責任」を学ぶ授業実践提案をお届けします。ご執筆は関西学院初等部の宗實直樹先生です。
執筆/関西学院初等部教諭・宗實直樹
編集委員/北海道公立小学校教諭・藤原友和
目次
1 はじめに
兵庫県宝塚市にある関西学院初等部の宗實直樹(むねざね・なおき)と申します。社会科を中心に実践研究を進めていますが、本稿では私が2021年〜2023年に兵庫教育大学大学院修士課程(芸術表現系教育コース美術分野)で学んだ内容について紹介します。
以下、子どもたちが本当に心を込めて〈ものつくり〉をしているのか、そしてその〈ものつくり〉が持続可能なものであるかどうか、という問題に焦点を当てて考えます。同時に、この問題に取り組む中で、持続可能な開発目標(SDGs)の視点を結びつけます。これらの考えをもとに、20世紀の美術から得た新しい技法やレッジョ・エミリア・アプローチからインスピレーションを受け、これに近いアプローチを採用した図画工作科の授業実践を紹介いたします。これは、先行実践をもとに考察するもので、私自身が実際に行ったわけではない点はご容赦ください。
2 ESDとSDGs
ESD(Education for Sustainable Development)とは、2002年に南アフリカのヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議」において、日本が提唱した考え方です。
これは、環境的、経済的および社会・文化的視点から、より質の高い生活を次世代も含む全ての人々にもたらすような開発や発展を目指す教育であり、持続可能な未来や社会の構築のために行動できる人材の育成を目的とします。
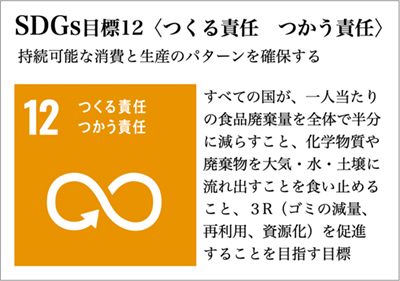
SDGs(Sustainable Development Goals)とは、2015年9月にニューヨーク国連本部で開かれた「国連持続可能な開発サミット」にて採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
ESDとSDGsに共通するキーワードは「持続可能」です。
その背景には、20世紀以降の大量生産・大量消費の問題があるでしょう。大量生産・大量消費は人々の生活を便利で快適にしましたが、環境破壊と資源の枯渇、生産過程の複雑化、個人の均質化・没個性化等の問題を伴います。
SDGs(Sustainable Development Goals)の目標の中の12番目に〈つくる責任 つかう責任〉というものがあります。
これまでの生産と消費の形態への反省から、すべての国が、一人当たりの食品廃棄量を全体で半分に減らすこと、化学物質や廃棄物を大気・水・土壌に流れ出すことを食い止めること、3R(ゴミを減らし、再利用し、資源化すること)を促進することを目指す目標です。
衣服や食品、生活に必要なものは、地球上の資源を使って作られ、人はものを作ることを通して生活を営みます。しかし、〈ものつくり〉の資源には限りがあり、現代の私たちは、〈ものつくり〉をする人間のあり方それ自体を問い直す必要に迫られているといえます。

