「ペア対話をどの学習でも1回は取り入れよう」対話型授業と自治的活動でつなぐ 深い絆の学級づくり #2

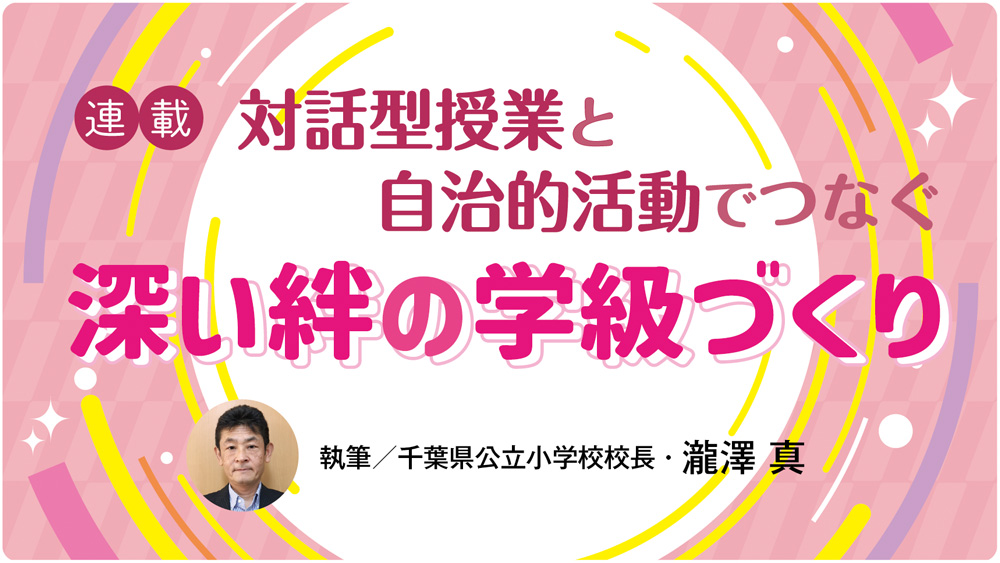
コロナ禍以降、コミュニケーションに苦労する子供や人間関係の希薄な学級が増えていると言います。子供たちが深い絆で結ばれた学級をつくるには、子供同士の関わりをふんだんに取り入れた対話型授業と、子供たちが主体的に取り組む自治的な活動が不可欠です。第2回は、ペア対話を取り入れた授業による学級づくりについて解説します。
執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真
目次
学級づくりは、学級活動+授業という戦略をもとう
学校生活で一番長く過ごすのは、何の時間でしょうか。考えるまでもなく「授業」ですよね。
子供が8時から15時30分まで7時間30分学校に滞在するとします。そのうち、45分×6時間=270分、4時間30分が授業です。
滞在時間の半分以上を過ごす授業が、学級全体に与える影響は決して少なくありません。したがって、深い絆をつくるには、この時間にできることは何かという戦略が必要になってきます。
絆のベースはコミュニケーションです。教師が一方的に説明するような授業では、子供同士のコミュニケーションはほとんど生まれないでしょう。
そこで、「対話的授業」を積極的に取り入れ、子供同士のコミュニケーションを活発にしていきましょう。それにより絆を深めていきましょう、というのが本連載の提案です。そのため、タイトルに「対話的授業」という言葉が入っています。
当たり前のことですが、学級づくりは学級活動だけでできるわけではありません。授業でも学級づくりをする、それが重要なのです。
では、対話型授業は、どんなことから始めればいいのでしょうか。
結論から言えば、「ペア対話」です。1対1のコミュニケーションがすべての基になります。ですので、このペア対話をまずは徹底していきましょう。
「ペア対話」の3つのルール
いきなり授業でペア対話をしても、なかなか話は弾まないもの。一方の子がずっとしゃべって終わる可能性もありますし、逆に沈黙したままということもあるでしょう。
そこで、まずはたわいもない話から始めましょう。その際、ペア対話の基本的なルールも確認していきましょう。
1.交互に話をする
2.肯定的に聞く(うなずく、なるほどと相づちを打つなど)
3.話が途切れないようにする
対話ですので、どちらか一方がずっと話していてはだめです。そこで「交互に短く話す」をルールとします。
また、話を否定されたら話をする気になりません。対話というのは親和的な雰囲気が大切です。ディベートとは違います。そこで、笑顔でうなずく、相づちを打つなども約束にします。
そして、話が途切れないようにすることもポイントです。沈黙していては、対話が成立しません。
このような決まりを設けても、話が弾まないこともあるでしょう。そのような場合は、「もう一度同じ話を繰り返してもいい」と伝えます。なぜなら、まったく同じ話を繰り返すことは実は難しいのです。私の経験では、先ほどの話に少し付け足して話すことが多い印象です。そうなると、少し話の筋が変わることがあるのです。それが対話の面白さとも言えるでしょう。思いもしなかった方向に話が進む、というのがいいのだということも伝えましょう。

