来期の教育課程に、導入を検討してみませんか? 個別最適な学び『自由進度学習』

3月は、来る新年度に向けて、様々な視点から次年度の計画を作成するための追い込みの時期と思います。皆さんは何を重点に置いて教育課程を編成しますか? 私が特に力点を置いてきたのが「授業改善」です。授業改善を組織全体で取り組むことによって、教員たちが変わり、子どもたちも生き生きし、学校全体に勢いが生まれるからです。このなかでも昨今注目を集めている、個別最適な学び『自由進度学習』の導入について少し考えてみましょう。
【連載】タバティのLet’sスマイル(レッツスマイル) 学校づくり #19
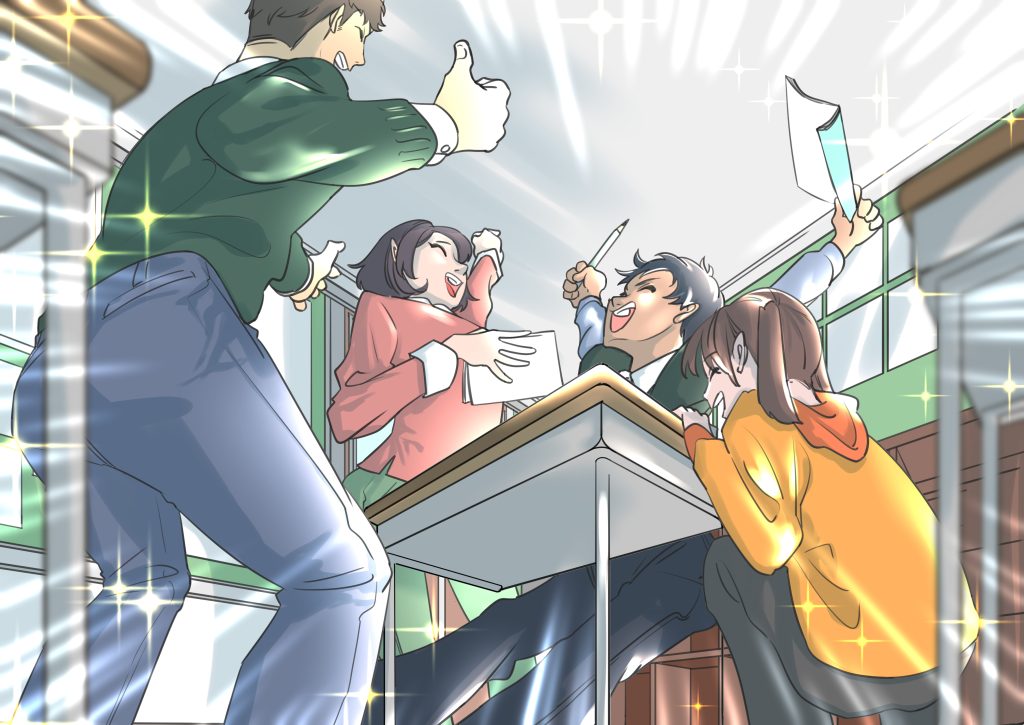
目次
子どもたちも教職員も楽しい取組を
授業改善で大切なこと。それは、子どもたち一人一人が「勉強が楽しく」「学習にしっかり参加でき」、結果「笑顔になる」ような取組であるということです。
ただ、管理職自身で授業を行うことはありませんから、教職員のモチベーションを上げ、皆が同じ方向を見つめて取り組んでいく必要があります。
教職員自身も、「面白い」「自分のものにしてみたい」「子どもが乗ってきた」と思える授業改善でありたいものです。
そのためには、まず教職員間で目指す授業づくりに向けて議論や雑談をすることです。本音を言える場を確保することが、教職員のモチベーションアップにとって重要ポイントです。管理職は細かいところまであれこれ口出しせず、校長・教頭・教務の三役で、温かく見守るような構えでいましょう。
個別最適な学び ─自由進度学習─
さて、授業改善という問題において、よく会議や雑談で話題になるのが、「算数学習における理解度の差や、つまずきポイント」のことです。算数は子どもたちの間で、最も理解に開きが生じる教科の一つです。この課題を何とかしたいとよく話題に上がります。
令和3年1月26日、文部科学省から出された「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと, 協働的な学びの実現~(答申)」は大きなきっかけでした。この提言は特別な支援を必要とする子どもたちを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実や創造性を育む学びの実現を目指した提言でした。これからの時代を見越した内容で全くもって共感しました。
本校では「協働的な学び」は「意見をつなぐ学び合い」としてすでに実践しており、そこに「個別最適な学び」を子どもの実態から求めていた時でした。「個別最適な学び」と「協働的な学び」が行き来する複線型の学び合いを目指していたのです。
GIGAスクール構想によって、全児童にタブレット端末が配られたのも大きな後押しでした。 GIGAスクール構想の良さは、タブレット端末で教室の全員がクラウドを活用できることです。その特徴は、
①作業している途中で教員も子どもも全員の思考途中を共有できる点
②後から追加や修正が簡単にできる点
③追加や修正の記録が簡単に残る点
ということです。特に注目すべきが、作業している途中で、教員が子ども一人一人の進度やつまずきを把握できることです。これまでは学級35人の子どもたちの学習進度を把握することが大きな課題でした。しかし、このクラウドを活用することで、子どもたちの学習進度の状況が一目瞭然になり、的確な支援ができるようになったのです。さらに設定によっては、途中経過の段階でも子ども同士も共有化できるのです。クローズドな学習過程がオープン学習になり、新しい時代の幕開けを感じました。ここに自由進度学習の授業が効果的にできる可能性を強く感じたのです。

