子供が主体的に学習活動を進めながら、ひらめきや発見のある授業をつくる 【全国優秀教師にインタビュー! コレが私の授業づくり! 第2回】
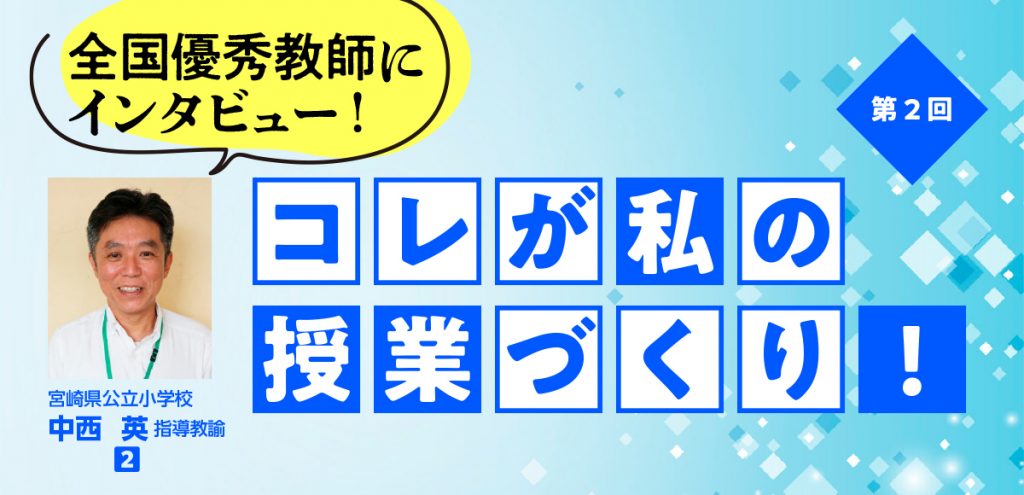
全国の優秀教師が「この授業こそ、私の授業づくりを具現化したものだ」と考える授業を紹介するこの企画。今回は、前回紹介した宮崎県のスーパーティーチャー(小学校・算数)である中西英指導教諭の、算数の授業づくりの考え方を紹介していきます。

目次
子供自身が活動の中で見付けだす学習過程がとても大事
「前回、算数の授業では演繹的な学習だけでなく、帰納的な学習が大事だとお話ししましたが、私は子供たち自身が定理を発見したり、活動の中で見付けだしたりする学習過程がとても大事だと考えています。
例えば、前回と同じ場面で同じ教材を使って授業をしても、『こうなっているでしょ』と言いながら、自分で数式を並べ替えてしまうような先生もいます。しかし、子供自身が並べ替える(操作する)のと、先生が操作するのとではまったく意味が違うのです。子供たちがみんなで、『ああじゃない?』『いや、こうでしょ』と言いながら並べ替え、子供が主体的に意思決定をするからこそ、『何で、そうだと考えたの?』と発問することで、子供の考えを引き出すことができます。もし、そこに間違いがあったとしても、子供たちに問い返せば、問題点が明らかになったり、子供たちの間で修正に向けた対話が生じたりするでしょう。
私自身がこのような授業づくりをするようになったのは、地元の大学附属小学校に異動した直後の、『入魂授業(異動した教員が最初に行う授業公開)』での授業研究会で、『今日の授業は先生がやりたかった授業で、子供たちがやりたい授業ではないですね』と指摘されたことがきっかけでした。子供がやりたいことを追究するからこそ、主体的に考え、意思決定し、表現するわけで、その先により確かな理解も生まれるわけです。
『したい』が生まれる授業が大事だと提唱されている先生もいらっしゃいますが、子供自身が『こう並べ替えたい』『こう変形したい』『~したい』と思い、行為することの中に、子供の見方・考え方が出てくるわけです。それを生かし(必要に応じて修正し)、より深い理解につなげていくような授業を、私は大事にしたいと考えています。加えて授業の中で、子供が自らその学習(課題や問題)に向かっていくような主体性が生まれないと、学んだことも剥落しやすいのではないかと感じています」
実際に「教育技術」誌上で以前、取材をさせていただいた中西先生の授業でも、子供たち自身が問題に対し、操作しながら見方・考え方を働かせていく過程を見ることができました。それは3年生の『大きな数』の単元で、大きな数をどう表記すればよいかを考えていく場面で、黒板にバラバラに貼られた1、10、100、1000の記されたカードを、子供たちが「分かりやすいように整理したい」と言い、整理をしながら「大きな数」の表記の仕方や読み方などを学習していくというものでした(画像参照)。



3年生の「大きな数」の学習でも、子供たちがカードを整理しながら量感を身に付けたり、表記の大切さに気付いたりしていった。

