単元テストや通知表をやめるのは、教員の仕事の見直しの一環【都心の小学校校長にインタビュー! 「宿題、テスト、通知表廃止」の背景と経緯 #02】
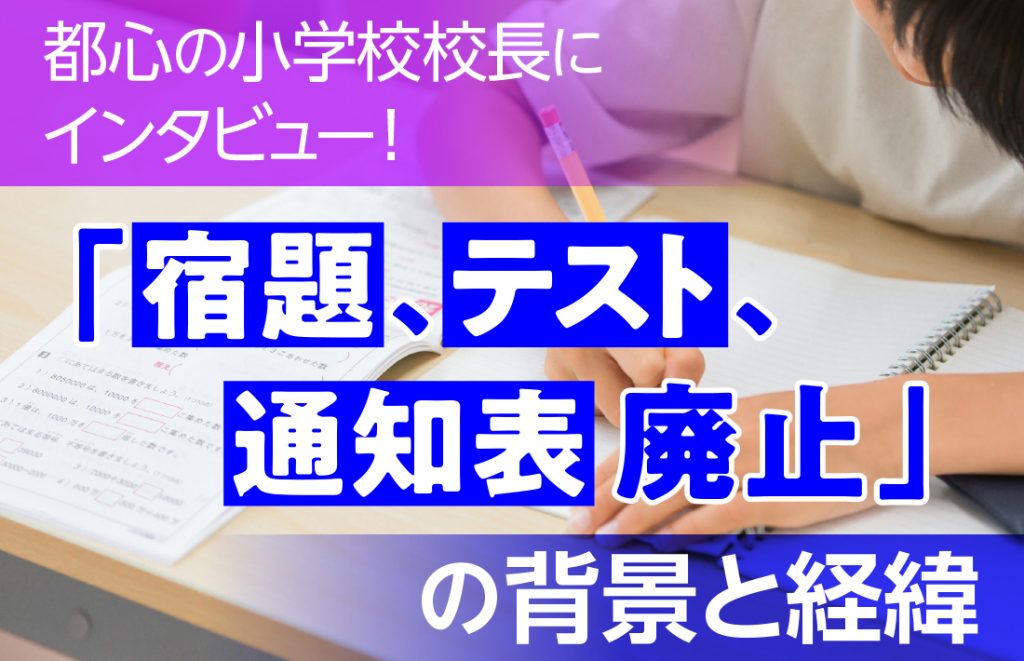
長井満敏校長は、西新宿小学校に異動して4年目なのですが、このタイミングで通知表の廃止、単元テストの廃止、与える宿題の廃止といった多数の改革を開始した理由はどこにあったのでしょうか。また改革を進めるには、当然、保護者や地域、教職員の理解が必要ですが、どのように理解を図ったのでしょうか。2回目はこうした話を中心に聞いていきます。

目次
教員が働きやすい環境をつくり、「学びを子供の手に返す」
「2022年度から改革の準備を始めることになったのは、一つにはコロナ禍の影響があります。私が本校に赴任した令和2年度から、一斉休校などの影響を受けてきました。それが、2022年度からいかに通常に戻していくかという時期に差しかかってきたため、周知を図って新たなことに取り組み始めるにはちょうどタイミングが良かったのです。
もう一つ大きかったのは、教員人事の問題です。東京都には教員の公募制度があるため、教員自身が希望すれば、学校指定で他地区から教員を集めてくることができます。本校でも、広く良い教員を集めることができればと考え、電話をかけるなどのアプローチをしていたのですが、そのとき、ふと『良い教員を集めれば学校が良くなるのは分かるけれども、そうでないと経営できない学校って何だろう?』と思ったのです。よそから人を集めるのではなく、『一定程度の力量をもっていさえすれば、誰でも教員として務まるような学校にしていかなければいけないのではないか』ということです。
現在、教員のやるべきことが増え、ハードルが高くなっています。そのため教職を目指す人が減り、東京都の小学校教員の採用試験倍率は1.1倍にまで下がってしまいました(資料参照)。その高くなった仕事のハードルを下げるため、学校内の仕事のいろんなことを見回して、やめられるものはやめ、子供の学びという大事なことに注力できるようにしようと考えたわけです。決して簡単なことではないけれども、単元テストをやめるのも、通知表をやめるのもそうした見直しの一環です」
結局、一部の優秀な教員を奪い合うだけでは公教育全体の質が上がることにつながらないため、現在、学校に在籍している教員が働きやすい環境をつくり、「学びを子供の手に返す」ことを目指すのだ、と長井校長は話します。
【資料】東京都教育委員会資料より抜粋


