提言|赤坂真二 令和版、尊敬される教師とは? 【教師という仕事の価値を高め、失われた自信と信頼を取り戻すために 今、求められる教師像とは? #05】
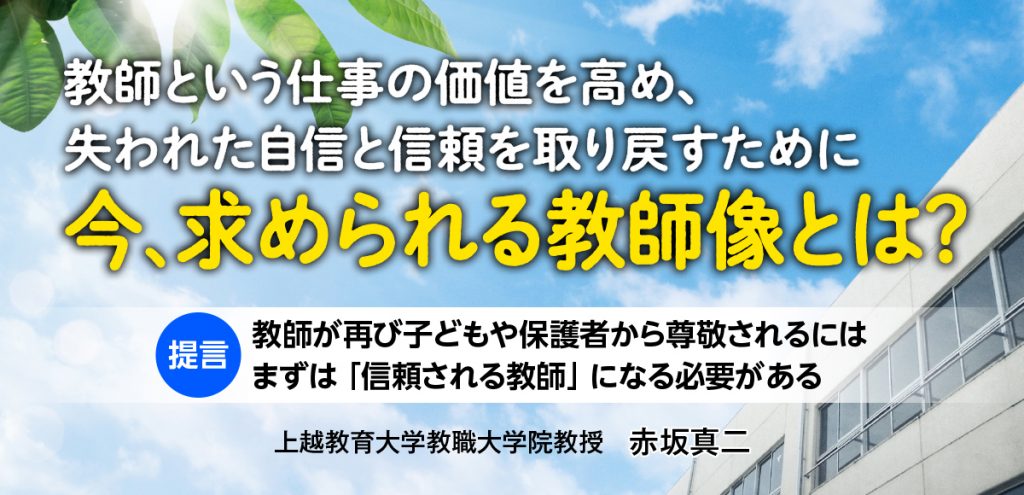
世間からは「学校はブラック」だと思われ、保護者対応の難しさから自信を失い、教師という仕事に対する価値が以前よりも下がったのではないかと、感じている方もいるのではないでしょうか。そこで、どうすればその価値を上げられるのかを考えてみることにしました。教師たちの失われた自信と信頼を取り戻すために、今、求められている教師像を明らかにする8回シリーズの第5回目です。元小学校教諭で、現在は大学で現職教員や大学院生の指導を行っている上越教育大学の赤坂真二教授に話を聞きました。

赤坂真二(あかさか・しんじ)
新潟県生まれ。19年間の小学校での学級担任を経て2008年4月より現所属。現職教員や大学院生の指導を行う一方で、学校や自治体の教育改善のアドバイザーとして活動中。2018年3月より日本学級経営学会、共同代表理事。『学級経営大全』(明治図書出版、2020年)など著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全8回予定)
●提言|合田哲雄 教師という仕事の価値は下がるどころか、むしろ高まっている
●提言|前田康裕 ICTを活用したクリエイティブな学びと情報発信
●提言|神内聡(弁護士) 分かり合えない保護者にどう対応するか
●提言|成田奈緒子(小児科医) 発達障害かもしれないと思ったら、教師がすべきこと
●提言|赤坂真二 令和版、尊敬される教師とは?(本記事)
目次
かつて日本の教師は尊敬されていた
かつて日本の教師は多くの人々から尊敬される存在でした。その背景として、日本人はもともと教育熱心な国民性であり、教師や教育そのものを大事にする風土があったと言われています。当時の文部省の調査によると、1970年の男女合わせた大学進学率は17.1%でした。教師になるのはその中の一部ですが、「授業名人」として知られる野口芳宏先生がよくおっしゃっていた言葉「教師たるもの、改革者たれ」で表現されているように、世の中に何か一つでも楔を打ち込んでやろう、世の中をよくしてやろう、という壮大な使命感を持った人たちが、教師をしていたのでしょう。そして、世の中にも未来に期待するムードがあったのだと思います。そのため、保護者は子どもに「先生の言うことを聞きなさい」と当たり前のように言いましたし、地域の人も「学校の先生の話は聞く価値がある」と思っていて、多くの人から尊敬されていました。その尊敬が教師という仕事の価値になっていたのではないかと思うのです。ただし、それは全国各地にいる熱心な先生方が、昼夜を問わず、子どものために献身的な教育を行ったことによって、得ていた尊敬でもありました。
1980年代になると中学校で校内暴力が増加しました。それに対して、教師側が高圧的で支配的な指導をして抑えつけようとしたのですが、当時の国民の世論は学校の味方をしていました。しかし、1990年代後半から今度は小学校で学級崩壊が増えてきたころには、風向きが変わっていました。学級崩壊の原因は教師の指導にあるのではないか、と逆に教師が批判されたのです。学級崩壊の場合は相手が小学生だったせいもあり、教師側はかつて中学生にしたような高圧的な指導ができなかったこともありますが、そのような指導を世間がもう許容しなくなっていました。そういった世論を誘導するかのように、大手新聞やテレビなどでは、学校に対する批判的な報道が毎日のように行われるようになりました。
世論が変化した原因の一つとして、1980年代に24時間営業のコンビニが増えてきたあたりから、世の中の人たちのサービスに対する期待が高まったことが挙げられます。店に行けば、欲しいものがいつでも手に入ることが当たり前になりました。それに対し、学校はコンビニ化しなかったからです。そのため、余計に学校は世の中の人々の不満に晒されたのです。
また、学校5日制の導入が与えた影響も大きいと思います。学校5日制は、公立小中学校では1992年から段階的に実施され、2002年度から完全導入されました。それまでは先生はいつも学校にいて、子どものことを無条件で愛してくれる存在だったのですが、学校のほうから「土曜日は子どもを家庭に返します」と申し出て、保護者に対して線を引いたかのような形になり、保護者との間に距離ができました。こうして学校5日制が完全導入されるころには、教師はすっかり世の中の尊敬を失っていました。
つまり、みんなから尊敬されていた教師という仕事の価値は、先生たちだけのせいではなく、世の中の流れの中で、徐々にディスカウントされていったのではないでしょうか。
しかし、教師という仕事の価値そのもの、絶対値の部分は、変わっていないと思います。「これからこの国を作っていく人たちを育てる」という教師という仕事の価値は何一つ変わっていないのですが、それを評価する側の考え方が変わっていったのです。例えば、金(GOLD)の価格は社会情勢による需要と供給の変化で変わっていきますが、金そのものの絶対的価値は変わりません。それと似ていると思います。
では何が変わったのかというと、教師という仕事の価値が変わったわけではなくて、学校と社会の関係性が変わったのです。
今の教師に必要なもの、それは信頼
最近、一部の研究者の方々から「学習指導要領が分厚く、充実しすぎていて、超人養成マニュアルのようになっている」と指摘する声が聞かれるようになりました。少し厳しい言い方をすると、学校では、そこに書かれている高度なことを、全ての子どもたちに理解させようとして先生たちが一生懸命頑張り、それにより、子どもたちが追い込まれているようにも見えます。
その結果、今、子どもにとって「学校が楽しい」という感覚が損なわれているのではないかと危惧しています。コロナ禍で休校措置になったときに、子どもの居場所としての学校の機能が再認識されたのに、いつの間にかそれが忘れ去られ、学校は再び学力向上の場に戻ってしまったのです。
そもそも学校には「引き上げる機能」と「養う機能」の2つの働きがありました。ところが、いつのまにか学力向上に代表される「引き上げる機能」の方だけが強くなり、ケアするという意味での「養う機能」が弱くなりました。おそらくそれがコロナ後の不登校の児童生徒の急増の一つの要因になっています。
学力を向上させなくていいとは思いませんが、学力を向上させるには、子どもの中に学習に向かうためのエネルギーを貯めなくてはいけないと思うのです。だからこそ、まずはベースとなる養う機能を充実させる必要があります。その部分を充実させていかないと、今後、子どもたちはますます学校から遠のいていくのではないでしょうか。
つまり、今、学校が再びその存在価値を高めるには、養う機能を充実させる必要があり、それには教師が子どもと保護者から再び尊敬される存在になることが重要です。ただし、昭和の「尊敬される教師」に求められたものと、令和のそれに求められるものは少し違うと思います。令和の「尊敬される教師」に求められるものは何かというと、それは信頼です。まずは信頼されなければ、尊敬されないからです。
そして、今の教師は、信頼を獲得することが自分の仕事にとって重要なのだというマインドを持って、そのためのスキルや知識を知る必要があります。
では、どうやれば信頼を獲得できるのかといいますと、まず、子どもから見て「信頼される教師」と「信頼されない教師」の特徴を知ることです。この分野の研究はすでに進んでおり、一般的にどんな先生が信頼されて、どんな先生が嫌われるのかはある程度わかっています。
例えば、中学校で信頼される教師は、聞き上手である、話すと元気になる、自分に定常的に関心を向けてくれる、自信がある、威厳がある、正義感がある、きちんと叱ってくれるなどの特徴があります。最後の「きちんと叱ってくれる」については、意外に思うかもしれませんが、「ダメなことはダメだとちゃんと言ってくれる」ということです。それは言い換えれば、教師の役割をきちんと果たしてくれる先生を意味します。
逆に、「信頼されない先生」の特徴としては、威張っている、自分の考えを押し付ける、考えや態度が否定的である、ネガティブである、ひいきをする、などが挙げられます。
もうひとつ、注目したいのは叱り方です。小学校の「信頼に関する研究」を紐解いていくと、適切な叱り方をする先生は、高く評価されていることがわかります。しかし、実際は、先生たちの叱り方は千差万別です。先生たちは叱り方について、誰からも教えられていないからです。授業がうまいか下手かも大事ではありますが、実は日常的にどんな言葉で語り、叱るのかのほうがもっと大事なのです。それによって子どもとの信頼関係が変わるからです。
このように様々な研究データを使って、学校として教師の指導力に特化した校内研修を行い、信頼を獲得するためのスキルや知識として積み重ねていく必要があると思います。
また、子どもからの信頼は、保護者の信頼にもつながっていきます。新学期が始まって数か月経ったころ、学校から帰ってきた子どもに保護者が「今度の先生どう?」と聞いたときに、「あの先生、好きだよ」と子どもが答えるようであれば、保護者もその先生を好意的に見てくれます。そこから信頼へとつなげていくには、保護者が教師に求めているものは何かを知っておく必要があります。学校に行ったときにざっくばらんに話ができること、自分の子どものいいところを見てくれること、それにプラスして、今の保護者には自分の話を聞いてほしい、という思いが強いことを理解しておく必要があります。

