実験と観察を重視した理科授業で「教えから学び」への転換を図る 【連続企画 探究的な学びがカギ! これからの「理数教育」のあり方 #05】
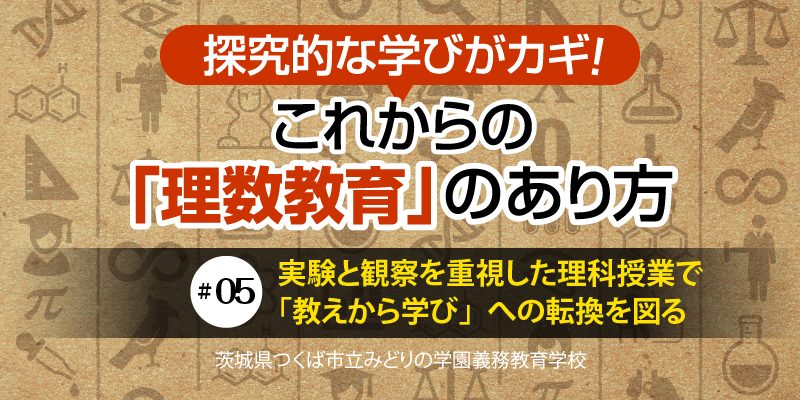
2018年に開校した茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校では、「Searching for the Better Future !」を教育方針に掲げ、義務教育9年間の連続性を生かした先進的ICT教育や英語教育を推進している。充実したICT環境のなかでアプリやソフトなどのデジタル教材を実験や観察の補完ツールとしてだけでなく、その特性を生かし探究力を深める理科授業を行っている。その教育について、理科担当の大山翔教諭に聞いた。
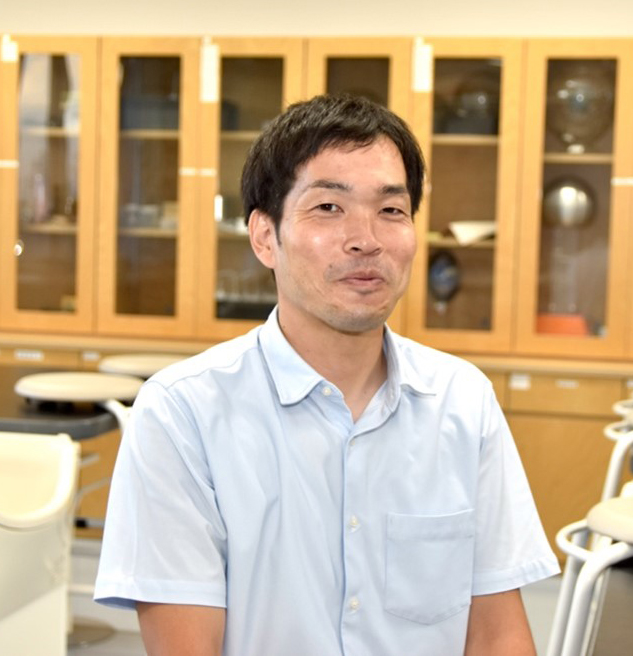
茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校
2018年開校の義務教育学校。「Society5.0」時代の世界をリードするチェンジメーカーに必要な7つの21世紀型スキルと社会力、すなわち「プログラミング的思考」「協働力」「知識・理解力」「言語活用力」「創造力」「思考・判断力」「市民性」を身に付けさせる学習を展開している。写真は、今回お話を伺った理科担当の大山翔教諭。
この記事は、連続企画「探究的な学びがカギ! これからの『理数教育』のあり方」の5回目です。記事一覧はこちら
目次
大事なのは科学的事象の仕組みを理解していること
みどりの学園義務教育学校は創立3年目で日本教育工学協会から「学校情報化先進校」に認定されるほどの充実したICT環境が整備されているが、理科担当の大山翔教諭は、理科の授業において最も力を入れているのは「本当にやりたいことに主体的に取り組ませること」だと語る。
「本校のICTツールは他校に比べて充実していると思いますが、何よりも子どもたちのやる気をいかに引き出すかに注力することが大事だと考えています。これからの子どもたちが生きていく世界は、正解のない世界。公式を覚えることも大切ですが、その前提となる『それはなぜなんだろう?』という本質を問う力が求められる時代になっていく。したがって子どもたちが主体的に学ぶことのできる多様性のある環境をいかにつくっていくかが重要だと考えています」
多様性のある教育環境の確保は大切だ。子どもたちが主体的な学びを獲得していくためには、教員側の「教えから学び」への意識変革と、子どもたちにいかに興味関心を抱かせるかの「仕掛け」が重要になる。子どもたちが中学校の段階で理科嫌いになることが多い最大の理由は、「覚えなければならない知識量が増え、暗記教科になるから」だと大山教諭は考えている。そのため、理科の学びに出てくる「語句」にこだわらない授業を、大山教諭は意識しているという。
「理科を学ぶ目的は、物事の本質を科学的に探究して理解することにあるわけです。ですから、科学的語句を覚えることよりも、その科学的な事象の仕組みを理解することや、科学的なアプローチ方法を身につけていることこそが重要。いまは語句を覚えていなくても、アプリで検索すれば出てきますから」
実験や観察ができない事象にアプリやソフトを積極的に活用
大山教諭が理科の授業で最も重視しているのが、実験や観察だ。
「小学生でも中学生でも、理科好きな子どもに聞くと『実験や観察が好き』という声がとても多い。実際に、科学の本質を探究する上では、観察と実験が基本になります。そのため授業でもできるだけ実験や観察を実施し、その上で実際の実験や観察が難しい事象についてアプリやソフト、動画などを使って理解を深めています」
たとえば6年生では月の動きを無料のWebプラネタリウム「ステラリウム(Stellarium)」を使ってシミュレートしたり、無料のバーチャル地球儀アプリ「グーグル・アース(Google Earth)」を使って海外の地層などを調べたりしている。
「ステラリウムで日時を変えて月の動きを追ってみたり、またそこに行かないと見られない地層などはグーグル・アースを使って見たりしています。グーグル・アースは地層がきれいに見えるんです」
授業においては、ICTを使っての効率化にも務めている。
「パドレット(Padlet)」という投稿ソフトがあるのですが、大きなボードに自分の意見をペタペタと貼っていける。いままでは子どもたち一人一人のノートを見に行かなければなりませんでしたが、画面で全部共有されているので、その投稿を見ながらシミュレーションを少しずつ修正していくといったこともやっています」


