“遊び” から入る理科授業(4年「空気と水の性質」より) 【理科の壺】

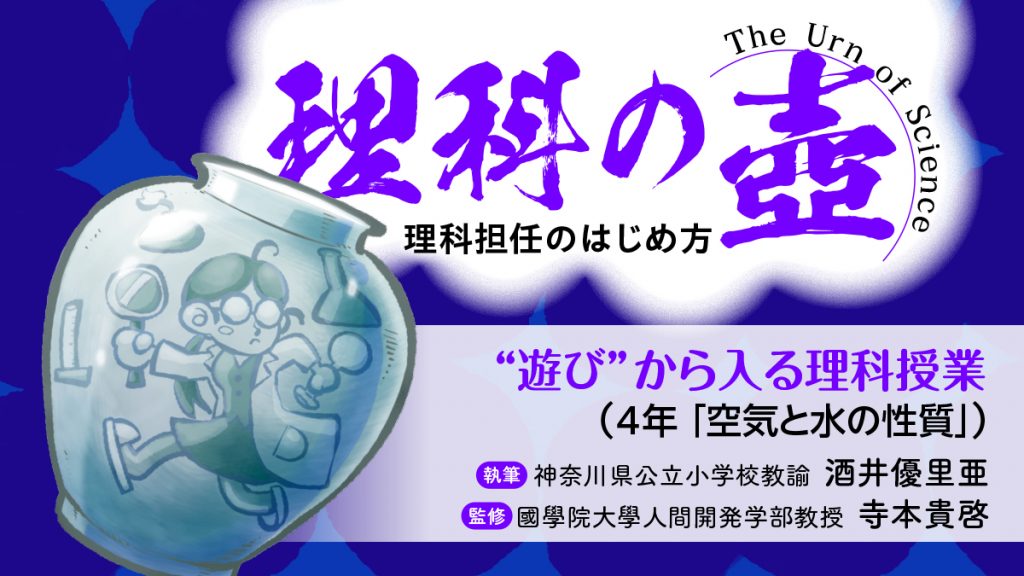
理科は、子ども自身が自然の事物・現象としっかり関わることから始まる、とよく言われます。これは、先生や友達から “不思議” を与えられるのではなく、自分自身で見つけ出して、その問題を自分事として解決することを求める、ということです。子どもたち自身が遊んでいる中から「やってみたい!」と思って始まる授業と、先生が「やってみたいでしょ?」とレールを敷くような授業とでは、どちらがよりよいでしょうか? 今回は、子どもたち自身が遊びの中から自然事象と関わり、理科の授業に入り込んでいく1つの事例をご紹介します。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/神奈川県公立小学校教諭・酒井優里亜
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.4年生「空気と水の性質」のスタートは水鉄砲大会!
みなさん、想像してみてください。先生が「今日から、空気と水の性質について学びましょう!」と言って授業が始まったときの子どもたちの反応。「はーい!」「どんなことをするのかな?」などでしょうか。
では、先生が「今日は、みんなで水鉄砲で遊びましょう!」と言って授業が始まったときの子どもたちの反応はどうでしょう。「いいの!?」「やりたい!!」と目を輝かせ、とびきりの笑顔でこちらを見つめてくる子どもたちの様子が浮かびませんか?
子どもたちはこの水鉄砲大会が“学習”のスタートだとは思わないでしょう。でも、これから始まる水鉄砲大会が、実はしっかり「空気と水の性質」の学習へと繋がっていくわけです。“遊び”から、いつの間にか理科の授業が始まっている。ワクワクドキドキ、理科の時間が楽しみになるような授業を始めましょう!
2.市販の空気圧式(加圧式)水鉄砲はどんなしくみ?
市販されている水鉄砲には、引き金を引く運動によって水を発射させるタイプのものや注射器のように水を押し出すタイプのものなど、様々な種類のものがあります。今回水鉄砲大会で使用するものは、シャカシャカっと空気をタンクの中にため込み、空気の圧力を加えてから勢いよく水を発射させる空気圧式(加圧式)タイプの水鉄砲です。
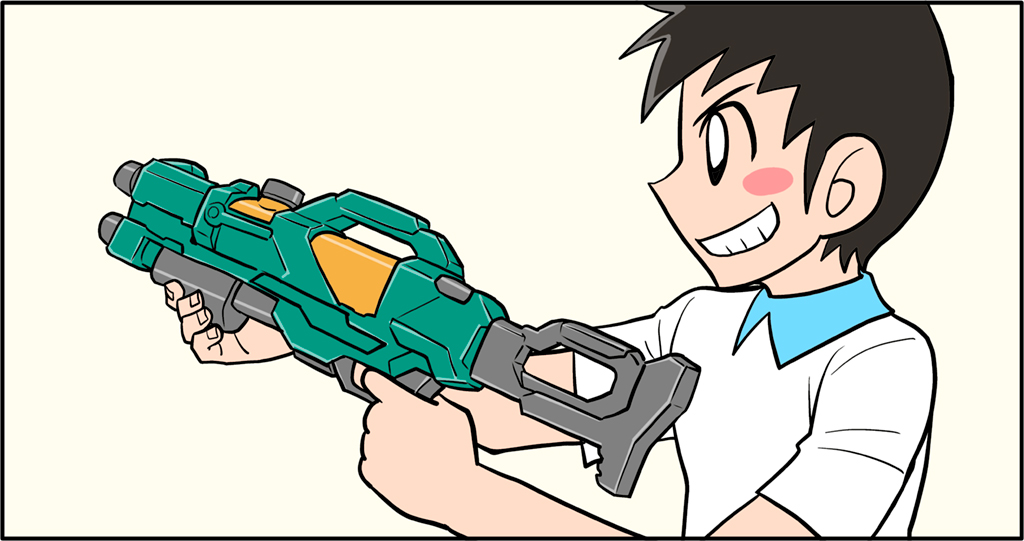
とは言え、これはかなり高価で、子どもたち用に学校で購入するのは厳しそう…。
大丈夫、安心してください。身近にあるもので、子どもたちと一緒に作ることができますよ! 完成形がこちらです。

作り方もお伝えしますが、その前にこの水鉄砲の仕組みを説明しましょう。
この手作り水鉄砲は、空気圧式(加圧式)水鉄砲と同じ仕組みです。ペットボトルの中に半分ほど水を入れ、キャップを突き抜けて飛び出しているストローを指で押さえたら、横に飛び出しているストローから息を吹き込む。そうすると、ペットボトルの中に空気がたまっていき、空気圧が高まり、水を圧し出そうとします。出口をふさいでいる指を離せば、ギュウギュウと空気圧で圧迫された水が勢いよく飛び出していきます。

