良い学級経営をするために「全員班長」と「学級通信」 【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第17回】
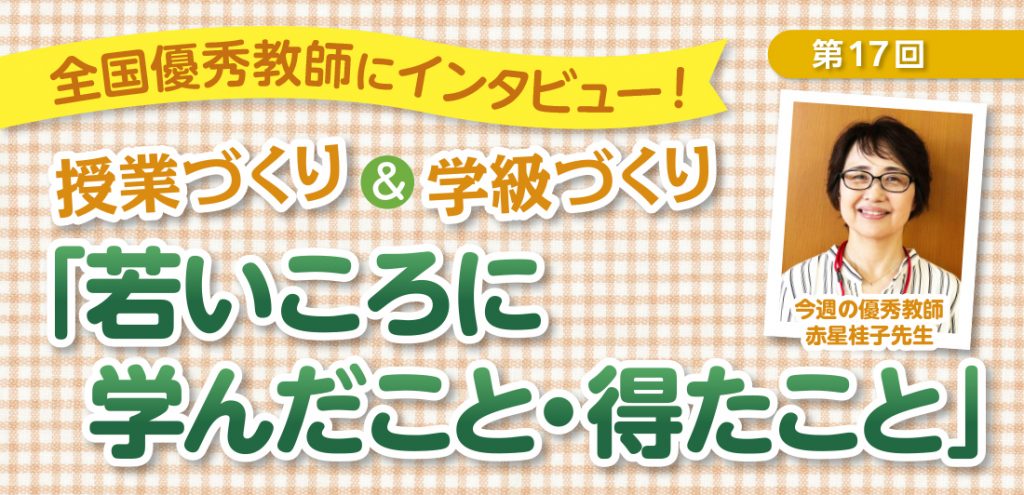
前回、熊本県の授業名人(小学校・道徳科)の赤星桂子指導教諭が、初任者の頃、学級づくりに苦労し、先輩方から学んでいったことを紹介していきました。今回は、学級づくりのために赤星先生が工夫していった具体的な方法や後に異動した学校で道徳の授業づくりを学んでいった過程などを紹介していきます。

目次
子供の良さを見付けたらすぐに付箋紙などにメモ
学級の中にはいろいろな個性をもった子供たちがいます。そんな子供たちが伸び伸びと過ごせるような、「一人一人の良さが生きる学級をつくりたい!」と考えた私は、まず全員が班長となるシステムをつくりました。班長と言えば、グループごとに1名つくるのが普通ですが、私は班員一人一人に役割を分担しました。「がんばり班長(グループ学習の司会など)」「ピカピカ班長(掃除のお世話など)」「パクパク班長(給食のお世話など)」「ニコニコ班長(喧嘩が起きたら仲直りさせるなど)」「モリモリ班長(外遊びを呼びかけるなど)」など、いろんな班長をつくることで、みんなに出番があり、活躍できるようにしました。
係活動(会社活動)も一人一人の良さが生きる上で大事なものです。黒板消し係などの学級に必要な係もつくりますが、学級が楽しくなるようなおもしろい会社をつくりました。遊び会社、塗り絵会社など、子供たちに活動する時間や場を確保することで、盛り上げていったのです。そのように子供たちに役割を与え、工夫する時間と場を与えることで、子供たちの企画力や調整力が劇的にアップしました。
また、より良い学級経営をするためには、教師と保護者と子供の三者がつながることが必要だと考え、大事にしたのが「学級通信」です。三者がつながり、三角形で美しい響きを奏でる「トライアングル」のような学級経営を目指し、学級通信の名前にして私の思いを込めました。ただ、「一人一人の良さが生きる学級をつくりたい!」と言いながら、私は子供たちの良さを見付けることが少し苦手だったのです。そこで毎日必ず、学級通信を出すことに決めました。B5判程度の紙に手書きで、その日あったステキなことや子供たち一人一人の良さを毎日、毎日書いていったのです。
学級通信の中のエピソードには、必ず子供たちの名前を載せるようにしました。子供たちは自分の名前を見付けると大喜びでした。また、名前を載せるということは、誰のエピソードなのかを保護者や子供たちにも知らせることになりますから、すべての子供たちをバランスよく観察しなくてはいけないわけです。そのため、記載した子供の名前は毎日名簿にチェックし、どの子供も同じ回数載せるように心がけました。大変な作業でしたが、自分がいかにすべての子供たちをバランスよく見てはいなかったかということにも気付かされます。そこで、チェックした名簿を確認しながら、「今日は、あまり見ていなかった、〇〇さんを中心に見ていこう」などと、自分の中で目標を立てて観察しました。また子供の良さを見付けたらすぐに付箋紙などにメモし、忘れないようにしました。初任時の数年のことではありますが、毎日続けたことで子供の良さを見つめる目が養われたと自分では思っています。

もちろん毎日学級通信を書くのは大変ですし、働き方改革が求められる時代ですから、若い先生に「ぜひ学級通信を毎日出してみてください」とお勧めするつもりはありません。しかし日々、子供の良さを付箋紙などにメモしていくだけでも子供を見る目を育てる上で有効です。しかも、付箋紙を保管しておいて学級懇談会で保護者に伝えたり、通知表の所見に記述したりと有効活用できるため、日々のちょっとした努力が仕事の効率化へもつながるので、こちらはぜひお勧めしたいと思います。

