子どもを主語にした学校づくりのために【木村泰子「校長の責任はたったひとつ」 #7】

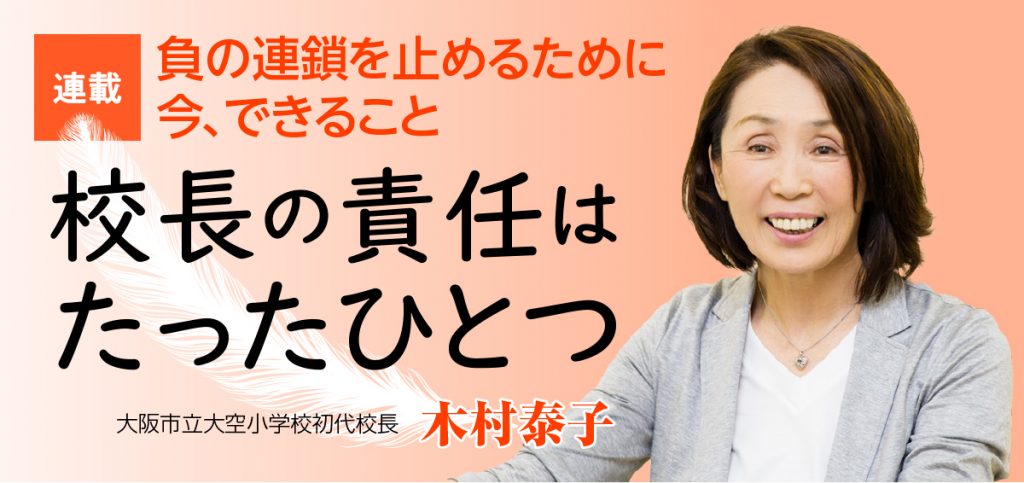
不登校やいじめなどが増え続ける今の学校を、変えることができるのは校長先生です。校長の「たったひとつの責任」とは何かを、大阪市立大空小学校で初代校長を務めた木村泰子先生が問いかけます。
第7回は、<子どもを主語にした学校づくりのために>です。
今、それぞれが抱えているリスクとは?
「すべての子どもの学習権を保障する学校」をつくるために、教員に必要不可欠な力は何なのかを問い直してみましょう。
時代が変わり、社会のニーズが激変し、保護者の価値観も多様になっている今、教員にこれまで求めてきた指導力の向上を、どれだけ声を大にして求めても現在起きている負のスパイラルが止まることはありません。子どもや保護者・教員や管理職もみんながそれぞれにリスクを抱えているように感じます。少し、整理してみましょう。
・学ぶ価値が見いだせない
・先生が怖い
・職員室に行くのが怖い
・学校には行きたいが行けない
・自分は叱られないが、叱られている子を見ると不安になる
・トラブルがあると事実確認をして解決されるが、よけいにいじめられるので親にも言えない
・周りの友だちも信じられなくなる
・みんなと違うところがいじめられる原因になる
・一人ぼっちになる
・大声で強い口調でどなりつけられ、子どもがおびえて学校に行きたがらない
・学校に助けを求めるとモンスターにされる
・管理職に訴えると子どもより学校を守る態度が見え見えで、教育委員会に言うしかなくなる
・教育委員会も学校も、自分たちの守りに必死で傷ついた子どもは切り捨てられる
・モンスターとみられ、ますます子どもは学校に行けなくなり、きょうだいまでが行けなくなり家庭は崩壊寸前になる
・保護者会が開かれても被害者である子どもが責められる空気になり、何一つ解決に進まない
・保護者同士が分断されていく
・地域で孤立し住めなくなる
・おかしいことがまかり通る学校体制に嫌気がつのる
・子どものために指導しているのに理解してもらえない
・「働き方改革」は時短ではない 自宅で休む時間がない
・トラブルが起きたら管理職は守ってくれない
・強い指導も社会に出て困らないためであり、自分には非がないのに責められ納得できない
・さぼっている教員に比べたら必死に働いているのに不公平だ
・子どもに寄り添っていると、ベテランの教員から毅然と指導しろと指導され、どうしていいかわからない
・職員室で孤立する
・保護者が感情的になり話にならない
・苦情対応で一日が終わってしまう
・保護者の要求を認めると教員から責められ、保護者を納得させようとすると教育委員会に訴えられ、精神的負担が増す一方だ
・教員が指導を受け入れない
・職員室がぎくしゃくした空気になり、誰もが疑心暗鬼の状態になり教員が分断される
・保護者の声を受け入れると一部の教員があらゆる手段を講じて管理職を責める構図ができる
・教育委員会からの圧が強く、精神がずたずたになり相談する相手がいない
・学校で孤立している
読者のみなさんの学校現場はいかがでしょうか。
学校の本質であるはずの「学びは楽しい」の言葉が遠のいていきそうです。これまでのやり方をどれだけ向上させても、今起きている負のスパイラルを変えることはできないのではないでしょうか。小学校の教員になりたいと願う若者が激減している原因もここにあるように思います。これらの負のスパイラルを、スッキリ切り捨てる戦略を練る必要があります。そのための手段として、まずは教員の「資質・能力」の転換を全教員で合意することから始めませんか。

