「ライ麦の根」全校朝会【校長講話】文例集 #5

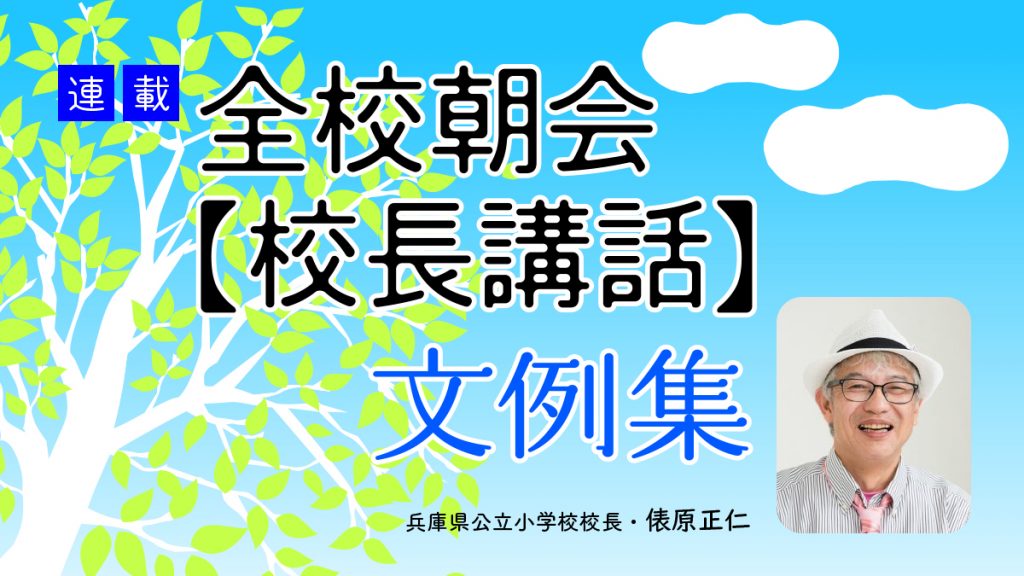
全校朝会での校長講話といえば、校長先生にとって腕の見せどころです。とはいえ、毎月、子供たちの知的好奇心を掻き立てたり、子供たちの心を整えたりする内容を考えるのは苦労するもの。そこで、本連載(月1回公開、全11回)では、学級経営や学校経営に関する多数の著書をもつ俵原正仁先生が、実際に使用したスピーチの全文を公開します。9月は講話「ライ麦の根」を取り上げます。
執筆/兵庫県公立小学校校長・俵原正仁
目次
9月のテーマはこう選ぼう
今回は、始業式で話す話題を紹介します。9月は、2学期のスタートということもあって、その月だけでなく学期を通じてがんばってほしいことや意識してほしいことなどを話題にします。
今回のキーワードは「根っこの大切さ」です。生きるすばらしさと見えないところでがんばる大切さを伝えていきます。
9月の講話「ライ麦の根」全文

今日から2学期が始まります。そこで、今日は校長先生が担任をしていた時に、始業式の日によく行っていた授業(※1)を紹介します。校長先生のクラスになったつもりでお話を聞いてください。「ライ麦の根」という授業です。
アメリカのオハイオ州の大学で、次のような実験が行われました。
木でつくった小さな箱の中に土を入れ、そこに一粒のライ麦の種をまきます。水を与えながら、数十日それを育てると、20cmほどの小さくて弱々しい一本の麦の苗が育ちます。そして、その小さくて弱々しいライ麦が、その生命を支えていくために一体どれほどの根を土の中に広げているかを調べました。箱を壊し、土をはらい、目に見える根はすべてその長さを測り、肉眼でははっきりと分からない根毛まで細かくく計量し、土の中にはりめぐらされたライ麦の根の長さをすべて測ったのです。
では、ここで問題(※2)です。ライ麦の根の長さの合計は、どれぐらいになったでしょうか?
①50cm
②200cm(2m)、校長先生より少し高いぐらいです。
③2500cm(25m)、学校のプールぐらいの長さです。
校長先生が担任をしていた時には、次のような答えをいう子もいました。
④5km。cmにすると、50000cmです。ここから三宮ぐらい(※3)までの距離になります。
⑤その他(※4)。ここには答えはありませんという意味です。「50cmより短い」と思った子や「5kmよりも長い」と思った子は⑤を選んでください。
答えは決まりましたか? 正解を発表します。答えは⑤の「その他」です。では、どれぐらいの長さだったのでしょうか? 20cmのライ麦の根の長さは、…………………(※5)なんと「11200cm」ではなく、「11200km」です。ここから三宮どころではなく、日本を飛び出して、アフリカにあるマダガスカルという国までの距離(※6)とほとんど同じです。めちゃくちゃ長いですね。
実は、校長先生は、この話を『生きるヒント』という本で知ったのですが、著者の五木寛之さんは次のような思いを書かれていました。
「風にそよぐ一本のライ麦が、その貧弱な生命をささえるために一万一千二百キロメートルの根を目に見えない土中に張りめぐらし、そこから必死で生命の糧を吸いあげつつ生きつづけているというのは、じつに感動的ではありませんか。」
校長先生もこの話を初めて聞いた時はとても驚き、感動しました(※7)。

ただ、「必死で生命の糧を吸いあげつつ生きつづけている」のは、ライ麦だけではありません。モンシロチョウもスズメも必死で生きています。もちろん、人間も同じです。人間には、11200kmの長い根っこはありませんが、心臓は24時間休むことなく動き続けています。「生きる」ってすごいことだし、すばらしいことだと思いませんか?
根の話題でいえば、相田みつをさんの有名な詩の一つに、「夢はでっかく 根はふかく」(※8)という根のことが書かれたものがあります。「大きな夢を持ちたいのなら、根が深くならなければいけない。反対に根が深くなればなるほど、夢も大きくなる」というような意味です。見えないところでがんばったり、当たり前だと思えることにていねいに取り組んだりすることが大切なんですね。例えば、5月に話したあいさつ(※9)も、生きていくうえで大切な根っこの一つです。
今日から2学期が始まります。生きているすばらしさを感じ取り、今、できることに一生懸命取り組み、でっかい夢をかなえるための根を育てていけるよう、がんばっていきましょう。これで、校長先生の話を終わります。

