「自由進度学習」とは?【知っておきたい教育用語】
近年、「自由進度学習」を導入する学校が増えてきています。自由進度学習が実践されるようになった背景から具体的な実践例、自由進度学習における課題を考えてみましょう。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴
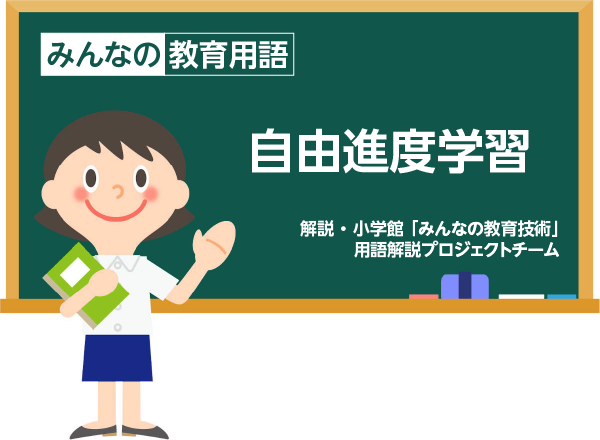
目次
「自由進度学習」とは
中央教育審議会が2021年1月に出した答申、「令和の日本型学校教育の構築を目指して」で示された「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現する先行的な実践として注目されている学習スタイルの1つが自由進度学習です。自由進度学習は、教師が計画する学習内容のフレーム内で、子ども一人一人が課題を自己決定し、計画を立てて自分の学習速度で進め、その過程で友達と相互に作用しながら学びを深めていくことを目指したものです。
自由進度学習が注目されるようになった背景
これまでの授業の多くは、同じ内容を同じ方法で、そして同じ時間で学ぶスタイル、つまり一斉・画一的に行われていました。この形態は、一定の内容を効率よく伝達することができますが、子ども一人一人の学びへの興味・関心を十分に生かすことは難しく、結果として受け身の姿勢を助長することになってしまいます。
これでは、現行の学習指導要領で示されている、子ども一人一人の興味・関心や発達の状況等を踏まえてそれぞれの個性を伸ばし、資質・能力を高めていく教育は難しいということになります。その授業改善の方策の1つとして「自由進度学習」が取り上げられるようになりました。2022年4月に組織された、中央教育審議会の「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会」では、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を通じて、主体的・対話的で深い学びの実現を目指すための方策等の検討の中でこの学習スタイルも紹介され、話題となりました。

