「探究学習のプロセス」とは?【知っておきたい教育用語】
「探究学習」とは、自ら課題を設定し、その解決に向けて情報を収集したり整理・分析したり、まとめ・表現したりしながら周囲の人と協働して進めていく学習活動です。具体的にどういったプロセスを経て行われる学習なのかを考えてみましょう。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・宮崎猛
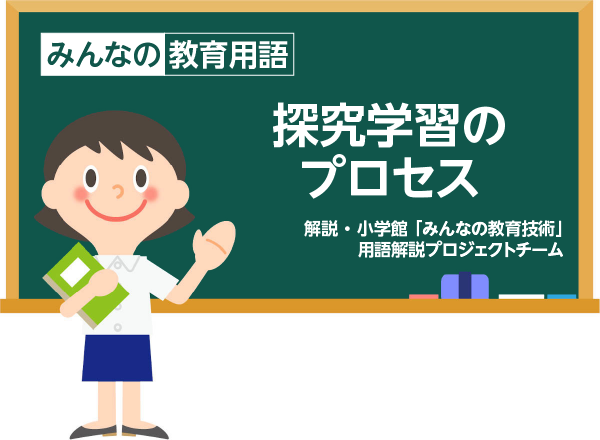
目次
「探究学習」とは
現行の学習指導要領で重視されるようになった学習方法です。問題や課題を解決するプロセスが探究で、そのようなプロセス(探究活動)を取り入れた学習が探究学習です。
「総合的な学習の時間」では探究学習を通して「探究的な見方・考え方」を働かせることが求められていますが、「総合的な学習の時間」に限らず、すべての教科・科目で探究的な活動の充実が必要とされました。2022年度より年次進行で実施されている高等学校の学習指導要領では、「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」となり、古典探究・地理探究・日本史探究・世界史探究・理数探究・理数探究基礎の7つの探究学習課目が新設されました。
探究学習が重視されるようになった背景
現代社会は、情報化の進展に急激に変化し、人工知能(AI)の登場で変化の勢いは加速しています。狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会(Society5.0)を目指すことが求められるようにもなりました。様々な知識や情報が情報通信技術で繋がるようになるなかで、Society5.0では人間が主体となり、人工知能(AI)を活用しながら社会を変革し、新たな価値を創造するとともに、豊かで快適な社会をつくることが求められています。人工知能(AI)は知識を集積し、整理するだけではなく、その知識を理解し、思考するようにもなってきたといわれています。学校教育でこれまで主に育成してきた知識や理解はICT技術AIが取って代わるようにもなりました。
こうした変化のなかで、学校教育には、変化に主体的に向き合い、「何のために」を問う力や「何が必要か」を自ら設定し、解決していく力の育成が求められるようになったのです。「答える」ことよりも「問いを立てる」や「問う」ことが重要になったということもできます。全国学力・学習状況調査やOECDが実施する学習到達度調査(PISA)においても、探究プロセスを意識した児童生徒ほど各教科で好成績を残しているという分析結果も報告されています。

