総合的な学習の時間で、子供の主体性を生かした課題設定とは? 中編【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#13】

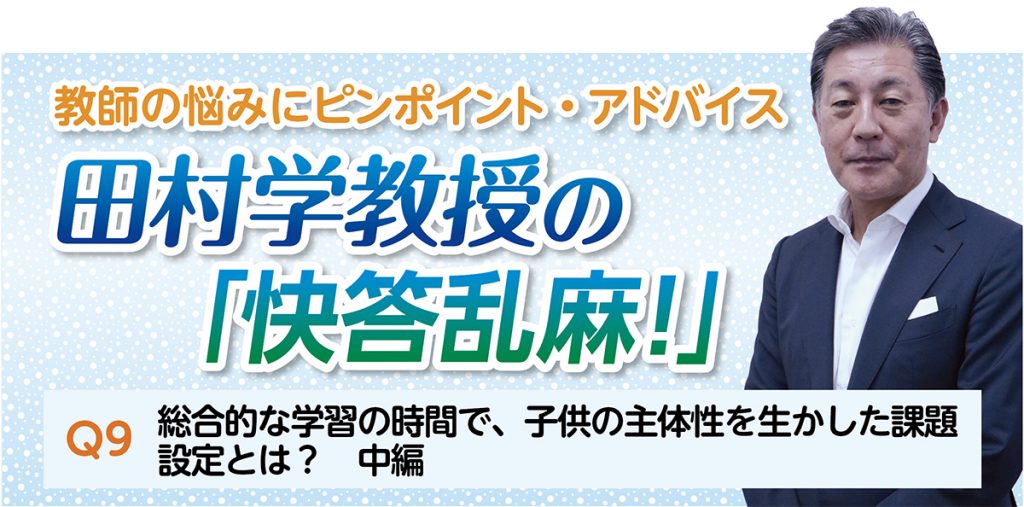
先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回は、総合的な学習の時間の課題設定の考え方について、さらに詳しく説明をしていただきます。
※
Q8 私は教師生活10年ほどの間、あまり総合的な学習の時間に力を入れてきていませんでした。しかし最近、その大切さを感じ、改めて単元づくりを学びたいと考えています。学校によって学年ごとにテーマが設定されていたり、学級ごとに自由に設定できたりと状況は異なりますが、その中で子供の主体性はどの程度生かして課題設定をすればよいのか、教師としてリードしてはいけないのかなど、単元づくりの基本を教えてください。(30代・中学校)
子供が設定した課題は、はたして期待される学びが生じるものなのかを考える
A 前回、総合的な学習の時間(以下、総合学習)において、生徒自身が追究課題を決めなければならないというように、先生方の発想が限定される危険性がある一方で、大事なことは、期待される学習が生まれ、期待される資質・能力が育まれることだということをお話ししました。また中学生(や高校生)の学習では、個の課題設定も考えられることや、先生が方向性を示した上で、個々が課題設定をするために思考ツールを活用していく方法などについても説明をしました。
ただ子供たちが設定した課題は、その地域性や学齢などの条件の中で、はたして期待される学びが生じるものなのかをしっかり考えていくことが必要です。
繰り返しになりますが、子供自身が課題を探究していく学習過程で資質・能力を育むためには、プロセスが充実していかなければいけません。もし、探究の過程で子供が行き詰まって、どうにもこうにもいかなくなってしまうような課題では力は付きません。逆に探究の過程で次々に問いが生まれ、それを調べたら、次に新たな人との出会いがあり、さらに問いが深まり…ということが起きれば起きるほど、期待される資質・能力が付く可能性が高まるわけです。となると、子供自身が最初に設定した課題は、本当に探究が充実した形で連続的に起き得るものなのかどうかを考えることが重要になります。
例えば、地域にそれに関わる人がいるかとか、あるいはそれにまつわる施設があるかとか、実際に自分が出かけてみることができるかとか、あるいはそれに関わる情報を子供たちのもつ情報収集能力の中で手に入れることができるかどうかといったことが大事なポイントです。ですから、小学校の子供たちであれば、自分たちの身近にその素材があるかどうかが大事になるし、多くの先生方もそれを意識されていることでしょう。前回、「森の植生」という例を示しましたが、もし学校の近くに森があるならば、「よし森に行って、これを見てこよう」「今回は、前回気になったこれを調べてみよう」と、次々と展開させることができますが、距離が離れていてバスや電車で行かなければならないとなった途端に、それを期待することが難しくなるわけです。

ただし経験が少ないと、「この学校で、この学年だと、このテーマを追究していくのは難しそうだな」と的確に判断するのは難しいかもしれません。そういう時には、周囲の先生や地域の人の力を借りるのがよいだろうと思います。
例えば以前、私の研究室に長期研修に来ていたある先生の学級で、総合的な学習の時間に、地元の市民の森について調べ、よりよく活用できるように発信していく学習をしたことがありました。その学習を始める時、最初に本人の中にあった取組のイメージには一定の限界があるわけです。しかし、研究室の中で他の先生方と共に話し合ううちに、「こんなことができそうだ」「あんなこともできるのでは?」とアイデアが出されて、イメージが広がっていきます。その中で例えば、「その学齢なら、自分たちでその森のすてきなところを写真に撮って、写真展で発信してみたらどう?」といったアイデアが出されるわけです。そうすると、その先生自身にもイメージが湧いてきて、実際に実践を進めるうちに多様な人たちも動いてくれて、それが市議会の人たちにも伝わり、せっかくの市民の森を生かすような予算を付けようというように、市政や市行政までも動かしていったわけです。
それはすばらしい実践なわけですが、最初に一人だけでそれを考えることは難しかったように思います。しかし仲間がいたり、話題にするチャンスがあったりして、とりわけそこに経験している人が周囲にいれば、「これもできそうだ」「あれもできそうだ」と追究の可能性が広がっていくのだと思います。やはり、そのような仲間や同僚にまず相談してみることが大事ではないでしょうか。
加えて、先行実践事例の資料を見ていくことも大きな力になると思います。実は、私自身が上越教育大学附属小学校時代に、学校で実践研究を行った後、実践事例をまとめた本が何冊か研究室の中に置いてあったのです。その中にはどんな内容に関してどんな活動ができるかといった事例がたくさん示してありました。それを前記の先生に資料として見せたとき、「こういうものが早く手に入るといいですね」と話していました。経験がまだない先生方は、このような先行の実践資料を探して参考にすることも効果的ではないでしょうか。

