多くの失敗をし、課題を指摘されてきたことが、授業改善の大きな契機【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第9回】
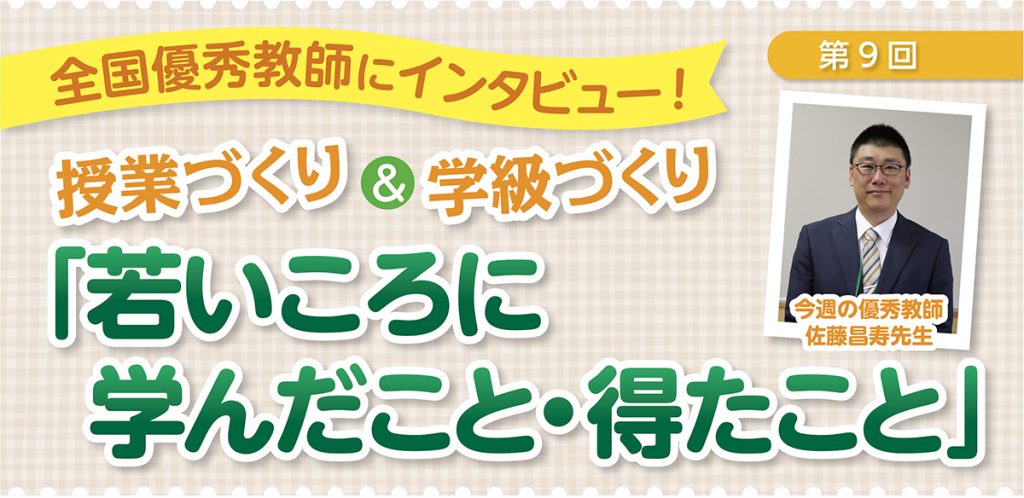
前回、佐藤昌寿教頭が30代の頃、授業を通して学級づくりを行うという考え方をもつようになった経験などを紹介しました。今回はその後、新潟市のマイスターに認定されるようになる過程などで学んだことや若手の先生方へのアドバイスを紹介していきます。

目次
マイスター養成塾で、徹底的に授業公開をして指導を受けた
前回、お話ししたような経験をした後、さらに授業づくりをブラッシュアップする契機になったのは、新潟市のマイスターに認定されるためのマイスター養成塾に参加したことです。その当時は(認定を受けるために)1年間に8回(うち専門教科は5回)指導案を書き、授業公開を行うことになっていました。それまでに、先にお話ししたような授業改善の方法をとってはいましたが、やはり変わりきれていなかったところもあり、実際にマイスター養成塾の指導者である先生に、以前指摘されていたことを改めて指摘されたこともありました。その際に具体的に、「もっとこうしたほうがいい」と指導していただいたこともあり、少しずつできなかったこともできるようになっていったと思います。
ただ、1年間に決められた8回の授業公開をするだけでは認定を受けられないのではないかと思い、自ら授業公開の回数を増やして10回以上の授業公開と指導案作成を行い、指導者の先生にも来ていただいて指導を受けました。そのようにして、毎月指導案を書き、授業公開をして、ふり返りのレポートも提出してと、たたみかけるようにやっていったことで、ずいぶんと授業が変わっていったと思います。
ちなみに、これらの授業についてもすべて文字起こしをやっていました。ただ、最初は全部を起こしていたのですが、次第に「今回は導入部分を」「次はまとめとふり返りを」というように、自分が課題意識をもっているところに絞り込んで文字起こししながら省察し、改善を図っていくようにしていきました。とても大変でしたが、この1年が自分自身の授業のいろいろなものをすべて変えてくれたと思っています。それまでも、自分で変えようとがんばってはいましたが、それだけでは限界がありました。自分一人では甘えが出てしまう部分もありますから、そういう意味では、意を決してマイスター養成塾に飛び込み、徹底的に授業公開をして指導を受けたことがよかったと思っています。

