学級経営については、日々の教科指導の中で行うようにする【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第2回】
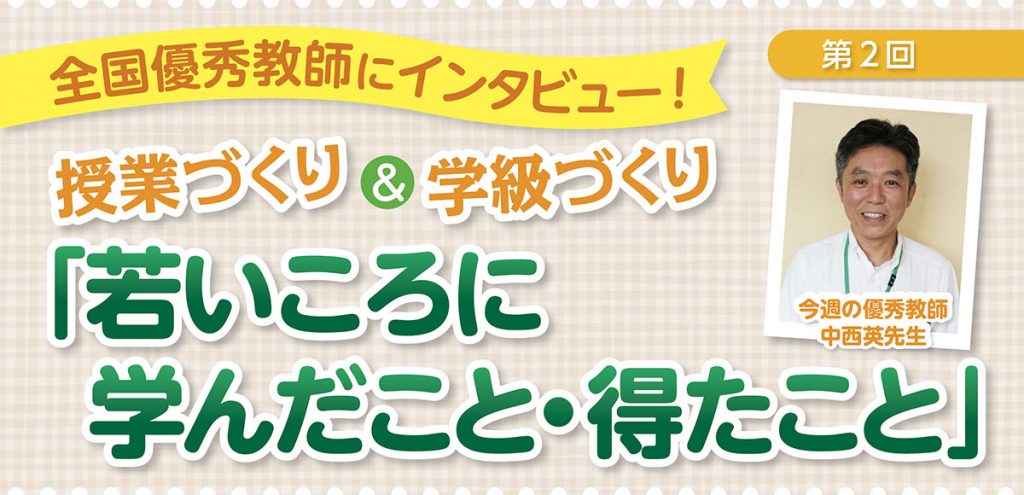
全国の優秀教師が何を学び、どんなふうに教師力を身に付けてきたかを紹介するこの企画。前回に続き、宮崎県スーパーティーチャーの中西英教諭(算数)のPart2で、研究校に在籍した30代以降に、何をどのように学んでいったかなどを紹介していきます。

目次
筑波大学附属小学校の先生と飲みながら、算数に関する多様な話を
宮崎大学教育学部附属小学校への異動直後の授業研究会を経て、改めて算数の授業づくりへの意識を高めた私は、以前以上に多様な本や教育誌を読み、自分自身の実践に落とし込んで子供の姿をていねいに見とって省察していきました。そして、そこで見た子供の姿を通して授業改善を図ったり、改めて深く理論を理解し直したりしていくような実践を繰り返していったのです。
そんなとき、ちょうど図書文化社の「指導と評価」という雑誌に、筑波大学附属小学校の正木孝昌先生が連載をされていました。それは、「算数の基礎基本とは何か」というような内容の連載だったのですが、ちょうど私自身も同じ問題意識を抱えていたために、非常に感銘を受けたのです。そこで、出版社を通じて正木先生に連絡をとり、先生の連載に感銘を受けたのでお目にかかってお話を伺いたいとお願いをしました。すると、正木先生は「ぜひ、東京にいらっしゃい」と快く言ってくださったのです。そこで、休みの日に東京に出かけて池袋でお目にかかると、一緒に飲みながら算数に関する多様なお話をしてくださいました。それが30歳くらいの頃ですから、今から25年くらい前の話です。
そこから毎年、筑波大学附属小学校の算数研究会に出席するようになって、筑波の考え方を取り入れながらさらに実践を進めていきました。20代の頃は独学や身近な学校の先生に教わって学んでいたわけですが、附属小学校に入ることで少し視野が広がり、30代では全国的な研究会などにも出かけて学ぶようにもなっていったわけです。
ただし、私の在籍する宮崎大学教育学部附属小学校には、学校が受ける多様な研究があり、自分自身の授業研究以外も非常に多忙でした。そうした研究の1つの幹事を任されたのですが、それは文部科学省の奥村高明教科調査官(当時)や宮崎大学の中山迅教授たちが、全国の学校(200校近くが参加)で一斉にケナフの種をまき、成長観察記録を共有していく「全国発芽マップ」というものでした。ちょうど学校にインターネットが入ってきた時期で、文部省と通産省(当時)がタイアップして、それを活用した実践研究を行う「100校プロジェクト」という事業の中の1つです。その研究では、例えば、沖縄の学校で5月何日に発芽したということが写真と共に掲示板やメーリングリストに報告され、それがどんどん北上していって6月何日に北海道の学校で発芽したというものを共有していくわけで、その幹事は非常に多忙でした。ですからこの研究に携わった時期は、算数の研究には十分に時間が取れない時期でもあったのです。
ただし、これは国のプロジェクトでしたから、理科教育学会とか科学教育学会といった学会の大学の先生や熱心な現場の先生と知り合うことができたのは財産の1つです。また、研究に関わることを通して、自分自身で科学研究費助成事業の審査を受けることもできるようになりました。そのおかげで、自分のやりたい研究について審査を受け、科研費によって学会発表の費用や調査出張費などを出せるようになり、行動範囲やできることもより広がったわけです。
この方法については、現場にいる多くの先生はご存じないのではないのでしょうか。しかし、こうした方法を知ることによって、より多くの先生や研究者と出会うことができ、より多くの良い授業を見る機会にも恵まれました。それは私にとって非常に大きな財産ですし、もっと現場の先生もこうした事業を活用されたらよいと思います。


