リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #36 どうして育ててもらえないの?|吉川裕子 先生(立命館小学校)

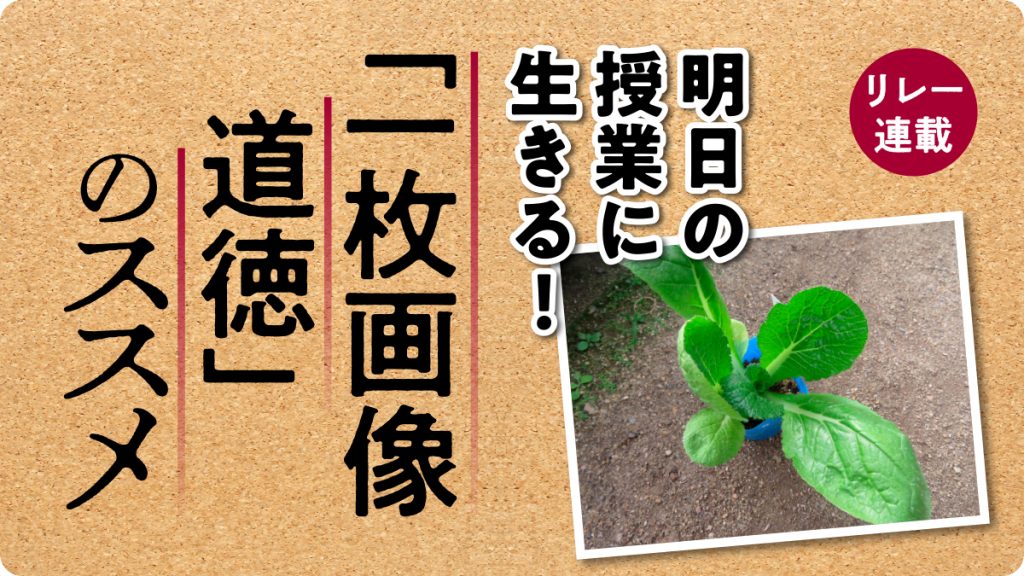
子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。今週は吉川裕子先生のご執筆でお届けします。
執筆/立命館小学校教諭・吉川裕子
編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和
目次
はじめに
はじめまして。
京都の立命館小学校の吉川裕子と申します。
私が勤務している立命館学園には、四つの附属の中学校・高校、一つの小学校があり、それぞれの学校が特色ある教育を展開しています。
2021年度、附属校の一つである立命館宇治高校から2名の生徒さんが、「コア探究」の授業の一環として、小学2年生に「食育」の授業をしに来てくれました(テレビ局主催のプレゼンコンテストに挑戦されていたので、取材もありドキドキしました)。
今回ご紹介する「一枚画像道徳」の授業は、その田中愛乃さんと福田奈津実さん(現在大学2回生)に教えてもらった内容です。お二人の活動をたくさんの先生方にも知ってもらいたいと思い、この題材を選びました。
1.授業の実際
対象:小学1年生
主題名:どうして育ててもらえないの?
内容項目:節度、節制(A―3)
ねらい:食べ物は多くの人の努力と勤労によって作られていることに気付く。
授業のはじめに、生活科で種をまいてアサガオを育てた経験を交流します。他にも植物を育てた経験をしている児童がいるので、交流します。
●チューリップの球根を植えた。
●家でトマトを育てた。
●おじいちゃんが畑でキュウリを育てていた。
●ミカンの木を家で育てている。
多くの児童が家庭や保育園、幼稚園で野菜を育てた経験があることが分かりました。そこで、野菜を育てた経験について話し合います。
●家で野菜を育てて食べたら、おいしかった。
●アサガオは種をまいたけど、野菜は少し大きくなったものを植えて育てた。
●それは「苗」っていう。
●おうちの人と一緒にお店に苗を買いに行った。
野菜は「苗」から育てることが多いことを確かめ、以下の写真を提示します。

発問1 この白菜の苗はこの後、捨てられることになっていました。なぜでしょう。
●売れ残ってしまった……?
●おいしそうじゃなかった……?
●葉っぱが少し曲がっている……?
●葉っぱが黄緑っぽい……?
この苗は「規格外」として、捨てられることになっていたものです。
例えば、茎や葉が曲がっているもの、葉が緑色でないもの、野菜農家の元に届けられるタイミングで、大きすぎたり小さすぎたりするものなどは、捨てられてしまうことがあります。
そのような規格外の苗でも、育てれば同じように野菜が収穫できることを伝えます。
発問2 種から野菜苗になるまで、どのぐらいかかるでしょう。
●1か月?
●2か月?
●半年?
野菜苗の多くは、苗農家で育てられます。
野菜苗としてポットに入って売られる状態になるまで、野菜の種類にもよりますが、2か月ぐらいかかるそうです。何回か植え替えをしたり、毎日様子を見ながら水やりの量を調整したり、手間暇をかけて育てられます。そして、野菜農家に届けられたり、小売店で売られたりします。
発問3 野菜がみんなの口に入るまでに、どれぐらいの人が関わっているのでしょう。
●種から苗に育てる人。
●苗から野菜を収穫するまで育てる人。
●収穫してからトラックなどで運ぶ人。
●お店で売る人。
●料理する人。
●どの仕事も一人だけではできない仕事だから、たくさんの人がいる。
●一つの野菜だけで、何十人も関わっているかもしれない。
例えば、今日の給食の野菜一切れにも、これまで思っていなかったほど、たくさんの人が関わって自分たちの口に入っていることに気付きました。

