第58回 2022年度 「実践! わたしの教育記録」特選作品 北島幸三さん(沖縄県今帰仁村立今帰仁中学校教諭)
クラウドファンディングを通して中学生が学んだこと
〜ICTを活用したPBLの可能性〜
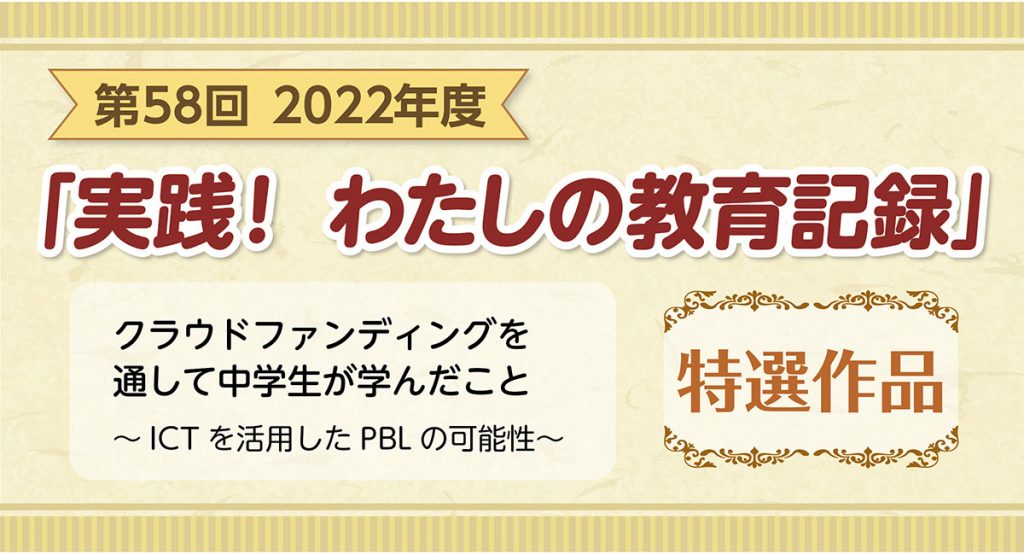
目次
1 はじめに
コロナウイルスの流行は、子どもたちから多くの教育機会を奪っていった。全国一斉休校に始まり、その後も学級閉鎖が繰り返された。職場体験、修学旅行、運動会、合唱祭、各種部活動の大会…さまざまな行事や大会が中止や縮小に追い込まれた。
2021年度、私の校務分掌は3学年主任。中学校生活を通して、コロナ禍の影響を色濃く受けてきた学年を受け持った。感染対策のため一度も送り出す立場で卒業式に参加することのないまま、彼らは自分たちの卒業式を迎えることになった。
卒業式を一月半後に控えた1月終わり、ある提案がPTA役員会から私のところに届いた。「コロナでさまざまな制限を受けた彼らに、せめて最後は思い出深い卒業式をプレゼントしたい。卒業式でバルーンリリースを行えないだろうか。予算はコロナの影響で使えなかったPTA予算の中から捻出できる。どうだろう」そんなお話をいただいた。大変ありがたい申し出ではあったが、お話を伺った時、「このまま、やってもらうだけで終わりにしていいのだろうか」…という思いが私の中に生まれた。それは、コロナの影響をあらゆる場面で受けてきた彼らだからこそ、「できなかった」「やってもらった」という思い出ではなく、「コロナがあったからこそ…挑戦できた!」、その実感を持って卒業させることはできないだろうかという思いであった。
私はPTA役員会に取り組みを待ってもらうことをお願いし、子どもたちに「予算集めも含めて、自分たちでこの企画を動かしてみないか」と投げかけてみることにした。
2 クラウドファンディング(下準備)
2022年2月2日(水)放課後、卒業を迎える3年生96名中、推薦等で進路の決まっていた27名に集まってもらった。私からは、①PTAが卒業式で30個程度のバルーンリリースを提案していること。②その予算はPTAが出してくれること。③しかし、私はPTAではなく、君たち自身でこの企画を実現できるのではないか、君たちならそれができるのではないかと考えていること。④必要な予算集めについては、君たち中学生によるクラウドファンディング(以下クラファン)を考えていること。⑤ただし、PTAから企画を引き取った後、クラファンで予算が集まらなかった場合は、企画は実行できないこと。⑥その上で、もし君たちに自分たちの手でやりたいという思いがあれば、PTAには断りを入れること。⑦その是非について意見を出し合い、話し合ってもらいたいこと。⑧もし「自分たちでやる」となった際には、私が世話人として活動をフォローすること。⑨ただし、それは大人の介入が必要な部分(クラファン業者への申請や口座の指定など)に関して関わるのであって、クラファンページの作成・運営や、その他の協力の呼びかけ等の実務に関しては手を貸さない(ただし、時にアドバイスとしての口出しはする)ことを伝えた。
私の提案を受けて話し合いが行われ、その後27名全員がそれぞれの意見を表明した。その意見を踏まえて多数決が行われ、結果、全員が「自分たちでやる」を選択した。その決定ののち、企画を先頭に立って動かしていく実行委員に10名が立候補。中学生によるクラファン&バルーンリリースの企画は、最初の一歩を踏み出した。

