子どもの事実から学び合う、新しい校内研修のあり方とは【菊池省三流「コミュニケーション科」の授業 #18】


教師と子ども、子ども同士のコミュニケーション不足こそ今の学校の大問題! 菊池省三先生が、1年間の見通しを持って個の確立した集団、考え続ける人間を育てる「コミュニケーション科」の授業の具体案と学校管理職の役割を提示します。
第18回「コミュニケーション科」の授業は、<子どもの事実から学び合う、新しい校内研修のあり方とは>です。
目次
客観的な “事実” を示す授業動画を活用
ようやく収まったかに思えた新型コロナウイルスの感染が、今年(2022年)に入ってから見る見る間に拡大し、学校教育に再び大きな影響を及ぼしています。
この2年間ほど、これまでの授業のあり方を見つめ直す機会はなかったのではないでしょうか。私自身、3学期に予定していた学校での授業や研修会の延期が相次ぎ、時間に余裕ができたことから、授業についてじっくりと見直すようになりました。
授業を振り返る際に最も役立ったのが、自分の授業動画です。自分で書き留めたノートや写真、参観者からのレポートなど、授業を思い起こす資料は様々ですが、そこには、自分の思い込みや記憶違い、参観者の主観など、どうしても曖昧な要素が多くなり、報告者の“視点”が入ってしまいます。一方で、動画には確実な“事実”が残っています。もちろん、すべての事実が映っているわけではありませんが、客観的に見直すことができることに大きな意味があります。
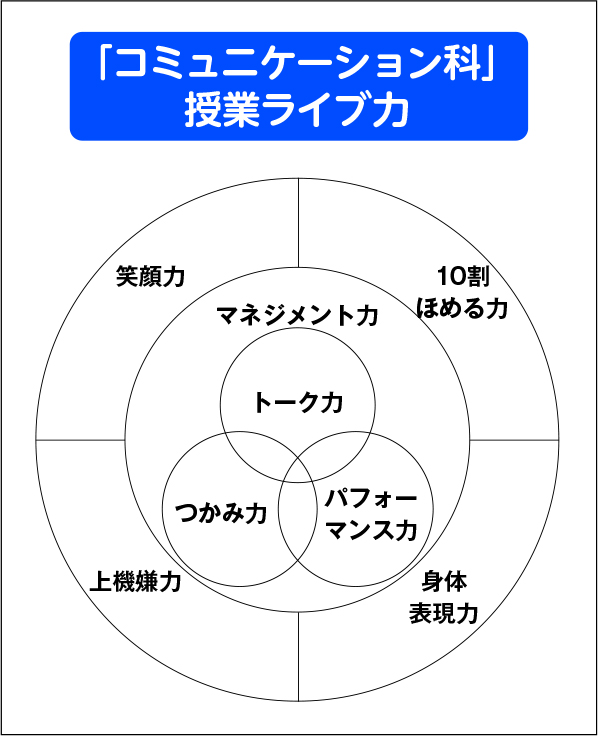
公立小学校で教師をしていた頃、時間があるときは、授業の写真を撮ったりビデオを回していました。自分の授業力向上のためだけでなく、子どもたちの学びの姿を残しておきたいと考えていたからです。
当時、授業や学級経営について学び合うサークル「菊池道場」をほぼ毎週末、自宅で開いていました。そこでは訪れた先生方と一緒に授業動画を閲覧し、意見を交わしていました。気になる場面で動画を止め、「なぜこういう声かけをしたのか」「この指示はどういう意図か」等、先生方の質問に答えていく、ストップモーションの方法で進めましたが、話し合いが過熱すると、3分間の授業の導入場面について2時間もかけて話し合うこともしょっちゅうでした。参加者は、小学校だけでなく、中学校教師や保育士、学生、一般企業に勤める社会人もいました。そういう人たちも積極的に参加することができたのは、授業動画という、客観的な“事実”を示す材料があったからこそです。時には、小学校の教師では思いつかない視点からの意見も出され、私自身も多くのことを学びました。
授業動画は自分の実践の振り返りだけでなく、学び合う材料としても、大いに役立つことを実感した私は、全国の学校に呼ばれるようになってからも、授業動画を見ながら話し、参加者に意見を出してもらう学び合いを大切にしています。
全員参加型の研修を
校内研修に呼ばれると、疑問に感じることがあります。担当教師が作成した指導案を見ながら、意見を交わし合うという“昭和”時代の研修から未だ抜けきれず、実のある研修になっていないのです。
発問や挙手指名のあり方、時間の配分など、授業の観点が“教師”に置かれ、学び手の中心である “子ども” の姿に目が行かないのです。また、指導案や資料が中心となるため、意見を求めても、一部のベテラン教師が述べるだけ。経験を十分に積んでいない若手教師が意見を述べるのはなかなか難しいのが現状です。このような研修スタイルは得てして、ベテランから若手への一方的な“指導”の場となり、全員参加型の研修とはほど遠いものになってしまいます。そのような一部の参加者だけで進める形骸化した研修ではなく、全員が参加できるよう、授業動画を活用するのです。
授業動画のストップモーションは、全員が参加できる研修として非常に効果的です。校内研修会でもぜひ活用してほしいと考えています。


