【木村泰子の「学びは楽しい」#22】2023年をふり返って~ある授業で出合った子どもたちの言葉から~

子どもたちが自分らしくいきいきと成長できる教育のあり方について、木村泰子先生がアドバイスする連載第22回目。今回は、この1年で一番印象に残った授業を紹介しながら、2023年をふり返っていきます。(エッセイのご感想や木村先生へのご質問など、ページの最後にある質問募集フォームから編集部にお寄せください)【 毎月22日更新予定 】
執筆/大阪市立大空小学校初代校長・木村泰子
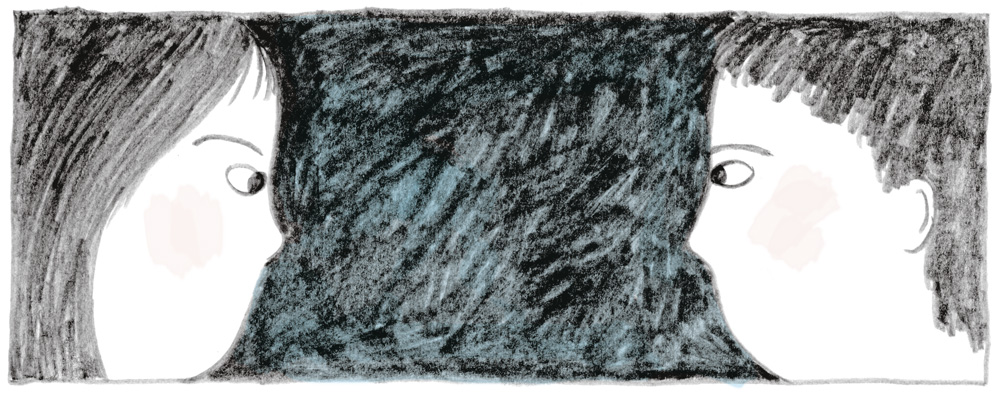
目次
なぜ子どもたちのつらい事実がなくならないのか
2023年も終わりに近づきました。先生たち、学びを楽しんでいますか。
メディアが教員の世界を「ブラック企業」だの「教員のなり手がいない」だのと報道すればするほど、学校現場は窮地に陥っているように感じます。何よりも子どもがその報道をどのように受け止めているかを想像すると、何一ついいことはないでしょう。少し立ち止まって、この機会に2023年の1年をふり返りませんか。
私の学びはこれまでとは大きく違い、全国のみなさんとご一緒に様々な学びをさせていただきました。自分でも驚くほど、毎日のようによく動いています。そして、行くところ行くところで、子どもたちに向き合っている先生たちとつながっています。どこでもみなさん必死で「自殺・不登校・いじめ」過去最多の子どもの事実をなくそうと行動されています。それなのに、なぜ、残念なつらい子どもの事実がなくならないのか、私たちは今ふり返る必要があるでしょう。
「受ける研修」から「求める研修」に
「教える授業」から「学ぶ授業」への転換が求められている今、研修も当然、転換が必要です。このことを私自身が目的にし、ブレないで研修をしようと試みてはいるものの、なかなか目的を達成できていない現実があります。もちろん、私自身の力不足が原因でもあると思いますが、それを棚に上げて語らせてください。
「求める研修」のためには、自分の言葉で語り合う対話が不可欠です。しかし、研修会場で問いを投げかけるのですが、みなさん、自分の言葉で語ることに不慣れというか、発言を躊躇されます。どうしてなのでしょうか。
教員研修も管理職研修も同様の空気が生まれます。みんなの中で、自分の考えを語る経験をもってこなかったのではないでしょうか。自分の言葉をもたない限り、「求める研修」にはなりません。これは子どもの授業でも同様のことが言えます。先生たちが自分の言葉で語るという当たり前を経験してこなかった弊害が子どもとの授業に表れているのではないでしょうか。

