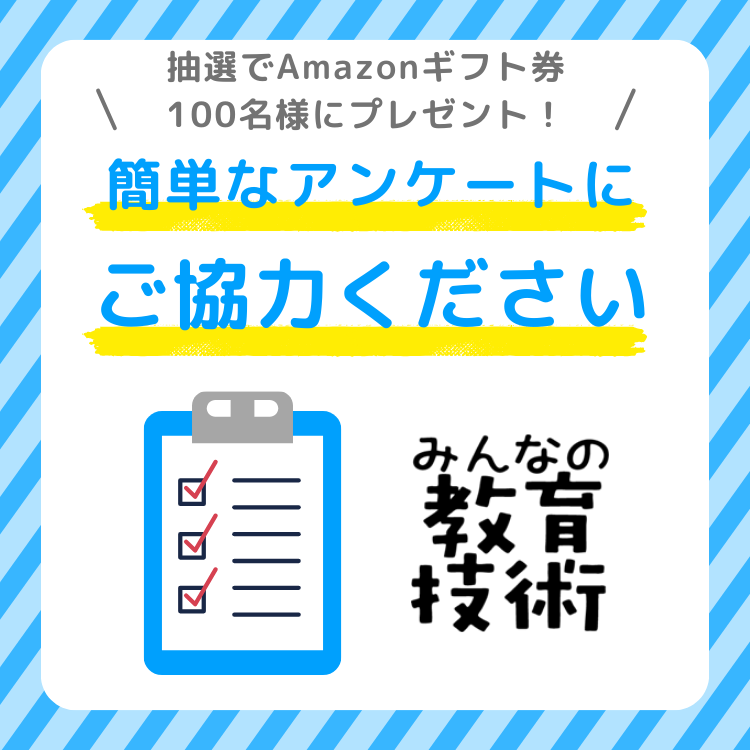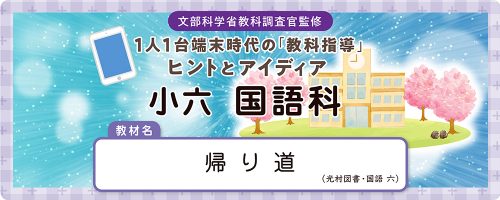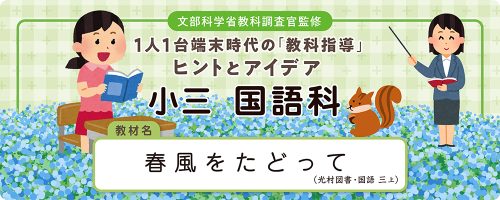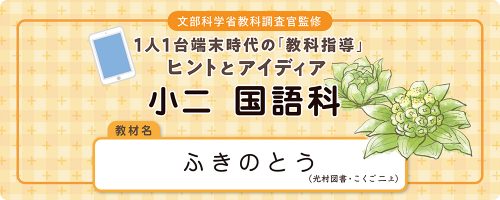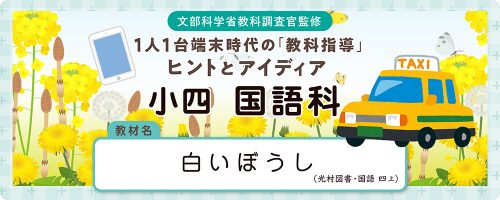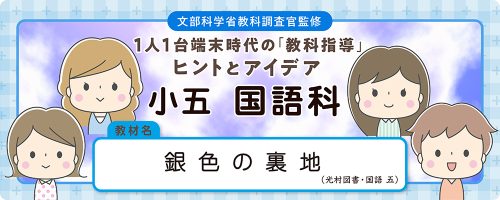子供の提出物チェック・採点・コメント術―子供たちの力を借りて、時短&省力化も実現しよう

学習ノート、テスト、プリント、作文……。毎日の提出物を迅速かつ的確にチェック、コメントすることは、子供たちを伸ばす上で大切な仕事です。とはいえ、それが担任にとって大きな負担であることも事実。スピードと丁寧さを両立させつつ、できるだけ負担を軽減する工夫や、子供たち自身にチェックを委ねるシステムづくりについて、宮城県公立小学校教諭・鈴木優太先生が解説します。
執筆/宮城県公立小学校教諭・鈴木優太

鈴木優太(すずき・ゆうた)●宮城県公立小学校教諭。1985年宮城県生まれ。「縁太(えんた)会」を主宰する。『教室ギア55』(東洋館出版社)、『日常アレンジ大全』(明治図書出版)など、著書多数。
目次
対面型よりも「横並び型」で
授業中、子供たちが一人一人ノートやプリントを教師の所へ持ってきて、採点やチェックをする場面があります。私はこのチェックを、子供と向き合う一般的な対面型では行わず、担任と子供が肩を並べる「横並び型」で行っています。
対面型で行う場合、ノートを「くるっ」と回す作業が発生します。この「くるっ」が原因で、学びのスイッチがオフになってしまう子もいます。横並びで「同じ方向」から「同じノート」を見ながら声をかけられる方が、子供たちにとっては安心感が高く学びやすいのです。
具体的にどうやるのかは、下のイラストと説明キャプションをご覧ください。

こうしたチェックの際には、長い行列や待ち時間をつくらない工夫も必須です。
そこで、子供立ちの動線を「一方通行」(上イラスト参照)にしています。
はじめは「1問限定チェック」にして、スピーディーに採点していきます。その後、「5問目までの自己採点チェック」など、あえて時間差が生まれる課題を出すなどして、緩急をつけて取り組んでいます。
平等に回収できる「班番号」
授業の中で取り組んだノートやプリント類は、「班番号」を活用して回収します。
「班番号」とは、班内の座席に1・2・3・4の番号をつけたものです。次のように指示を出します。
1番は、ノートを開いて集めます。
2番は、プリントの向きを揃えて集めます。
3番は、お便りを取りに来てください。
4番は、次の時間にお願いします。

一日の中で全員が万遍なく仕事をします。
学級で平等に仕事を任されるシステムが、学級への所属感や安心感を育みます。班で回収したノートやプリントは班ごとにまとまっているため、返却もあっという間にできるという利点があります。