たこ焼きを作ろうとして、桃ができたことはありますか?<アート思考を育むアート鑑賞vol.1>

中学・高校の美術教師として行ってきた授業内容を一般向けに書き下ろし、19万部突破のベストセラーとなっている『13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)の著者・末永幸歩先生。
今回は、末永先生が九州大学で行ったアート・シンキングの授業から、教師人生に役立つアート思考のエッセンスをご紹介します。

目次
鑑賞についての違和感
今回の記事は、九州大学大学院芸術工学府(ストラテジックデザインコース)で行われたアート・シンキングの授業(2022年7月2日から全8回)をもとに構成しています。
この授業の主題は、「自分なりのものの見方でみる」というもの。
いわゆる対話をしながら進めていく美術鑑賞なのですが、従来の「作品をありのまま見る」鑑賞スタイルについては、末永先生自身に違和感があったとのこと。
今回の授業を通して、自分なりの考えを以下のように再認識したそうです。
■みるって視覚だけのこと?
五感でみたり、想像によって目には見えないものをみたりすることも「みる」である。
■対話が深まるって、「みんな違う考えだね」で終わること?
対話が深まるとは、相手のまなざしになって「みる」ことにより、今まで見えなかったものが見えたり、新しい想いや考えが生まれたりすること。
■「作品とのやりとり」によってもたらされるものは、観察力?
作品の中に全ての答えが詰まっているという前提で、見落とさないように見る「観察的な見方」を磨くのではなく、作品とのやりとりによって自分の想い(主題・興味・問い)に気づく方が価値がある。
これらを頭の片隅に置きながら、読み進めてみてください。
鑑賞する作品は、「龍虎図屏風(りゅうこずびょうぶ)」の高精細複製品(京都文化協会とキヤノンが推進する「綴プロジェクト」制作)。17世紀(桃山時代)の長谷川等伯の作品で、原本はボストン美術館に所蔵、複製品は大分県立美術館に所蔵されている作品です。

この講義の流れは大きく以下の三部構成になっています。
① 龍虎図屏風を鑑賞
② ①によって自分の中に芽生えた想いをもとに工作する
③ ②を鑑賞
まず、この記事では、「①龍虎図屏風を鑑賞」の講義から、「先生のためのアート思考」をひもといていきます。
大人は子供よりも◯◯と△△に頼りすぎている
講義の冒頭、末永先生は自身が監修を務める教育番組において、一般の5歳の男の子が作ったという作品を紹介しました。
それは、折り紙や毛糸、紙コップ、絵の具などを使って食べ物や飲み物を工作したものでした。

「この子は最初、たこ焼きを作ろうとしていたそうなんです。ここにたこ焼きがありますよね。たこ焼きの隣には様々な色の水溶液が入ったコップがあります。たこ焼きの焼き目を塗って、茶色い絵の具のついた絵筆を洗ったときに、水入れの水の色を見て、その子の中でコーヒーが出来上がっていました。その発想から派生して、色々な絵の具をといて、りんごジュースとか、他の飲み物も作っていったのではないかと考えられます。注目すべき点は、たこ焼きの横に、桃が添えられていること。現実にはあまりない組み合わせですので、『桃を作ろう』と計画していたとは考えにくい。おそらく、ピンク色の飲み物を作ったあと、丸めたティッシュで絵筆を拭いたときに桃みたいだなと思って、桃を作ったのではないかと考えられます」
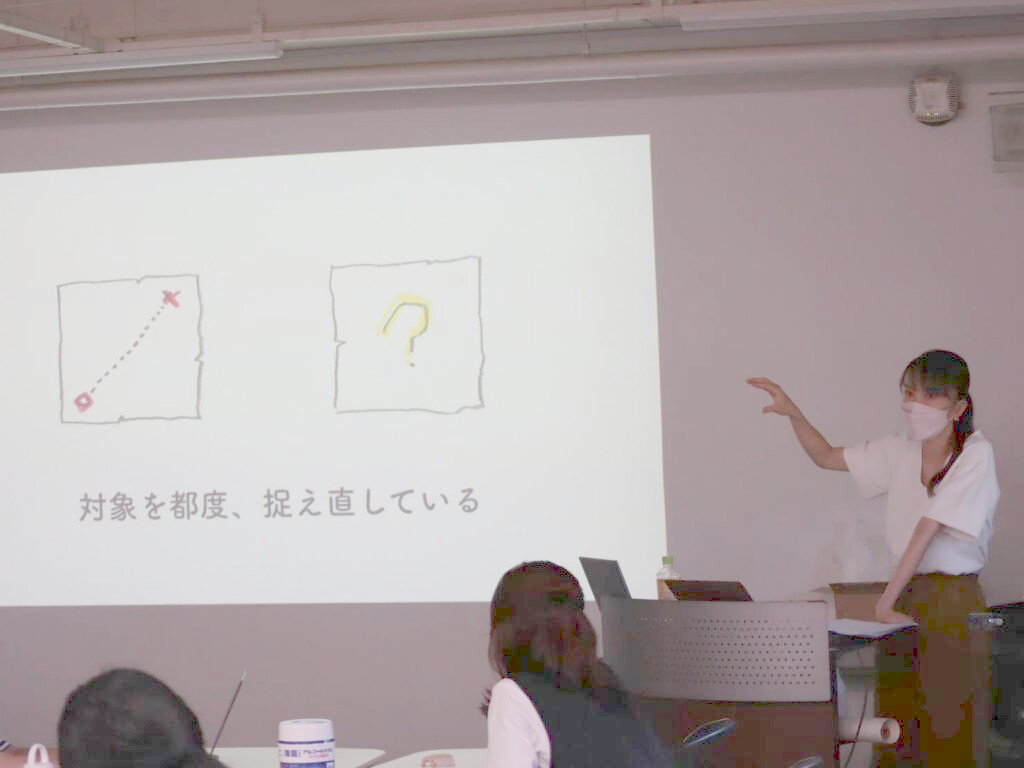
「大人だったら、たこ焼きを作るって決めたら、たこ焼きしか出来上がらないのではないでしょうか。スタートからゴールまでの最短距離を探しますよね。でもこの子は、作りながら新鮮な目で対象に出会い直している。また、同じ工作の他の箇所では、おそばが作られています。しかし始めは毛糸から着想した様子で『パスタを作ります』と言っていた。でも、工作途中に匂いを嗅いだらおそばの匂いがしたそうで、そこからパスタがおそばにガラッと変わります。五感を駆使して対象をみつめ直すような見方も、大人はなかなかしないのではないかと思います」
これこそが「自分なりのものの見方」。
「子供はみんなアーティスト」というピカソの言葉を紹介しながら、子供はすでに自分なりのものの見方ができている一方、大人は視覚による認知と言葉による理解に頼りすぎていると末永先生は指摘しました。
それを体感できる、ミニ・ワークショップもご紹介します。

