給食指導の考え方を教えてください
好き嫌いを理由に量を調整してもいい? 給食指導の目的とはそもそも何でしょうか? みん教相談室に届いたお悩みに対する専門家からのアドバイスを読んで、給食指導と食育について考えてみませんか。
回答/福岡教育大学教職大学院教授・脇田哲郎
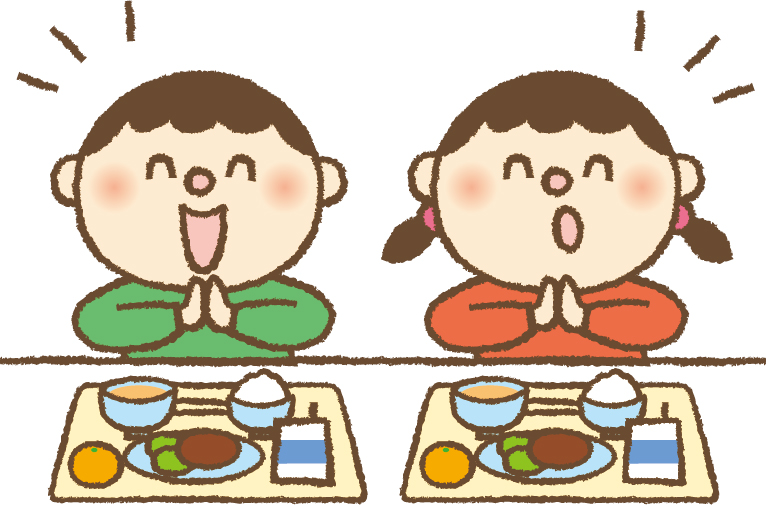
目次
Q1 給食の量を調整してもよいですか?
四年生の担任をしています。 給食の考え方について質問です。
給食の量を子供たち一人ひとりと調整(増やす、減らす)をしてもよいですか? 特に、牛乳やチーズ、パン、納豆、魚の切り身などの個々に分かれている物を調整してもよいですか?
私の学校のスタンダードでは、個物は調整不可で、食べ切れないときは残すというルールがあります。(夏至先生・20代男性)
A1 食育を行った上で調整することはあっていいと思います
給食の食べる量を自分で調整することはあってもいいと思います。
ただし、今の自分が食べられる量を意思決定する。食べられるならば、少しずつ、食べる量を増やしていくという方向での意思決定です。
嫌いだから残すというのでは、不十分です。
個々に分かれているものの扱いについては、学校が、そのように取り決めておられるのなら、それを基本に考えられたらいいのではないでしょうか。
食育の6つの視点(食事の重要性、心身の健康、食品を選択する能力、感謝の心、社会性、食文化)などの学習を通しながら、食材に含まれる栄養素に関する理解、生産者や給食を作ってくださる方々への感謝の気持ち、アレルギーなどで食べたくても食べられない友達がいることなどを理解する心を涵養し、子供たちが今の自分が食べられる量を意思決定することができるようにすることが必要だと考えます。

