クラスで行うオリンピック「クラリンピック」をやってみよう!
クラスで行うオリンピック「クラリンピック」を開催してみませんか?
執筆/福岡県公立小学校教諭・柳井文陽

目次
クラリンピック開催!
クラスで行うオリンピック「クラリンピック」を開催してみましょう。

学級会で話し合う
計画委員会を組織して学級会で話し合います。「何をするか(種目)」だけでなく、「どのような工夫をするか(旗づくり、ルールなど)」についても話し合うことで、互いに協力したり、相手を尊重したりする力を高めます。
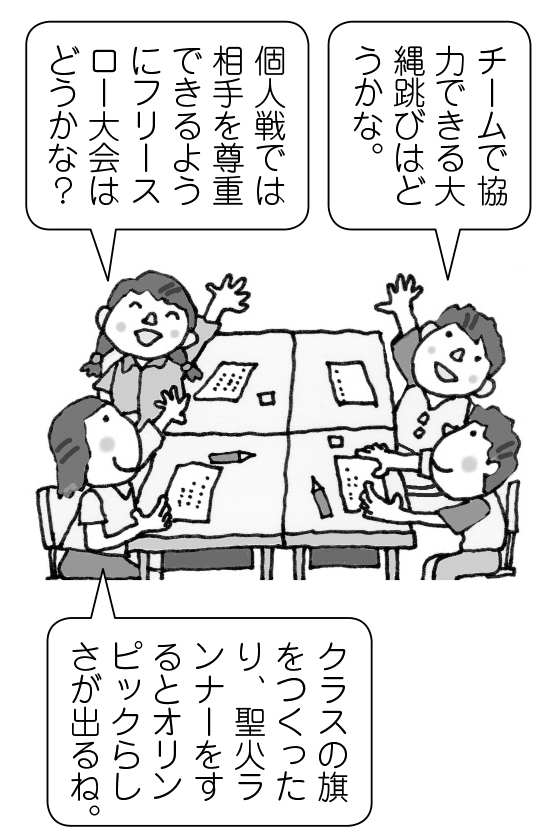
オリンピック精神に基づき「連帯感」「友情」「フェアプレー精神」を持ち、よりよいクラスになるように仕組み、オリンピックでやっているものをまねしてみると、オリンピック感がでます。話し合う前にはオリンピックがどのようなものなのか、パソコン室などで競技や歴史等を調べることで、そのイメージを膨らませることができます。
役割分担
学級会で決まったら、役割分担をして準備していきましょう。子供の準備状況をしっかり見て、褒めたりアドバイスをしたりすることで意欲が高まり、楽しみも増えます。
メダルや賞状づくり
メダルを用意すると、子供たちの意欲も高まります。
また、「頑張ったで賞」などの賞状があると、運動が苦手な子も楽しくできるでしょう。子供が手づくりすることで、さらに所属感や連帯感が高まります。

クラスの旗づくり
オリンピックでは、様々な国の国旗がありますので、それを参考にクラスの旗をつくってみましょう。つくることで連帯感や所属感が高まります。
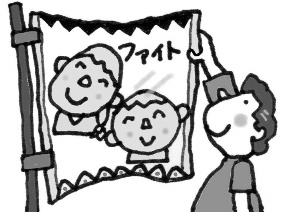
聖火ランナーや旗の掲揚
運動場で聖火ランナーを決めて走りましょう。オリンピック感が出ます。

実践に当たって
「クラリンピック」は、クラスで行う「オリンピック」です。
根本精神は「連帯感」「友情」「フェアプレー精神」等です。
まずは教師が、いい動きをした子供を「ナイスプレー」と褒めたり、1位になれなかった子には「頑張ったね」と声をかけたりするなど、子供たちの努力や健闘を称えます。
そうすれば、子供たちにも自然にオリンピックに見られるような言葉かけや行為が見られるようになるでしょう。
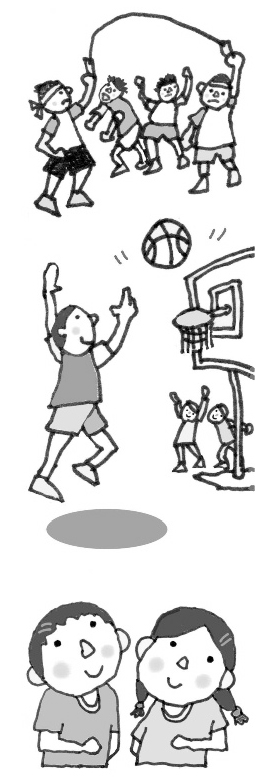
振り返り
クラリンピックが終わったら、振り返りをしましょう。振り返りをすることで、今回の課題を次の活動につなげることができます。また、教師は、課題だけでなく、よかったところをしっかり褒め、子供たちの成就感を高めます。


