「てびき」をキイワードに再発見する 伝説の教師 大村はまの国語授業づくり #5「沈黙のてびき」――大村はま国語教室の日常


日本教育史上突出した実践を展開し、没後20年を経た今も伝説として語り継がれる国語教師、大村はま。現役時代の教え子であり、その逝去の二日前まで身近に寄り添った苅谷夏子さんが、今、改めて大村はまの国語授業づくりの「凄み」を語る連載です。
執筆/苅谷夏子(大村はま記念国語教育の会理事長・事務局長)
目次
大村はま国語教室の日常的なかかわり
この連載の第4回までを丁寧に読んでくださった担当編集長の白石さんから、先日、こんなメッセージをいただいた。
「(『花火の表現くらべ』のような)『繊細かつ精確な言語感覚』を育てる学習は現場で軽視されて久しいですね。こうした授業が成立するための、大村先生の『日常的なかかわり、仕事』についても、もっと知りたくなりました」。
確かに、「花火の表現くらべ」のような取組は、突然、材料と手順を提示しただけで成立するものではないだろう。あの単元は中学1年生が9月に取り組んだ。入学以来わずか4か月ほどしか大村の授業を受けていない。そういう彼らが、長い夏休み明けの最初の単元であれだけの関心と熱意、精度でことばを見つめ、話し合った。子どもたちがあんなふうにしてことばに向き合う、その下地のようなもの、構えのようなもの、基本的な力、そうしたものはどのように育まれたのだろうか。それをお伝えすることは、とても大切なことであるに違いない。白石編集長の問う「日常的なかかわり、仕事」に重要な鍵があることは確かだろう。
ささやかな伝授の積み重ね
大きなプロジェクト(たとえば「花火の表現くらべ」もその一つ)は、時に何か月もかけて取り組み、堂々たるまとめが制作されたり、発表会が行われたりしている。しかしその一方で、大村国語教室の日常には、小さな小さな、実にささやかな「ことばを育てる営み」が、大きなプロジェクトの合間を縫って時には5分、10分単位で積み重ねられた。授業が終わったあとの休み時間の窓辺やストーブのまわり、廊下でも、「勉強」とは思えない柔らかな雰囲気の中でそれは止むことがなかった。
『大村はま国語教室』(小学館)(全集「大村はま国語教室」(筑摩書房)の第9巻に転載)の中で大村は、倉澤栄吉、野地潤家という当時を代表する国語教育研究者と対談をしている。そこでこんな教室の風景が語られている。
いっしょに暮しておりますので、いろいろなことがありますね、クラスの中でも。それで、「いま、私のしたこと、これはどういうことばで言えるか」といったようなこともよくいたします。たとえば、「怒られた」というようなことを生徒はよく申しますね。しかし、怒ったのではなく、「叱った」も強すぎて、「たしなめた」とか、「注意した」とか、そういうふうなことです。今、この人のこの背中を丸くしている姿勢のことを、私がこう言うのは「たしなめた」というのであって、怒ったのでも、叱ったのでも、注意したのでもない。(略)「先生にたしなめられた」というふうに言うのだというように教えます。
「叱る」に限らず、いい場面があれば、どんどん、いろいろなことばを教えます。……その場その場で、一人にでも、ひと言でも、ことばを教えるようにしておりました。私自身もそういうときに適切なことばを使うのを、勉強するわけです。
「たしなめる」などはたいへんおもしろかったと思います。しばらくの間、クラスの流行語になっておりまして、「叱られたのか、たしなめられたのか、なんだろう、いまのは」なんて言ったりして……。そういうことばが出てくるというのは、やっぱりことばに関心を持っているからでしょうし、ことばを覚えることが楽しいからではないかと思います。
こんなにささやかな「ことばを教える」という営みが、生徒をよろこばせ、関心を育てたのは、教える人ならではの力量があってこそだ。「叱ったのか、怒ったのか、たしなめたのか」などという話を、押し付けがましく、説教がましく、下手に話したらそもそもつまらないだろうし、生徒は辟易し、聞く耳を持たないに違いない。話の内容の豊かさと同時に、話し手、伝え手としての力量が問われるわけだが、その力量の下地となっていたのは、大村の次のような信念なのではないか。
ことばは、人間というものを開いて見せる窓
ことばは、生活のなかでほんとうにはまったのを見つけたとき、言うに言われないような快感があるのではないでしょうか。(略)ことばというのは、一つ身についたときに、ぱあっとどこか生活の一場面というか、人生の一場面というか、人間の一部分というのか、そういうところが開いていくような気がいたします。
そして、ことばはたった一つですけれども、ほんとうにわかったというときには、私はたしかに心がそれだけ太ってくるし、またおおげさな言い方をすれば、人生の一部がほんとうにわかっていくのではないだろうかと思います。(略)ことばは、ほんとうにそういう力のある、人間というものを開いて見せる窓というような気持ちがいたします。(同書)
「ことばは、人間というものを開いて見せる窓」、そういう確信とともに、大村は子どもたちにことばを手渡し、窓を開いてみせた。人間とか人生とか生活とか、そうしたものに直結したものとしての「ことば」は、どんな小さな断片も、興味深くないはずがない。そのおもしろみを、大村はいつだって絶対に手放さなかった。「ことば」は、自分の外側にある、自分とは関係の薄い、細切れでバラバラな乾いた客観的データなのではなくて、かならず人間に、つまりは自分につながっている、自分と世界をむすぶ紐帯だ――そういう感覚である。だから、大村が「叱ったのか、たしなめたのか」というような話をするとき、それは人間らしい温度とふくらみを持ち、ゆたかな会話となった。聞いていても、おもしろかった。
大村が手渡そうとするこういうことばの世界は、むずかしいことばを辞書で調べ語義を覚え、頻出漢字を記憶し、効率的な読解のテクニックを身に付ける、いわゆる「国語学習」とは別次元のものだった。その多彩さと豊かさ、魅力に惹かれて、生徒たちは「ことば」というもの自体に興味をもち、注視することを覚えた。この興味と注視という二つを基盤として、生徒たちは自分事としてことばに対しながら本格的単元学習に取り組み、結果として力を付けていった。白石編集長の問う大村はまの「日常的なかかわり、仕事」は、そうした名もない小さな伝授の集積と言えるのではないだろうか。

ことばへの注視を体得させる試み
大村はまの実践には1時間の授業で完結する小さなものもある。ここでその一つを紹介したい。
「大きい」「大きな」ということばの意味の広がりを実感させようという試みだ。まず次のAをプリントして配付する。(全集「大村はま国語教室」第9巻に記録されている。以下の引用はすべて同書から)
《この「大きい」の意味は》
A「大きい」(形容詞) 「大きな」連体詞
1,机はもっと大きいほうがいいね。
2, もっと大きな望みをもってほしい。
3,いま、順にあげるから、大きい人は待っていなさい。
4,もっと大きな心を持ってほしい。
5, 中学生になってから急に大きくなって、姉さんを追い越した。
6,調査の結果、その被害額はかなり大きな数字になっている。
7,大きなことを言っていたのに、こんな結果になって恥ずかしい。
8,大きくなったら何になりたいかと弟に聞いてみた。
9,今年の大きな事件といったら何か。
10,大きな声を出すな。
11,大きな研究をなしとげた。
そして、「一つ一つ、これを芯にした短い話を作り、話して聞かせ、生活断片の中でそれぞれの意味を感じ取らせる。どう違うかと問わない。説明させない。心の中でかみしめ、納得するのを見届ける。」
「大きい」という、幼児でもわかることばを扱うこの取組では、この今さら考える必要もないような簡単なことばを、国語教室ならではの新しい目で改めて注視し、わかっているはずの自分の頭の中を覗きこむようにして意味を細かく捉える、そこを狙っている。よくよくわかって、現に使えていることばだからこそ、この「改めて注視する」という神経の使い方を体得させることができる。もし十分に使いこなせていない難解な語を取り上げても、この目的には合わないはずだ。自分の心の中、脳の中を覗きこんで、丁寧に精緻にことばを捉えるという基本中の基本の態度を、大村はこんなふうにして日常の中で育てていた。
「大きい」をめぐる上記の11個の短文は、どれをとっても平易な、日本語として何の不足もない文章だ。このままこれだけを材料に考えさせることも十分に可能だ。しかしあまりに短いために味気なく、ことばの現場の光景として立ち上げる力も、子どもを惹きつける力も弱いことが想像される。それでは不十分だと大村は考えていた。言語感覚をしっかり目覚めさせた状態でことばに対することはどうしても必要で、ぼんやりと、焦点の定まらない、受け身の姿勢でいては、ことばなどほんとうにはその人のものにならない。子どもたちの言語感覚を呼び起こすためには、いきいきとした素材が必須で、だから大村はこれらの短文を芯とした短い興味深い話を用意して話して聞かせるという段階を作った。ことばが暮らしの中の鮮やかな一場面と結びついて、生きた、鮮度のいい素材として子どもの前に提示されること、それを実現するような「短い話」をさっと作り、優れた話しことばで届ける、その手腕は当たり前のものではない。大村の言語力が支えになっているが、私たちもやってできないことではないと思いたい。
「短い話」の実例
では、大村はどんな「短い話」をしたのか。「大きい」の実例は記録に残されていないが、たとえば「妙」という文字を柱に、巧妙、当意即妙、言い得て妙、神妙、妙技、軽妙といった語群を知る機会をつくった「伏せ字『妙』」という取組の例を見てみたい。
「浜口君」
浜口君とは、中学校時代三年間同じクラスであった。学習でも、学級の仕事でも、よく同じグループになったものだ。(略)文集を作ったときもいっしょだった。
そういうとき、浜口君は、いつも、だれよりもといってよいくらい熱心だった。熱心なだけではない、いや、それが熱心の結果かもしれないが、いろんなことをよく思いつくんだ。ぼくなんか、いくら考えても、これということも思いつかない、たまに思いついても、どのグループでも思いついていそうな平凡なことばかり。なのに、浜口君なんか、あとからあとからいい思いつきを出すんだ。それがまたどれも「そりゃあいい!」って、思わず賛成の声が上がるような思いつきなんだ。おかげで助かったことがずいぶんあったと思う。
「浜口君」というタイトルまでついたこの文は、「妙案」ということばに出会うために用意されたものだ。おそらく浜口君は大村教室に実際にいた生徒で、この話は子どもたちにとってたいへんリアルで、共感も納得もしやすいものだっただろう。この身近なエピソードとともに、「妙案」という日常語を少し超えたレベルの語彙が手渡される。
「妙」をめぐるこの取組の一つ目では、安野光雅さんのテレビでの対談を話題にしている。大村は、「一つの言葉を知るときに、一つの感性とペアで覚えていて、はじめて本ものになる」という安野のことばを紹介した後に、「『一つのことばを知ることは、一つの人生を知ることだ』と言って、ことばの教育にくふうしてきた私は、ここに安野さんの一つのことばを得て思わず、おうと声を出しかけたほど感動した」と結んでいる。これは「いい得て妙」という表現に出会わせるための文だ。一連の取組の冒頭でこの「一つの言葉を知るときに、一つの感性とペアで覚えていて、はじめて本ものになる」という考え方が提示されたのは、もちろん偶然ではない。こんなふうにしてことばは、実感を伴い、感性とペアになって世界に結びつき、本ものとして子どもの頭に根を下ろすことになる。それを大村は生徒に実際に味わわせようとしている。
「大きい」の意味をめぐって語られる11の短い話も、このような姿勢で用意されたに違いない。それらが大村の声でいきいきと語られたとき、生徒たちは、関心と興味とともに心を連動させながら、言語感覚をしっかり目覚めさせた状態で聞いたことだろう。聞きながら、それぞれの「大きい」の意味を感じ取っていくことになる。
問わない、説明させない、納得するのを見届ける
さらに、重要なのは、大村がとった次の方針だ。「どう違うかと問わない。説明させない。心の中でかみしめ、納得するのを見届ける。」
どう違うかと問わない、説明させない――これは、多くの先生方にとっては大きな驚きではないだろうか。まず普通は、聞きそうなものだ。「この例の『大きい』はどんな意味で使われていた? だれか説明できますか?」しかし、こう聞いたとたんに、これは「出題」になり、生徒は「正解」を出そうという姿勢になる。よく整理された、辞書的な、要領のいい説明を求められていると感じ、試されていると思い込む。それではここで大村が求めていたものとは違ってしまうのだ。大村はこんなふうに書いている。
「国語の時間に『これはどういう意味ですか』と子どもにことばの意味をお聞きになり、子どもが辞書的に答えるという授業があります。あれは子どもにとって困難だろうと思います。よく知っていることばでも、聞かれるとわからなくなってしまうことがございますし、だいたい世の中で、そういうことはいらないのではないかと思います。(略 教師は職業上、言えなくてはいけないが)子ども、また、一般の人は、ことばの意味をちゃんと説明するということはできなくてもいいのではないか。そのことばがそのままわかっていて、そこにあればわかる、人が言えばわかる、読めばわかる、自分も使えるというのでしたら、別のやさしいことばで説明するという特殊技術はいらないと思いまして、ほんとうにさせなかったのです。」
特にこの取組では取り上げるのが「大きい」というような基本的語彙だからこそ、それを更に分析して別の語で言うことは、「わかる」を超えた別の力と割り切っている。「子どもを深く知る」ことを教師の仕事の根源としていた大村は、「わかっていることでも、聞かれると言えない、わからなくなる」という子どもの事情(実はおとなも同じようなものだ)をよく理解していたし、「意味が言えないなら、説明ができないなら、わかっていないのだろう」という決めつけをしなかった。それをせずに、子どもたちが「心の中でかみしめ、納得するのを見届ける」というのは、本当に教える専門家ならではの見識と覚悟だ。わかったかどうかを客観的な形にするための問いというのを、必要とも必然とも考えていないし、そうすることのマイナスを見切っている。「評価」は重要なこととされているけれども、点数化とは別の次元の、もっと子どもに寄り添った評価こそが、教室をほんとうに明るくするのだと大村は考えていた。「納得するのを見届ける」ことは、「それを見届けるのは自分だ」と決めればできることだった。いまは説明責任が求められる時代ではあるが、この「見届ける」という教師の働きは、数値化とは別次元のところにある、人間ならではの把握力、洞察力ではないだろうか。
この連載では、てびきに注目して大村の実践を紹介することを目指しているが、今回のこの「問わない、説明を求めない」という姿もまた、「沈黙のてびき」と言っていいように思う。問わないことで、説明を求めないことで、実現することばの教育のあり方――おもしろいてびきの一例ではないだろうか。
こうして、子どもたちは、外面的にはただ大村の話す11の小さな話を聞くだけでいいことになる。「大きい」の意味の広がりについて驚きながら目を向け、これまでこんなふうに着目して考えたことはなかったけれども、聞けば、微妙な違いが自分の頭の中に現にちゃんと浮かび上がってくることを実感し、納得する。それをおもしろいことと受け止める。こうしてまたことばへの感度があがるのだ。
さらに比べるという視点をつくる
この取組では、次に、もう一つのBというグループが用意されている。これはプリントせずに、大村が手元で持っているだけのものだ。この中から順不同に取り出し、また短い話をしていく。生徒たちは、B群から語られた話の中の「大きい」がA群の何番の「大きい」と同じ意味で使われたものかと、手元のプリントを見ながら考えていくのだ。最初にA群の話を聞いていたときとはまた別種の、「比べる」という視点、頭の働かせ方をすることになり、その感触の違いも興味深いはずだ。
B「大きい」「大きな」
1,大きなかばんを二つも持って、やってきた。
2,少年なのに、もっと大きな夢が持てないのかな。
3,大きいのに、お行儀のわるい!
4,あれもだめ、これもできない、と失敗ばかり数えあげないで、もっと大きな目で見てやってほしい。
5,大きい人を先頭に、背の順に並んで。
6,義務教育といっても何の費用もかからないわけではない。たとえば参考書代などもかなり大きい。
7,大きな口をきくんじゃない。
8,こんなきずは、大きくなれば治るよ。
9,大きなまちがいもせずに、なんとか勤め終わってほっとしています。
10,ドカンドカンという大きな音で、授業も妨げられました。
11,二十世紀の科学上の大きな発見は何か。
自分で自分のことばの力を育てていくに違いない……
このようなことばを育てる小さな実践例は全集に多く記録されているが、大村はそれらを概観してこう言っている。
「どういうことばを覚えたかということではなくて、どれだけ、ことばの感覚を鋭くしたか、というところに値打ちを見たいと思います。
どんなに教えても、ことばは教えきれるものではありませんが、ことばへの限りない興味と、鋭い感覚とがあったら、自分で自分のことばの力を育てていくに違いないと思っております。」
程度の高い単元学習に張り合いをもって、いきいきと臨む子どもたちを生んだ「大村教室の日常的なかかわり、仕事」の一端は、こうしたものだったと考える。一端と言うからには、他にも別の側面はありそうだ。それはまた別の機会に紹介できればと思っている。

<大村はま略歴>
おおむら・はま。1906(明治39)年横浜市生まれ。東京女子大学卒業後、長野県諏訪市の諏訪高等女学校に赴任。その後、東京府立第八高等女学校へと転任。すぐれた生徒たちを育てるが、戦中、慰問袋や千人針を指導、学校が工場になる事態まで経験する。
敗戦後、新制中学校への転任を決め、後に国語単元学習と呼ばれるようになった実践を展開。古新聞の記事を切り抜いて、その一枚一枚に生徒への課題や誘いのことばを書き込み、100枚ほども用意し、駆け回る生徒を羽交い締めにして捕まえては、一枚ずつ渡していったと言う。1979(昭和54)年に教職を去るまで、単元計画をたて、ふさわしい教材を用意し、こどもの目をはっと開かせる「てびき」を用意して、ひたすらに教えつづけた。退職後も、90歳を超えるまで、新しい単元を創りつづけ、教える人は、常に学ぶ人でなければならない、ということを自ら貫いた。著書多数。
2005年、98歳10ヶ月で他界。その前日まで推敲を進めていた詩に、「優劣のかなたに」がある。
<筆者略歴>
かりや・なつこ。1956年東京生まれ。大田区立石川台中学校で、単元学習で知られる国語教師・大村はまに学ぶ。大村の晩年には傍らでその仕事を手伝い、その没後も、大村はま記念国語教育の会理事長・事務局長として、大村はまの仕事に学び、継承しようとする活動に携わっている。東京大学国文科卒。生きものと人の暮らしを描くノンフィクション作家でもある。
主な著書に『評伝大村はま』(小学館)『大村はま 優劣のかなたに』『ことばの教育を問い直す』(鳥飼玖美子、苅谷剛彦との共著)『フクロウが来た』(筑摩書房)『タカシ 大丈夫な猫』(岩波書房)等。
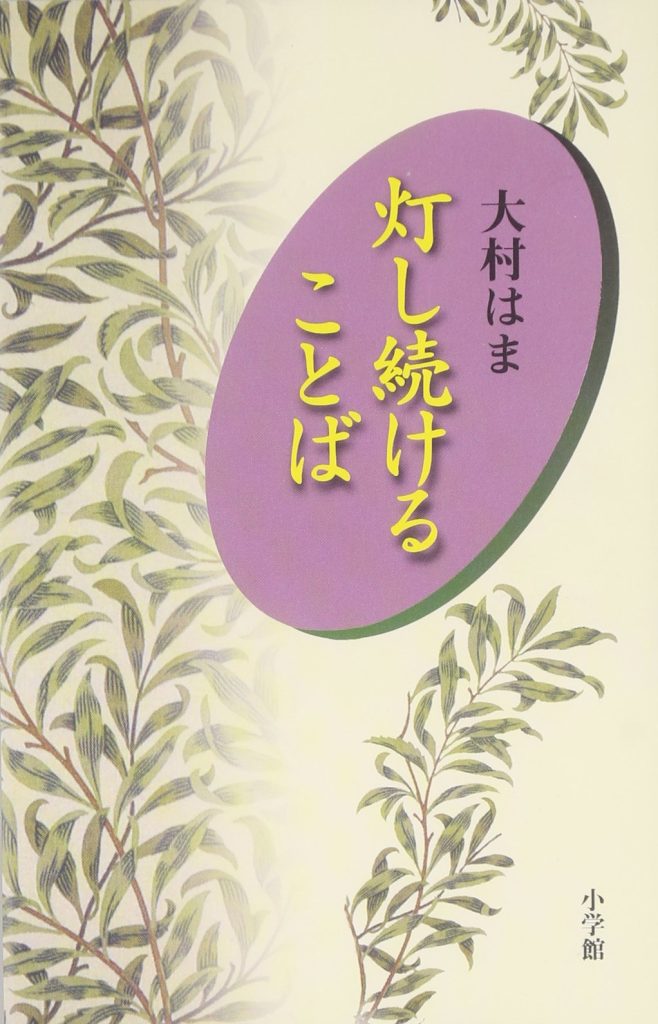
ロングセラー決定版!
灯し続けることば
著/大村はま
「国語教育の神様」とまで言われた国語教師・大村はまの著作・執筆から選びだした珠玉のことば52本と、その周辺。自らを律しつつ、人を育てることに人生を賭けてきた大村はまの神髄がここに凝縮されています。子どもにかかわるすべての大人、仕事に携わるすべての職業人に、折に触れてページを開いて読んでほしい一冊です。(新書版/164頁)
大村はま先生の貴重な講演動画!「忘れ得ぬことば」大村はま先生 白寿記念講演会 5つのことばがつむぎ出す、国語教育の源泉【FAJE教育ビデオライブラリー】〈動画約60分〉がこちらでご覧いただけます。

