家庭でのデジタル活用に問題あり?【矢ノ浦記者が語る「教育取材余話」⑤】
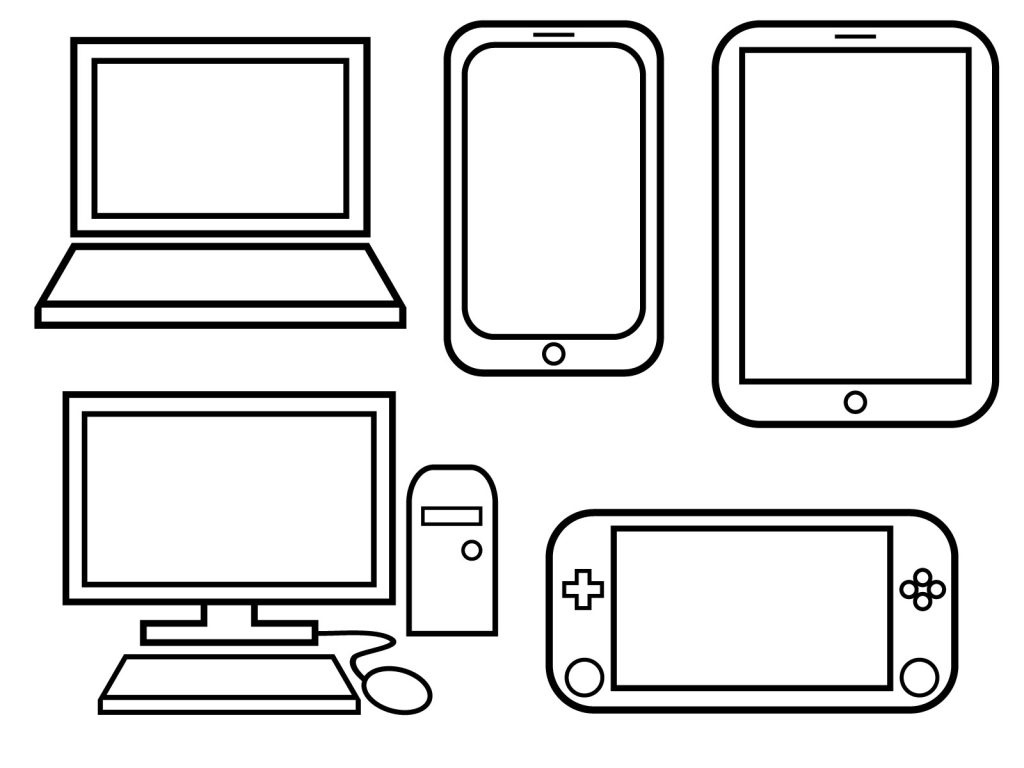
教科の学習も、教科の中で閉じているだけでなく、それを通して生活の中の多様な場面で生きて働く力となることが求められています。しかし、学んだことは学んだことで、答えが出たら終わり。それと現実世界の問題を擦り合わせながら生かそうとはしない子供が増えているのではないかという声を、取材の中で耳にすることが増えてきたと感じています。今回は、そんなお話をしたいと思います。
執筆/教育ジャーナリスト・矢ノ浦勝之
目次
「答えを精査しない子供が増えているように感じる」
先日、ある先生に授業取材をお願いしたときに、「短絡的に答え(正解)を求めてしまい、答えを精査しない子供が増えているように感じる」というお話を耳にしました。例えば算数の学習で、現実世界の問題を算数の世界に置き換え、数学的に問題解決を図った後で、それを再び現実の問題に当てはめて、それが本当に正しいのか再度、精査して答えを書くということをしないというわけです。
小学校の算数の学習内容であれば、算数の世界と現実の世界のズレがそれほど見えては来ないかもしれません。しかし、中学校や高校の数学になると、現実問題を抽象化して数学の世界に置き換えて解決を図った後、その結果と現実とのギャップの調整が必要になってきます。
そのように抽象化して数値上の計算をした後、改めて現実問題に当てはめながら調整を行って考えることは、社会に出ればなおさら重要になるわけです。しかし、「計算して答えが出たら終わり」とか、ひどい場合であれば、「抽象化して計算しても(直接的に)問題を解決したことにならないから、数学は好きじゃない」という子供までいるという声を、実際に聞いたこともあります。
その原因は分からないとしつつ、雑談の中で次第に、もしかしたらICT活用が日常的になり、AIなどが簡単に答えを出してくれることによる問題があるのではないかという話になりました。ちなみにその先生は、意図的に間違ったものを出してきたAIの答えを示して、それを吟味するような授業が必要ではないかとも話しておられました。
あるいは別の教科の先生から、SNSの頻繁な使用によって誰かから情報が流されてきたら、すぐに返信することが求められているせいか、「文章も定型化して短くなっており、その裏側に言葉の吟味や内容の熟慮が見えない気がする」というお話を伺ったこともあります。右から左へ形に沿って情報を流しているだけで、そこに思考が伴っていないのではないかということなのです。
それは何も、子供ばかりではないとおっしゃる先生の声を聞いたこともあります。もしかしたら先生方も(加えてその先生自身やこれを書いている私自身も)そうなっていないかというお話をしておられました。
もし、ここまでの先生方の実体験が実際にその通りなのだとすると、子供たちは学校生活の中で(加えて我々は日常生活の中で)、何も学んでいないことになるのではないでしょうか。
以前、脳科学の先生が哺乳類の学習は排除法の誤差学習だと言われたことを紹介しました。その内容はつまり、間違いを排除しながら誤差を修正していくのが、ヒトも含めた哺乳類の学習だということです。そう考えると、1度出てきた情報(あるいは算数・数学の答え)が間違いかどうか確認もせず、現実に即した修正もしないというのであれば、そこには学習がないことになってしまいます。

