教員の育成は指導型から伴走型へ

児童の育成に個別最適化の視点が導入されて久しいですが、教員たちの育成をするときにも、管理職は同じ視点に立っているでしょうか? 上から圧をかけるような指導になったりしてはないでしょうか?
これからの時代に求められるのは、教員の育成も個別最適化する、という新しいリーダーシップ=サーバント・リーダーシップです。信頼を土台に、教員一人ひとりの個性と課題に応じた個に寄り添う支援を実践してみましょう。若手教員が情熱を取り戻し、ひいては学校全体の教育の質を高めるための強力な鍵となります。
指導者が一方的に話すのではなく、教員自身に気づかせることが、自律的な成長を促し、教育の質を向上させます。
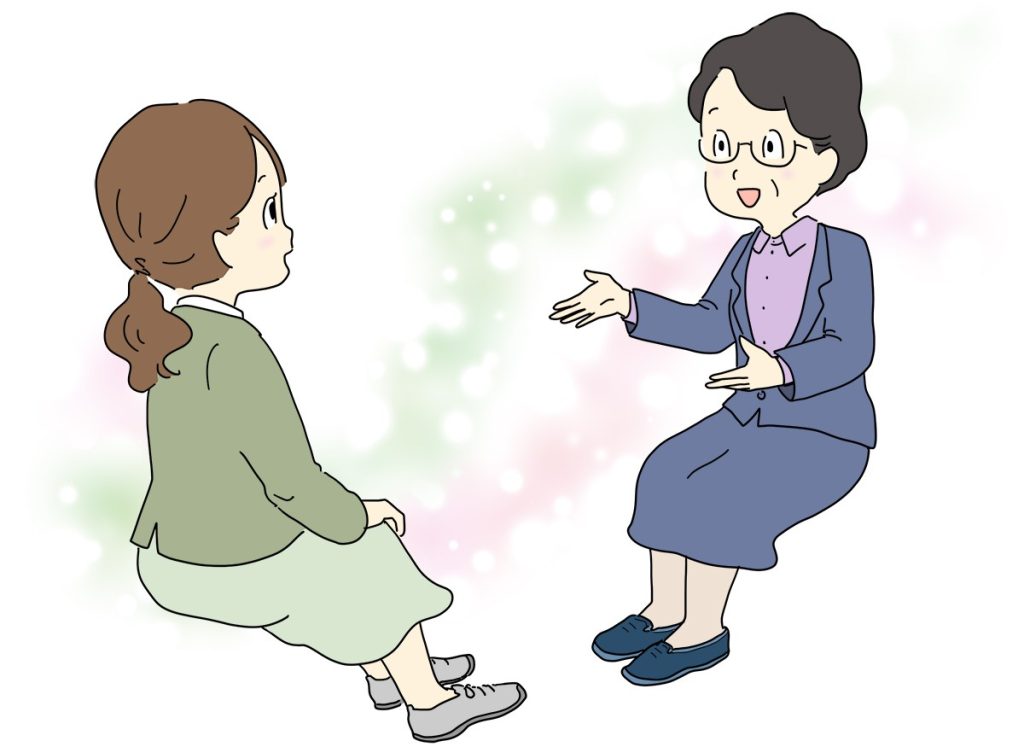
執筆/元山形県公立学校教頭・山田隆弘(ようだたかひろ)
目次
若手教員の伴走者になろう
本記事は、上司・先輩が後輩の教員の指導力向上のために、授業の様子を見てアドバイスをするという状況を想定しています。まずは、あなたが若手だったときのことを思い出してみてください。上司や先輩から、上から目線でとやかく言われるのは、決して良い気分ではなかったと思います。プラス志向でアドバイスや批評をくれているのに、なぜそう感じたのでしょうか? 理由を分析していきましょう。
評価ではなく事実を伝える
授業改善を検討するとき、単なる感想はやめましょう。あなたの主観的な良い・悪いは言わないようにします。客観的な事実だけを冷静に記録し、共有することに徹します。指導者の主観が入ると、教員は無意識のうちに心の壁を作り、防衛的になって、成長のための内省が阻害されます。
客観的なデータのみを使い、感想から技術論へ
- 教員が話した時間(授業者発話量)と、児童生徒が発言した回数(児童発話量)の割合
- 作業時間なのに手が止まった児童の人数や時間帯
- 特定の児童への声かけ回数の偏り
など、データや事実だけを冷静に記録しましょう。「10分のうち、板書に費やした時間が3分あり、その間、後方の児童の手が止まっていた」という客観的な事実を提示するのと、「児童が戸惑って困っていたみたい」と言われるのとでは、どちらのほうが改善の議論につながるでしょうか?
相手の話を傾聴し、指示ではなく質問を返して、考える力を養おう
問題点が見えたら、質問で内省を促し、教員が自分で考える力を養わせていきます。自分自身で気づきと発見を得るようにコーチングするわけです。
このとき、管理職が話す時間は最低限に。教員の話をじっくり聞くことに徹します。質問に答える過程で、教員自身が課題と解決策に気づくことが、真の成長につながります。
ここでよい対話を積み重ねることによって、児童との対話や指導の質の向上につながるわけです。
内省を促す発問の例
【過去と現状の分析を深める質問例】
「なぜこの方法を選びましたか? そのめあては何ですか?」
「あのとき、発言できなかった児童はどんな気持ちだったと思いますか?」
「あなたの授業の目標を達成するために、最も効果的だったと感じた瞬間はどこですか?」
【前向きな行動につながる質問例】
「次回、同じ単元を行うときに、どこか変えたいところはありますか?」
「その変化を加えることで、児童の反応はどのように変わると期待しますか?」
「その解決策を実践するために、わたしがサポートできることはありますか?」
能動か受動か? 相手の個性に合わせたアプローチをしよう
相手がどんな性格的志向を持つかを把握し、それぞれのタイプに合わせた接し方をすることで、関係性が構築しやすくなります。大きく分けると、以下の3タイプに分けられるのではないかと思います。
①能動型には 問いの深化と自主性の尊重を
【特徴】
意欲が高く、率先して行動するタイプ。自主性が高いがゆえに、失敗を一人で抱え込むこともある。
【最適化アプローチ】
育成のポイントは、問いを深めるコーチングに重きを置くことです。具体的な技術指導よりも、彼らの実践に対する「なぜ」を深掘りする質の高い質問に徹し、自律的な探究の姿勢を促します。
【具体的な声かけ例】
その斬新な指導案、とても興味深いです。何を意図してそのステップを入れたのか、もう少し詳しく教えていただけますか?
あなたのその経験と学びを、今度の校内研修で5分間、他の教員に共有してみるというのはいかがでしょうか?
成果を承認し、教材研究や校内研修の一部運営を任せるなどの自主性の尊重(権限委譲)をします。さらに、失敗をフォローできるように定期的に対話をし、安心して仕事に取り組めるよう、組織的なサポートもしましょう。
②受動型には型の提供と小さな成功の可視化を
【特徴】
上司や先輩からの承認や指示を待ってから行動するタイプ。手順や従来からの型を重視し、ルーティンは正確ですが、新しいことや予定外のことに対応するのは苦手です。
【最適化アプローチ】
育成のポイントは、「型」の提供と技術の習得に重きを置くことです。具体的なマニュアルや指導案のテンプレートを与え、スモールステップで課題を提供します。
【具体的な声かけ例】
この発問の流れは、とくに集中力が途切れる午後の時間にとても効果的だったよ。まずはこの型を完全に自分のものにしてみよう
今日は5人もの児童が、君の意図した発言をしてくれたね。数字で見ると、小さな成功が積み重なっているのがわかるよ
授業での発問の数や板書の手順など、小さな成功体験を客観的なデータ(連続フィードバック)で可視化することが効果的です。即時フィードバックで不安を軽減し、完璧主義に陥らないよう、「7割できたらOK!」という安心感を常に伝えていきます。
また、受動型の中には、仕事への意欲をなくしている人も含まれています。
責めることなく、なぜ意欲が低いのか、その背景(業務過多、人間関係など)を丁寧に傾聴し、問題の原因を組織として取り除くようにしていきましょう。小さな成功を体験できる場(チームでの共同開発など)を意図的に設定するのも、やる気を引き出すのに効果的です。
連続フィードバックで成長を加速させよう
なるべく具体的に成長を可視化してあげることで、自己効力感を高めます。
①努力が積み重なっていることを伝える
前回の授業の反省点で『発問後の待つ時間』を意識すると言っていたけれど、今日の授業では前回より5秒も伸びていましたね。素晴らしかったですよ
この教材研究の工夫は、以前お話しした『教え方(方法)と、その方法で児童に何を学んでほしいか(ねらい)の結びつき』という大切なポイントを見事に取り入れたものですね。あなたの頑張りがしっかり成果につながっていることがわかります
といったように、過去の目標や努力と現在の結果とのつながりを指摘します。この行為が、若手教員の日々の努力がムダになっていないということを目に見える形で伝えます。
②成長の可視化と自己効力感の向上
以前の授業は説明中心でしたが、今日は児童の声が多く聞こえ、授業者と児童の発言比率が3:7に改善されました!
前回は特定のグループだけが活発でしたが、今日は教室の右奥の児童まで手が挙がっていましたね
など、前回との違いを具体的に伝えることで、教員自身が変化を自覚し、さらなる成長へと向かうエネルギーが生まれます。

