戦略とは戦わずして勝つこと。そして教師の最大の武器とは「戦略的コミュニケーション」。

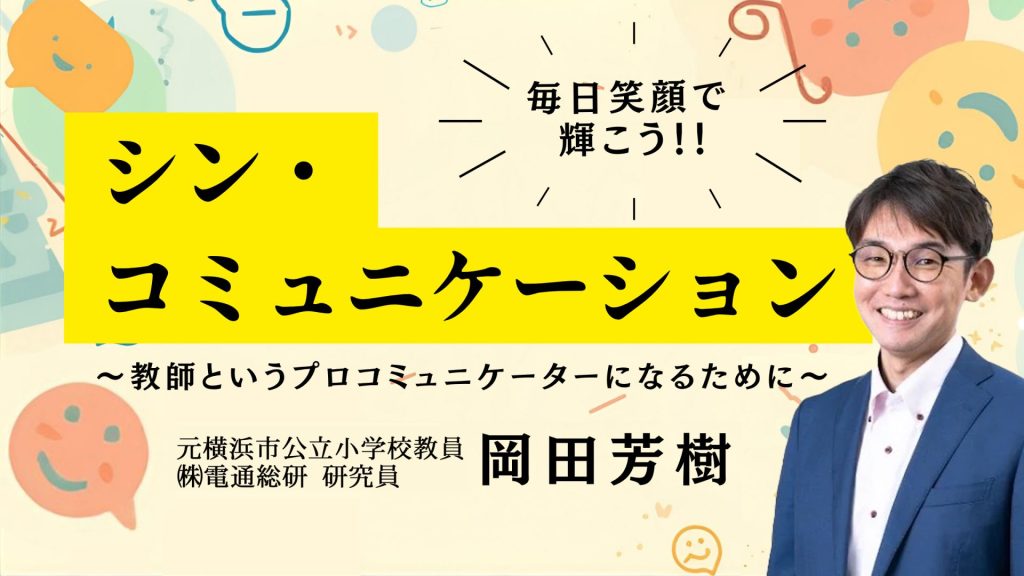
「戦略」。この言葉は、ある目的達成のために力や資源をうまく配分する…といった意味で、よく使われますね。しかし本来「戦略」とは、戦いを省略すること、つまり「戦わずして勝つ」ことを意味していました。人と人とが誤解なく分かり合えば、余計ないざこざは生まれず、物事は円滑に進みます。これこそがコミュニケーションのもつ最大の力であり、教師の磨くべき一番の能力ではないでしょうか。今回は、そんなお話をしていきたいと思います。
執筆/株式会社電通総研 研究員・慶應義塾大学SDM研究所 研究員・元横浜市公立小学校教諭
岡田芳樹
シン・コミュニケーション#2
目次
コロナショックで奪われた対面コミュニケーション
2019年から始まったコロナショックは、社会のあり方に決定的な変化をもたらしました。人と人が対面でコミュニケーションする機会が大きく減り、その結果として意思疎通の食い違い、雑談ロス、マルハラ(※1)などが生まれ、その弊害は2025年の今でも尾を引いています。ある調査結果では、テレワーク経験者は生産性が高まっている一方、コミュニケーションの重要性をこれまで以上に感じるようになったそうで(※2)、社会のあらゆる組織・集団においてコミュニケーション改善の施策は急務といえそうです。
教育現場も、もれなくコロナによる影響を多大に受けました。
第一に対面コミュニケーションの激減です。今でこそ緩和されましたが、コロナ禍当時は先の見えない休校に、分散登校、給食時の黙食、表情の見えないマスク常時着用や、年中行事の中止・縮小など、あらゆる活動に制限がかかりました。
制限により 、対面でコミュニケーションが取れなくなった教師と子ども達は、相互の意思疎通が難しくなりました。子ども達はそれでも対面で話したい気持ちが強く、マスクを外して話す光景も見られましたが、学校のルールとしてマスクを着けて話すことを教師は指導しなければなりません。
人の発達段階において、友だちや教員と濃密なコミュニケーションをとることは、社会的に成長するため不可欠です。そして集団生活最大の魅力もここにあります。そこに制約をかけざるを得ないというのは、教師にとって精神的に相当な痛みを伴う指導だったことでしょう。また、余計な軋轢を生むことも多かったでしょう。
第二に、非言語コミュニケーションも激減しました。マスクはお互いの感情を読み取りにくくし、結果として得られる情報量が乏しくならざるをえませんでした。体育の授業での物理的な接触も禁止であり、従来のルール通りにボールや校内遊具を使用することは当然できませんでした。
このようにして、子どもたちは学校生活で本来受けるべき経験をする機会を奪われてしまいました。
部活動も自由にできない中高生たちの苦渋の思いは察して余るものがあるほど辛かったはずです。
こうして、対面コミュニケーション、そして非言語コミュニケーションを欠いた数年間は教育現場に様々なデメリットを教師と子どもの双方に与えました。人間関係がうまく構築できなかったことや、体験すべきことを体験できなかったことは、今後も彼らの人生に大きな影を落とすのではないかと危惧します。
この層だけに限定することではなく、昨今社会全体に蔓延しているキャンセルカルチャーも、コロナ禍で人と人の繋がりが薄くなり、他人への共感性が乏しくなったことが原因ではないかと考えられます。
(※1) マルハラスメントの略。SNSで上司から送られる文末の句点に対して、若手が「上司は怒っているのではないか」と恐さを感じてしまうハラスメントを示す。
(※2)人材開発専門誌『Learning Design』(日本能率教会マネジメントセンター)2021年5-6月号の調査結果より。
教育現場では、なぜ戦略的コミュニケーションが重要なのか?
著名な経営学者であるピーター・ドラッカーは、「コミュニケーションで最も大切なことは、相手の言わないことに気づくことである」と名言を残しましたが、これはまさに教育活動の核心を突いた言葉といえます。なぜなら、非言語コミュニケーション、つまり表情や視線、ジェスチャー、服装や姿勢など、言葉以外のメッセージから子どもの様相を察知する力が教師には自ずと求められるからです。まさに「相手の言わないことに気づく」力です。
教師は多いときには30人以上の子どもを管理しなければなりませんが、前述したとおり、子ども一人ひとりと対話し、向き合う時間はそう簡単に確保できません。ましてや、非言語メッセージを汲み取ることは心身共に消耗することであり、容易ではありません。
しかし、そのメッセージを見逃すと教室内の重大なトラブルを見落とすことになります。だからこそ、教師はコミュニケーションに関して戦略的に取り組み、子どもたちの情報が入手しやすくなるような仕組みづくり、関係性づくりをするべきだと言えます。
関係性構築のための説得
それでは、本記事のテーマである「戦略的コミュニケーション」についてご紹介していきましょう。
この言葉は国際政治や安全保障の分野において用いられる重要キーワードであり、学術的定義としては「政治目的達成に向けて、言葉、非行動、シンボル、イメージなど用いて相手の行動を変化させるコミュニケーション」を示します。
戦略的コミュニケーションには「構築」「防衛」「レジリエンス」の三つの機能がありますが、本記事では最も中核的な概念である「構築」に焦点を当てたいと思います。
「構築」とは、相手との関係性を構築し、確固たる連携を結ぶことを意味しています。
教師とは、様々なステークホルダー(※4)との関係性構築が求められる職業です。子どもだけでなく、保護者、地域の方々、そして管理職や同僚とも良好な関係性を築く必要があり、これらのステークホルダーとの意思疎通が上手くいけば、教師の学級経営は非常にスムーズになりますし、逆に上手くいかないと、学級経営にも支障があるどころか、放課後まで本来すべきでない業務に取り組まなければならない事態も生じかねません。ましてやいさかいなどはデメリットしかなく、誰もが避けたいはずです。そう考えると、「構築」機能が備わっている戦略的コミュ二ケーションは是が非でも身につけておきたい能力だと考えられるのではないでしょうか。
(※4)ステークホルダー=企業や組織に利害関係を持つあらゆる関係者のこと。
構築することは、説得すること
関係性を「構築」する上で重要なこと、それは「説得」です。相手の心を動かし、相手が納得するように説得することです。戦略的コミュニケーションとは、つまり相手を説得することなのです。
そして、このコミュニケーションを用いる主体を「戦略的コミュニケーター」と呼びます。戦略的コミュニケーターとは、自ら言葉をあやつり、行動することで、自分の望ましい結果を創出できる人のことです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、有能な戦略的コミュニケーターと評されています。
『孫子』(孫子の兵法)は、人生の指南書とか組織運営の基本概念の教科書などと言われていますが、その中で「戦いを略する」ことは「戦略」であると説かれています。そのために重要なのは相手の需要を把握し、己のできることを明確に把握することだと示しています。不要ないさかいを略すためにも、『孫子』は教育に携わる人であれば、ぜひ一度は読んでいただきたい本の一つです。
戦略的コミュニケーションに取り組むために
では教育現場において、具体的な戦略的コミュニケーションとは、どのようにすることでしょうか? ここでは、過去の研究をもとに3つのポイントに絞って紹介します。
1.教育理念・ビジョンの共有
教育現場の戦略的コミュニケーションの第一歩は、学校・学級の理念を子どもや保護者、地域に伝えることです。
教育改革の世界的権威であるマイケル・フランは「教育改革のリーダーシップ」を提唱し、理念を明確にし、ステークホルダーに浸透させることが教育改革の基盤であると述べました。学級でも、年度当初に教師がこのようなクラスにしていくという明確な方向性を示すこと、そしてそれを1年間一貫することが重要です。
エラスムス大学のコーネリッセン教授(※5)の研究によれば、ブランド・政策・メッセージは矛盾が生じると一気に信頼が崩れることを示唆しており、これは発信した理念にも同様のことがいえるでしょう。言動の一貫性と整合性は非常に重要ですので、発信したメッセージは年度末まで貫きましょう。それが信頼構築の第一歩です。
(※5)ヨープ・コーネリッセン(Prof. Dr. JP (Joep) Cornelissen)/エラスムス大学 ロッテルダムスクール・オブ・マネジメント 教授
2.ステークホルダー(子どもや保護者)との双方向の対話
PRマネジメントの名著『Managing Publication Relations』が示唆する「双方向対称モデル」では、単なる一方的な広報ではステークホルダー、つまり教育現場でいえば子どもや保護者の納得を得ることはできないと主張します。
大事なのは「双方向の対話」です。相手の価値観や背景を汲み取り、いかにwin-winな結論に至れるのかを探ることがポイントとなります。
そのためにも、コミュニケーションの時間をいとわず、積極的に自分から子ども、保護者や周囲の教員へコンタクトを取ることで、自ずと周りから話しかけられることが増え、結果として些細な情報から危機管理に結び付けることも容易にできるようになります。
とくにトラブル対応の場合、後手に回ると深刻なクレームに発展することがあります。何より先手が大事だと私自身、身をもって学びましたので、強調しておきたいと思います。
3.ストーリー性とナラティブを意識する
近年の感情研究から、人は単なる事実を並べて話されるより、ストーリー性や感情を揺れ動かされるものに強い影響を受け、行動変容を促されることが分かってきました。さらに、データなどに基づいて説得を試みる科学的コミュニケーションより、感情に乗っ取った物語からなるナラティブ・コミュニケーションの方が、人々を納得させる力があることが判明しています。
この「ナラティブ」というのは、「物語」のことです。物語というと、「ストーリー」が一般的ですが、ナラティブは、語り手の経験や主観に基づいて変化する物語を示します。いわゆる「I(アイ)メッセージ」と言えば分かりやすいでしょうか。ストーリーには2人称・3人称もありますが、ナラティブとは主観や感情を含めた1人称の物語です。
ナラティブには受け手の感情を揺さぶり、共感を得る働きがあり、非常に強力なコミュニケーション手段となりえます。自国に良いように物語を語り国民を誘導する、プロパガンダの手法として国家が使ったり、商品のマーケティングで各企業も頻繁に使っています。
ナラティブ・コミュニケーションの世界も大変奥深いため、詳しいことは別の回で論じられたらと思います。
子どもとの対話でナラティブを意識してみよう
子どもたちとのコミュニケーションを図るうえでも、ナラティブは強力な武器になりえます。ぜひ、意識してみてください。そのためのポイントをここで2つ挙げさせていただきます。
1つは、自分の発するメッセージにナラティブを込めることです。過去の自分の成功や失敗を感情豊かに交えつつ、子どもたちに対して伝えたいメッセージの本体にも、こうなってくれたら本当に嬉しいとか、悲しいなどといった、自分の感情をしっかり盛り込んでいくのです。
もう1つは、子どもや保護者に対して、相手のナラティブを良い方向に変換してあげる、ということです。人はどうしても自分だけの視野にとらわれた見方や考え方をして、独自のナラティブを築きがちです。子ども同士だけでなく、保護者同士においても大抵はそれがトラブルの発端です。教師はそれを変換し、別の視点(ナラティブ)を提供することができます。
この2つによって、相手との相互理解は有意的に深くなります。
私はナラティブ変換によりトラブル解決につながった事例を多く見てきました。ナラティブ・コミュニケーションは教師にとって非常に頼もしい武器であり、シン・コミュニケーションの重要な核の一つであるため、是非多くの教師に身につけてほしいと思います。
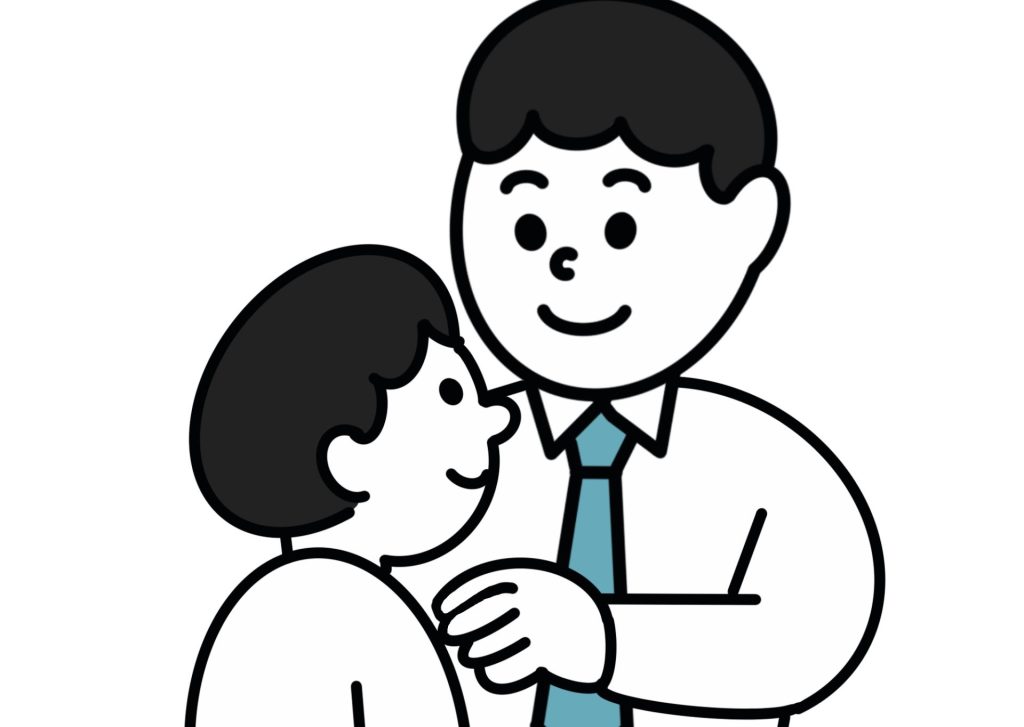
この他にもリスクコミュニケーションや、コミュニケーションに対する評価検証など様々なポイントはありますが、それらは別の回で触れることとし、今回は学校でとくに実践しやすいポイントに絞って紹介しました。
「戦略」と聞くと打算的で抵抗感を覚える方もいるかもしれません。しかし、戦略を何も持たないということは、何も準備せずに授業したり面談したりするのと同じことです。戦略はいさかいを避けるもの。ぜひ、それほど時間をかけなくてもよいので、楽しくコミュニケーションについて考えてみてほしいと思います。
そして、何より子どもと保護者は学校側との対話を待っています。コロナで一度は奪われた対話の時間を今からでも取り戻してみてはいかがでしょうか。
話し手が対話に対する見方を少し変えるだけで、相手の反応は大きく変わります。この私自身の体験から得た学びを共有し、本稿はここで締めくくりたいと思います。
【参考資料】
・HR総研『「社内コミュニケーション」に関するアンケート2024結果報告』(2024)
・パーソル総合研究所『職場での対話に関する定量調査』(2024)
・人材開発専門誌『Learning Design』2021年5-6月号
・田口佳史(2014)『孫子の兵法 「最後に勝つ人」の絶対ルール』三笠書房
・マイケル・フラン他(2022)『専門職としての教師の資本』金子書房
・青井千由紀(2022)『戦略的コミュニケーションと国際政治』日本経済新聞出版
・大治朋子(2023)『人を動かすナラティブ』毎日新聞出版
・Cornelissen, J. (2017) ”Corporate Identity, Branding and Corporate Reputation.” London: SAGE Publications Ltd.
・Grunig & Hunt (1984) ”Managing Public Relations” CBS College Publishing

執筆者:岡田芳樹(おかだ・よしき)
1986年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修了。新卒で政策シンクタンク勤務を経て、横浜市の小学校教諭として7年間勤務。現在株式会社電通総研にて研究員を務める。同時に慶應義塾大学SDM研究所の研究員、大学院のゲスト講師、『週刊教育資料』のコラムニストを担う(「バーンアウト防止に必要なデータによる感情管理」「安易なウェルビーイング教育は感情の資本化を促進する」など)。研究テーマは感情社会学、教育社会学、戦略(コミュニケーションやインテリジェンス)研究など。

