『6つの声』の使い分けで授業が変わる!

新人教員のための学級安定実践13選⑪
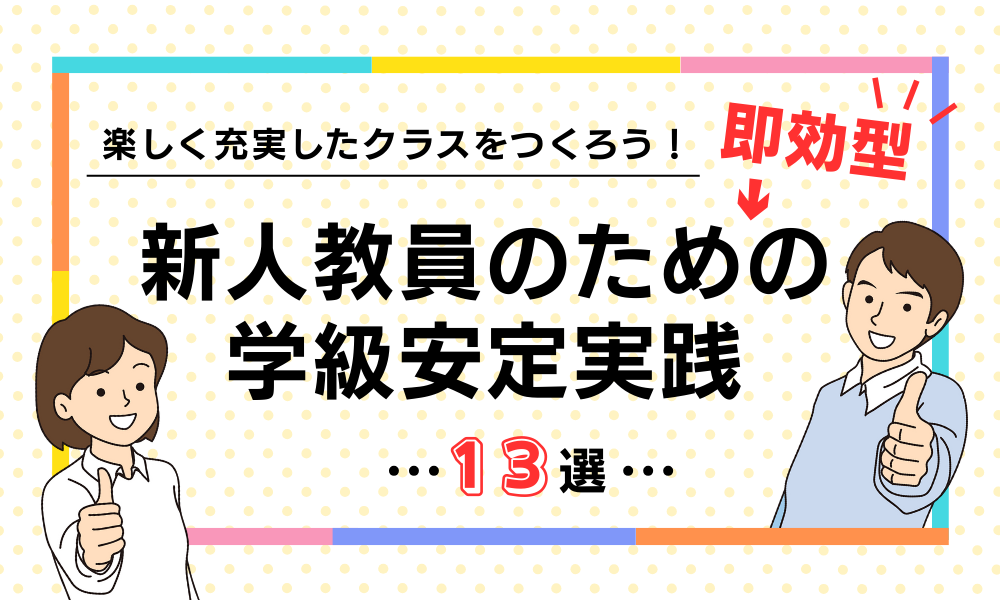
教師の声は、最も基本的で重要な指導技術の一つです。同じ内容を伝えるにしても、声の大きさ、高さ、速さによって子どもたちに与える印象は大きく変わります。多くの教師は「大きな声」を意識しますが、効果的な指導には「大きな声・小さな声」「高い声・低い声」「速い声・遅い声」の使い分けが不可欠です。
執筆/私立小学校教諭・熱海康太
目次
「大きな声・小さな声」の使い分け
教室の隅々まで声を届けることは、教師として基本的なスキルです。しかし、常に大きな声で話し続けると、子どもたちは慣れてしまい、重要な場面でも注意を引けなくなります。
効果的な技術は、突然声を潜めることです。いつもより小さな声で「これからとても大切なことを話します」と言うと、子どもたちは自然と注目し、集中して聞こうとします。この技術は、重要なポイントを強調したいときや、クラス全体の注意を集めたいときに威力を発揮します。

「高い声・低い声」で感情を表現
高い声は、子どもたちの声に近く、親近感を与えます。楽しい活動のときや、子どもたちと一緒に盛り上がりたいときには、普段より高めの声を使うことで、同じ目線に立っていることを表現できます。つまり、高い声は子どもの声と同じだということです。
一方、低い声は安定感と権威性を示します。落ち着いて話をしたいときや、重要な指示を出すときには、低めの声でゆっくりと話すことで、子どもたちに安心感を与え、内容への信頼性を高めることができます。
「速い声・遅い声」でリズムを作る
話すスピードは、授業のリズムを大きく左右します。楽しい活動や、すでに理解できている内容については、テンポよく速い声で進めることで、活動の活気を演出できます。ただし、理解を促す際には速い声では難しいです。この声については、アクセント的に使うことを推奨します。
逆に、新しい内容を説明するときや、重要なポイントを伝えるときには、意識的にゆっくりとした声で話します。子どもたちが内容を理解し、定着させるための時間を確保することができます。また、サザエさんに出てくるマスオさんのように、人を安心させる声でもあります。子どもがあわてているときや混乱しているときには、この声を効果的に使って、落ち着かせるとよいでしょう。
圧に使わない声の原則
6つの声の使い分けで最も注意すべきことは、声を「圧」として使わないことです。大きな声や低い声を使って子どもたちを威圧することは、その瞬間は効果があるように見えても、長期的には信頼関係を損ない、子どもたちの主体性を奪ってしまいます。
緊急時以外は、声を威圧的に使うことを避け、常に子どもたちとの対話を重視した声かけを心がけます。理想は少し小さな声でも学級全体に伝わることです。ただし、聞こえづらい声はそれ自体がストレスになってしまいますので、その辺りは子どもたちとよく確認をしながら行っていきます。
同じパターンからの脱却
多くの教師は、無意識のうちに同じトーンで話し続けています。自分の声の傾向を知り、意識的に変化をつけることが重要です。普段大きな声で話しがちな教師は小さな声を、ゆっくり話す傾向がある教師は時々速く話すことを意識します。
1か月間、意識的に6つの声を使い分ける練習をすることで、声の使い分けが自然にできるようになります。
技術と心の両立
声の技術を身につけることは重要ですが、それに溺れてはいけません。最も大切なのは、目の前の子どもたちをよく観察し、今必要な声を選択することです。技術はあくまでも手段であり、子どもたちの学びを支援するためのツールであることを忘れてはいけません。
バナーイラスト/futaba(イラストメーカーズ)

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

