よくわかる教育委員会〜指導主事の仕事を中心に|第12回 危機管理の基本

学校を取り巻く「危機」には様々なものがあります。感染症・アレルギー・食中毒・交通事故・非行・いじめ・自然災害・施設管理の毀損・教育課程の不履行・財務の不履行・個人情報漏洩・教職員のコンプライアンス違反などなど。これら一つ一つの「危機」に対して、 迅速かつ適切に対応すること(=危機管理)は、 教育委員会に課せられた最重要使命であると言えます。
しかし、 こうした危機管理能力・対応能力は、 教育委員会によって差が生じやすいものです。そしてその差は、 事態が逼迫したり深刻化したりすればするほど顕著な差となって表れるものです。また、こうした「危機」が多様化・重篤化の一途をたどっている一方で、対応の失敗はますます許されないというのが近年の傾向です。
今回は、 数ある「危機」の中でも「自然災害」と「学級が機能しない状況」にしぼって、 いくつかのポイントをお示しします。
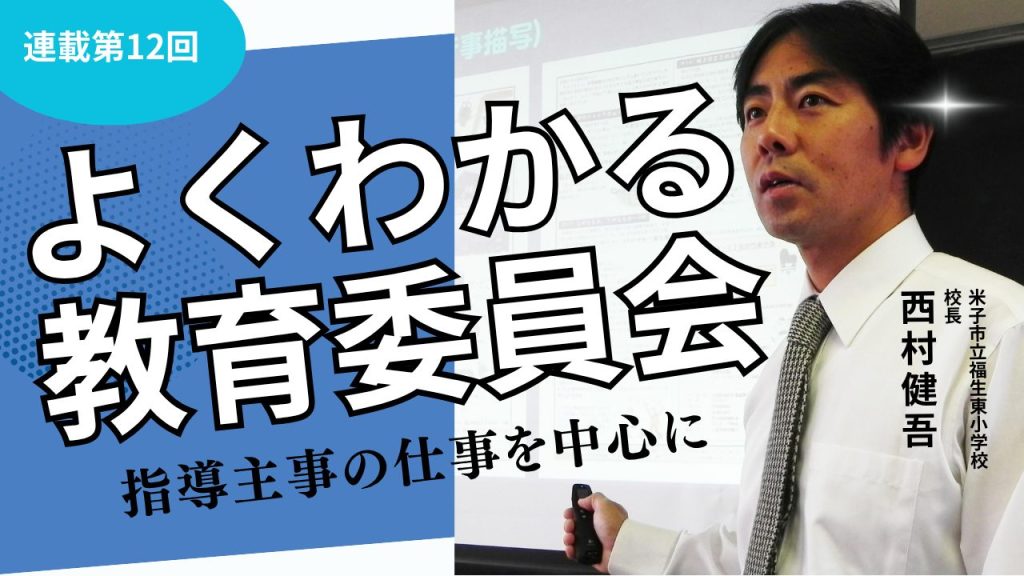

西村健吾(にしむら・けんご)
1973年鳥取県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、鳥取県の公立小学校および教育委員会で勤務。「マメで、四角く、やわらかく、面白い…豆腐のような教師になろう!」を生涯のテーマにしている。学校教育に関わる書籍を多数執筆。近著は『学校リーダーの人材育成術』(明治図書)。現在、米子市立福生東小学校長。本コラムは、10年間の教育委員会事務局勤務の経験を元に執筆している。
目次
自然災害対応のポイント
非常変災その他急迫の事情による臨時休業について
非常変災とは、地震・風水害、火山の噴火、毒劇物や放射能による災害、凶悪犯罪の発生などの緊急事態のことです。これによる臨時休業は、 校長の判断により行われます。その根拠は、 学校教育法施行規則第48 条「非常変災その他急迫の事情があるときは、 校長は、 臨時に授業を行わないことができる」です。教育委員会の承諾なしに、 校長が独断で決めることができるのですから、 これは大きな権限です。
しかし、保護者にとって「近隣の学校は授業をしているのに、 うちの学校だけ休業した」となると、万が一結果が裏目に出た場合、学校は窮地に陥ります。校長が臨時休業の決断をすることは、それだけ責任と勇気が伴うことなのです。
このため、 校長は普通、 近隣の学校に電話で相談するのが常です。しかし、 それぞれの学校がそれぞれに、こんなことをやっていたのでは手間と時間の無駄ですし、対応がまちまちになって混乱を招きかねません。こうしたことを背景として、おそらくは、教育委員会が慣例的に「要請」を出している地域も少なくないことでしょう。
ただしこれは、教育委員会が学校の臨時休業を決めるということではありません。決めるのはあくまでも校長です。この点については双方がきちんと認識しておく必要があります。
さて、このような前提があるものの、一斉の要請を出す教育委員会にも、やはり大きな責任が伴います。多角的・多面的に情報を収集すること、刻一刻と変わっていく状況を注視すること、遠くない未来の状況を見通して予測すること、その上で、数あるツールを駆使して、正確で明快な指示を迅速に出すことが求められます。
メール連絡の重要性と利便性
状況が刻一刻と変化する中では、学校へのきめ細かな指示・連絡は不可欠です。その連絡手段は緊急性や内容によって様々です。自治体によっても異なるでしょう。
しかし、緊急なものについては、メールまたはメッセージアプリを使うことが一般的になってきたのではないでしょうか。個人的には、令和2年度に端を発した新型コロナウイルス感染症対応が、メールでの連絡を急速に進めたと感じています。
もはや言うまでもないですが、緊急連絡の手段として、メールやメッセージが優れているのは次の点です。
- 送信日時・宛先・内容が自動的に記録されるため、後から「誰に・いつ・何を伝えたか」を明確に確認できる。
- 送信履歴を正式な記録として残せる。
- 複数宛先への一斉送信が容易であり、電話と違い通信が混雑しても比較的安定して伝達できる。
- 緊急時の指示・対応手順・連絡先などを誤りなく伝えることができ、受信者も読み返しながら確認できる。
- PDF・画像・地図などの資料を添付できるため、避難経路や対応マニュアルなどを同時に共有できる。
- 電話のように相手の作業を中断させず、受信者が状況を見て対応できる。
ただし、メールでの連絡は、各校長の私物携帯(スマートフォン)への送信になっている自治体がほとんどでしょう。私物携帯は、教育委員会・学校組織の管理下にない端末ですので、これを緊急連絡の手段として使用することは、情報管理・危機管理・コンプライアンスの観点から適当ではなく、今後、自治体として改善すべき点だと感じています。
冗長性としての電話連絡
メールによる緊急連絡のデメリットとして、校長がメールを確認するまでのタイムラグが生じる可能性が挙げられます。したがって、とくに急を要する連絡の場合、メール送信と同時に各学校へ電話連絡を行った方がよいこともあります。メールに加えて電話するメリットには、次のような点があります。
- 確実な「受信確認」が取れる
- 緊急度や状況の「温度感」を伝えられる
- 相手の状況に応じた柔軟な指示・相談が可能
- その場で指示・決定・行動につなげることが可能
- 多重連絡による冗長性(予備や重複を持たせること)が確保できる
若い世代になるにつれ、メールやメッセージが主な連絡手段となり、電話は敬遠されがちです。しかし、組織において緊急かつ重要な情報の伝達には、複数の伝達手段が欠かせません。もし、FAXが重要な連絡手段になっている自治体があれば、それを使うことも大切です(ただし、FAXによる一斉送信は、全ての学校に行き渡るのにこれまたタイムラグが生じるという難点もありますが…)。いずれにせよ、日頃から、情報伝達の冗長性は常に意識しておくことが肝要です。
校長向け文書例
緊急連絡のメールは、文面も重要です。通常の行政文書のような書き方では、読み間違いや読み落としが発生する公算大です。以下、台風のときの対応連絡をするメールを例に解説します。
良くない例
【9月2日(火)事務連絡】
台風9 号、10 号の影響が心配されるところですが、本市防災安全課に確認したところ、ひとまず台風9 号については、本市への大きな影響はない見込みのようです。ただし、明日3日(水)未明から朝方にかけて最接近する予報ですので、万が一天候(風雨)の著しい悪化が確認された場合、特に朝の登校時の見回り等、必要に応じてご検討ください。
一方、特別警報級とも言われている台風10 号については、台風9号よりも西寄りを進み、今のところ朝鮮半島へ向かう予報です。ただ、予報円が大きく、進路が東側(本市側)に寄る可能性もあるため、まだまだ予断を許さない状況です。現在のところ最接近想定時間帯は来週月曜日の朝方であることから、ひとまず状況を注視し、いずれにせよ5日(金)の午前中までには再度ご連絡いたします。
なお、現時点では、本市教育委員会から各学校へ特段の要請を行う予定はありません。体育祭・運動会や修学旅行等を控え、大変心配されるところですが、よろしくお願いいたします。
この文書は、行政文書らしく正確ではあるものの、情報が詰まりすぎており、「どこが重要なのか」「どう行動すべきか」が伝わりにくい構成となってしまっています。なお、この文書は“詰まりすぎ”という文書構成上の問題ですが、中には、余分な情報が多く混じっている文書も散見されます。情報過多は真に大切な情報が薄まることも肝に銘じておく必要があります。
いずれにせよ、緊急連絡の文書では、余分な情報を極力カットし、必要な情報だけを、文の切れ目を明確にし、重要点を先に、行動を後に配置しながら伝えることが大切です。
改訂例
【9月2日(火)台風対応連絡】
台風9号、10号ともに、本市教育委員会から各学校へ特段の要請を行う予定は今のところありませんが、以下、情報提供します。
■台風9号への対応について
本市防災安全課によれば、台風9号による本市への大きな影響は現時点では見込まれていません。
最接近は明日3日(水)未明から朝方にかけてとの予想です。そのため、風や雨が強まるなど、天候の急変が確認された場合には、とくに登校時の安全確保にご留意ください。
必要に応じて、見回りなどの対応を各校でご判断ください。■台風10号への備えについて
「特別警報級」とも言われている台風10号は、現在の予報では、台風9号よりも西側に進路を取り、朝鮮半島方面へ進む見込みとのことです。
ただし、進路が東寄り(本市側)になる可能性があり、予断は禁物です。
最接近は来週月曜日の朝方との予想です。
今後の情報を注視しつつ、状況が変わる場合には、5日(金)の午前中を目途に改めて連絡します。■今後の行事等への影響について
体育祭・運動会、修学旅行などを控え、心配な時期かと思います。
まずは児童生徒の安全確保を最優先に、各校で無理のない判断と対応をお願いします。
引き続き、最新の気象情報にご注意ください。
保護者向け文書ひな形例
学校が保護者向け文書を発出する必要があるケースでは、教育委員会が、以下のような文書ひな形を作成し、各学校に配信することもあります。
従来は紙で配付することを想定し、Wordなどワープロソフトのひな形を配付することが多かったと思いますが、今や保護者へのメールやメッセージでの連絡が一般的です。ひな形も、メールを想定した形で、かつ、スマートフォンなど、縦長の画面で読むことを想定して作成する必要があります。ポイントは次の3点です。
- 結論を冒頭に明示する
- 条件・対応・連絡方法を箇条書きで整理
- 「万一のときの判断基準」を具体化
太字やアンダーラインが使える環境にある場合は、適宜使用するとさらによいでしょう。具体的には次のような文例が考えられます。
【保護者の皆さまへ】台風10号への対応について(お知らせ)
令和〇年9月5日
〇〇市立〇〇学校
校長 〇〇 〇〇1.登校について
9月8日(月)は、現時点では通常通りの登校とします。
現時点での予報では、台風10号による本市への大きな影響は見込まれていません。2.ただし、次の点にご注意ください
登校時に風や雨が強い場合は、登校を急がず、状況を見て安全を最優先にしてください。
危険と判断される場合は、→ 自家用車で送っていただいても構いません。
→ 始業時刻に遅れても、遅刻扱いにはしません。学校は、この日は〇時〇分に開錠しますので、早めに到着しても校内で安全に待機できます。
3.今後の連絡について
台風の進路や強さによっては、状況が急変する可能性があります。
登校方法などに変更がある場合は、9月7日(日)午後5時までに以下の方法でお知らせします。1. 緊急連絡メール
2. 学校ホームページ
3. 電話連絡(必要に応じて)
※ これらの連絡がない場合は、「通常通りの登校」とお考えください。
4.お願い
最新の天気情報や、メール・ホームページの更新をこまめにご確認ください。
お子さんの安全を第一に、無理のない対応をお願いいたします。
学級が機能しない状況への対応のポイント
学級が機能しない状況の背景
とくに小学校において、子どもたちが継続的に問題行動を起こして授業が成立しない、教師の指示・指導が入らないといった「学級の荒れ」が問題になっています。この状況に陥ると、その年度内の立て直しに多大な時間と労力を浪費するばかりでなく、数年間にわたる対応が強いられることがあります。
こうした「学級の荒れ」は、必ずしも指導力のない教師の学級で起こるものではありません。指導力があり、学校の中核となっている教師の学級でさえ起きる可能性があります。その原因や背景には、次のようなことが考えられます。
- 担任の指導力が十分とは言えず、指示や指導が入らない場合
- 発達や愛着形成に課題がある、養育環境・家庭環境に課題があることなどに起因する、指導が通らない子どもへの対応がうまくいかず、その影響が学級全体へ波及する場合
- 私語や離席などへの指導が年度当初から徹底されず、次第に他のルールもなし崩しになる場合
- 指導が通りにくい子ども(2割)にうまく対応できず、落ち着いたリーダー層(2割)から教師が愛想をつかされ、残りの子ども(6割)が一斉にそちらへなびいてしまった場合(2:6:2の法則、パレートの法則)
- 前年度より既に学級崩壊に近い状態になっており、教師と子どもの信頼関係が築けていない場合
学級を立て直すときの指導主事の視点
こうした学級が機能しなくなった状況で、指導主事が学校に入らざるを得なくなる場合があります。これは、既に担任の指導に従わない児童生徒が複数いて、担任や管理職だけで改善に向かわせることが難しい状況に至っているということです。
その状況に至るまでに、学校はある程度原因を分析し、何らかの対応を取っているはずですから、学校に入るときには、まずその内容を把握し、尊重する姿勢が必要です。ただし、その対応の是非については、客観的に評価し、改善の必要があれば指導していかなければなりません。
いずれにしても、学校へ入る段階において、丁寧な観察や聞き取りを行い、情報を整理するとともに、原因と経緯を分析し、解決に向けたある程度の方向性を見いだす必要があります。
担任への指導
学習環境の整備
荒れた学級では、「ロッカーの乱れ」「きちんと上靴を履けない」「授業中の姿勢の悪さ」「私語の多さ」「机から物がよく落ちる」「床にいろいろな物が散乱している」など、教室に入った瞬間に目を覆うばかりの光景が広がっています。学級の立て直しには、こうした乱れを正していく必要があります。ただし、一気に改善しようと細かいことに目くじらを立てながら指導したのでは、子どもたちのさらなる反発を招いて逆効果です。したがって、焦らず、少しずつ、スモールステップで取り組んでいく必要があります。
例えば、「上履きを全員がしっかり履く」という目標を立てます。この目標を子どもたちと共有し、一定のスパン(1週間〜2週間)内に目標を達成できるよう取り組みます。目標が達成できれば、子どもたちをしっかりと褒めます。仮にできなくても、進歩した部分を認めて褒め、次の取組につなげます。
こうやって2〜3つの目標を達成できたあたりで、急速に学級の雰囲気が変わることがあります。小さな目標達成のおかげで、クラスに一体感が生まれ、教師との間に信頼関係が生まれるからです。もちろん、そう簡単にはいきませんが、こうして学習環境を地道に整えていくことが、学級の立て直しの第一歩となります。
授業を再構築する
荒れた学級では、通常の授業が全く成立しません。担任が、そうした状況を何とかしようと、従来の授業形式を徹底させようとすればするほど、ますます成立しなくなります。そうこうする内に、いわゆる「学習空白の時間」が生じ、混乱はますます深まります。これにより、学力が低調になり、「学習が分からない」「授業がつまらない」といった不満を子どもが家で訴え出すと、保護者からのクレームが学校に一気に押し寄せる段階に突入してしまいます。
こうした状況に陥らないように、学級の「沈静化」ではなく「安定化」を図るべきです。安定化のための一つの方法として、授業の再構築があります。思い切って授業に対する既成概念を転換するのです。以下に、いくつかの例を示します。
- 「読み聞かせ」→「音読」→「漢字練習」→「授業」→「プリント」といった形で、10 〜15 分単位の学習活動の組み合わせで授業を構成する。こうした授業は、「ユニット型・パーツ型・オムニバス型」などと呼ばれます。目先を変えることで、集中を持続させる効果のある授業方法。
- 朝休憩や長休み(業間休憩)、掃除時間明けなどを経て授業に入る場合は「読み聞かせ」から始める。子どもたちの「興味があること」を設定し、「遅れて来ると損をする」という状況を作りだす。遅れた子を叱る必要もなくなるので、自然とチャイム着席が守れるようになるケースが多い。
- 授業に向かおうとする子どもの学力を保障するために学習プリントを多用する。がんばろうとしている子たちの学力の保障が「肝」。
- 対話的な学習活動を設定し、「合法的立ち歩き」を奨励する。子どもたちのコミュニケーション欲求が満たされ、落ち着く場合がある。
寄り添いながら基本的な教育技術を教える
指導力が十分ではない若手教員の場合、指導言が曖昧だったり、多すぎたり、言葉そのものが分かりにくかったりすることがあります。こうした教室の子どもは、
- やる気はあるのに先生の言っていることが分からない
- →だんだん面白くなくなる
- →先生の言うことを聞いても仕方がない・聞きたくない
といった流れになりがちです。こうした流れが見えていない教師は
- 子どもたちに分からせようとさらに詳しく(くどく・まどろっこしく)説明(指示・発問)する
- →一生懸命説明しているのに分からない子どもを叱る
といった悪循環に陥ります。
教室に入った指導主事は、こうした教師に対して「一時に一事の説明・指示」や、「スモールステップの説明」、「発問した後の待ちの姿勢」など、基本的な教育技術を具体的に教えていく必要があります。状況によっては管理職に代わって、丁寧に担任に伝えていくことも大切です。
ただ、こうした教師は、指導主事が入る前から相当疲弊しているはずです。指導主事が入るとさらにモチベージョンが低下してしまう可能性があります。ただ、逆に「もしかしたら指導主事は自分を助けてくれて、改善方策を示してくれるのではないか」という期待感を持っている可能性もあります。指導をする際には、こうした心理を慮りながら、しっかりと担任に寄り添い、伴走していく姿勢が求められます。

