保護者クレームの電話対応の達人になる 〜声だけで信頼を築く技術〜

保護者クレーム対応の実践スキル 危機を絆に変える技術⑥
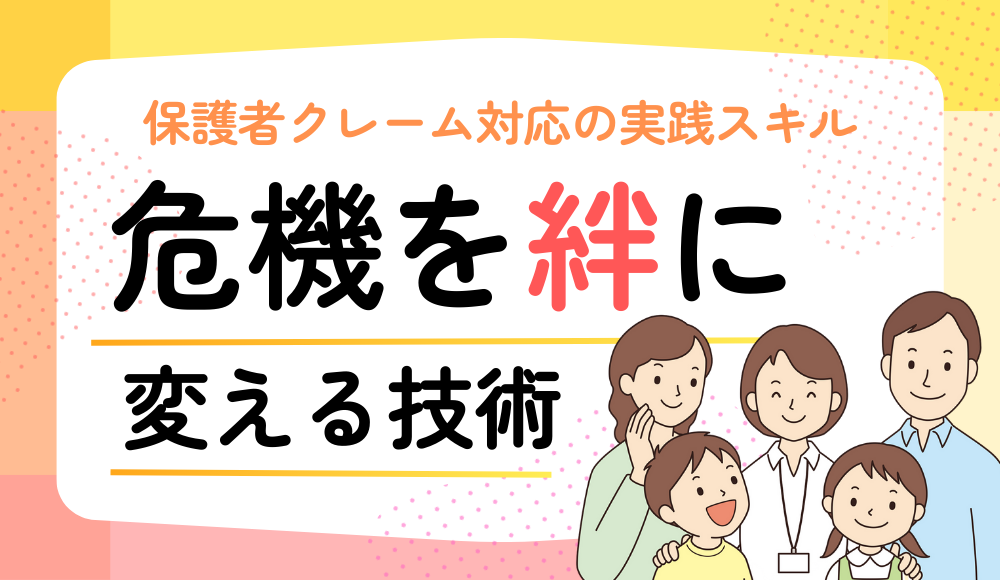
現代の教育現場において、保護者との最初の接点は電話であることが多くなっています。しかし、電話でのコミュニケーションは、表情や身振り手振りといった非言語的な情報が伝わらないため、対面での対応以上に高度な技術が求められます。
執筆/一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事・熱海康太
目次
電話対応の基本フローの確立
効果的な電話対応を行うためには、まず基本的なフローを確立することが重要です。電話を受ける際の第一声は「お電話ありがとうございます。○○学校の○○でございます」が基本形となります。「もしもし」という表現は避け、より丁寧で正式な応答を心がけることで、最初から相手に良い印象を与えることができます。
続いて「いつも大変お世話になっております」という挨拶により、日頃の関係性に感謝の気持ちを示します。この一言があることで、相手は歓迎されていると感じ、話しやすい雰囲気を作り出すことができます。特にクレームの電話の場合、相手は緊張や不安を抱えていることが多いため、温かい挨拶により心理的な障壁を下げることが重要です。
通話の最後には「お電話をいただき、ありがとうございました」「○○が承りました」「それでは、失礼させていただきます」という流れで丁寧に終了します。受話器を置く前に指で切ることで、不快な音が相手に聞こえることを防げます。
担当者不在時の適切な対応
クレームの電話において、担当者が不在の場合の対応は特に重要です。「申し訳ございません。担当の○○は席を外しております」と現状を正直に伝えた上で、「こちらから折り返しをさせていただきます。何時頃がご都合がよろしいでしょうか」と具体的な対応策を提示します。
この際、相手の電話番号と要件を必ず確認します。「お電話番号を教えていただければと存じます」「ありがとうございます。電話番号090…、○○様から○○の件のご連絡があった旨、担当の○○に伝えます」といった形で、情報を復唱することで正確性を確保し、相手に安心感を与えることができます。
大切なことは相手に「たらい回しにされた」という印象を与えないことです。電話を受けた人が責任を持って担当者に確実に連絡を取り、折り返しの約束を守ることが、組織としての信頼性を維持するために不可欠です。
声による信頼関係の構築
電話対応では、声がすべての情報を伝える唯一の手段となります。そのため、声のトーンや話すスピード、間の取り方などが、相手に与える印象を大きく左右します。基本的には、普段よりもやや低めのトーンで、ゆっくりと話すことを心がけます。高い声は緊張や不安を伝えやすく、早口は相手に圧迫感を与える可能性があります。
相手が感情的になっている場合は、こちらの声のトーンをさらに意識的に落とします。相手の声が大きくなっても、こちらは落ち着いた低い声を維持することで、相手も自然と声のレベルを下げる傾向があります。これは電話特有の現象で、対面以上に声のトーンの影響力が大きいためです。
また、適切な間を取ることも重要です。相手が話し終わった後、少し間を置いてから応答することで、相手の話をしっかりと聞いていることを示すことができます。ただし、間が長すぎると相手に不安を与えるため、2〜3秒程度の適切な長さを心がけることが大切です。
効果的なメモの取り方と情報管理
電話対応において、正確で効果的なメモを取ることは極めて重要です。対面での対応と異なり、後から相手の表情や雰囲気を思い出すことができないため、会話の内容や相手の感情状態まで含めて記録しておく必要があります。
基本的な情報として、日時、相手の名前、連絡先、要件を5W1Hの形式で整理します。さらに重要なのは、相手の感情状態や話し方の特徴、強調していたポイントなども記録しておくことです。これらの情報は、担当者に引き継ぐ際や、今後の対応を検討する際に貴重な参考資料となります。統一されたメモのフォーマットを使用することで、必要な情報を落とさずに記録することが可能になります。

長時間通話への対処法

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

