不登校への対応とは?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #29

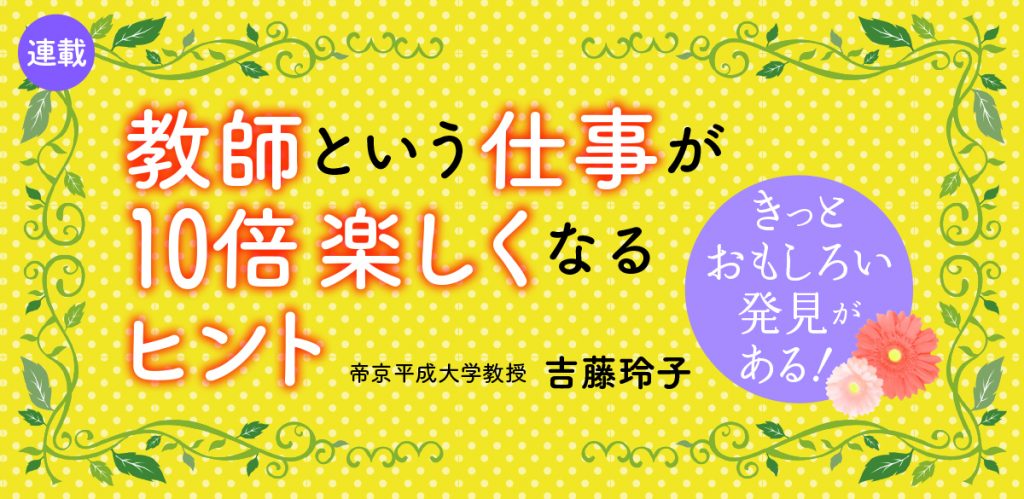
「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」の29回目のテーマは、「不登校への対応とは?」です。夏休み明けは学校に行きたくないという子供が増える時期です。不登校の子供への対応をどのようにするのがよいのか、考え方や対策など様々なヒントをお届けします。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等、様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
不登校を体験した学生たち
大学生たちと話していて、「実は、小学校の4年生のときに不登校になりました」「中学校で本当に学校が嫌になりました」などの話を聞くことがあります。でも今、彼らは決意して先生になるべく勉強をし、不登校の子供たちの相談に乗りたいと話します。彼らの人生で不登校の時期はあったかもしれませんが、それを克服して前に進んでいます。かつて不登校児童や生徒であってもこのようなうれしい事例もあるのです。
長い夏休みが終わると学校へ来なくなる子供がいます。担任をしていて自分のクラスに不登校の子供が現れると本当に落ち込みます。自分の対応のどこがいけなかったのか、その子供と他の子供との関わりの何を見逃していたのか、もっと子供の話に耳を傾けてあげればよかったなど、真面目な先生たちほど悩みます。
今、日本の教育は個別最適な学びを奨励し、一人一人の子供を大切にする方向になっています。しかし、一人一人に最適な学びの環境を追究していくと、現状の学校現場のあり方では対応できない子供もたくさんいます。今回は、不登校の子供がクラスに現れたときにどう考えたらよいかを述べたいと思います。

不登校の子供を受け入れる
まず、「不登校はだめ」という概念を捨てましょう。そうでないと、担任も不登校の子供も苦しみます。まず担任は、自分を否定的に考えることはやめましょう。不登校を経験した学生に聞くと、何が何でも学校に来いと言われたときはきつかった、「今日登校できなかったら、ゆっくり考えようね。いつでも待っているから」と担任の先生に言われたときはうれしかったと話しています。
「不登校=だめなこと」ではなく、不登校を受け入れる度量をもちましょう。私たちには学校に毎日来なくてはいけないという概念がありますが、多様な子供が増えている今日、いろいろなケースがあるのだと受け止めましょう。不登校の子供には、何か学校に来ることができない理由があるはずです。学年の先生や管理職と相談しながら、焦らずにその子供とどう向き合っていくかを考え、いろいろ声かけをしてみることが大切です。不登校に関する本は数多くあります。でも、不登校になる理由はその子供にしか分かりません。パターン化できるものでもないのです。解決方法は一人一人違うと思います。
担任は根気よく話を聞く姿勢をもって不登校の子供と関わるようにしましょう。そして、まずその子供を安心させることが大切です。学校に来ていない時間、その子供が何もしていないのではと思いがちですが、その子なりに日々を過ごしています。「学校に来られなくても大丈夫。本当は今すぐ来てほしいけれど、時間をかけてその時を待っているから」というぐらいの余裕をもって対応しましょう。
ステップ バイ ステップ
まず、不登校の子供の保護者と連絡を取ります。保護者の方に「子供が学校に行くようになってほしい」という思いがある場合は、さらに連絡を取り続け、家庭訪問に行きましょう。可能なら自分だけではなく、学年主任や養護教諭、場合によっては管理職にも同行してもらってはどうでしょうか。
私は、校長職をしているときに担任と一緒に家庭訪問をしたことが何回かあります。不登校の子供を抱えた保護者もつらい思いをしています。担任が子供と話している間、私はお母さんの話を聞いていました。そのうち保護者から「何とか1時間、まず学校にいることができるように子供を説得してみます」という話を聞くことができました。彼が登校できなくなったのはクラスの友達とのトラブルでした。そのため家庭訪問と並行してそのトラブルがあった子供との対応もしていきました。彼は、保護者と一緒に1時間だけ学校に来るようになりました。でも、教室へは入れませんでした。会議室で担任が用意したプリントを使って学習していました。そのうち、会議室で2時間程度過ごすことができるようになり、給食も食べられるようになりました。クラスの子供たちが入れ替わり立ち替わり給食を運んでくれました。給食を持ってくる子供たちと話しているうちにいつしか、「教室で給食を食べる」と言い出し、自然に教室に入れるようになりました。トラブルがあった子供との関わりも解決し、無事にその子供は卒業しました。
これは、一例にすぎません。不登校の場合、その子供によって対応方法はまったく変わってくるからです。私が言えることは「焦らないでください」ということです。このケースのように子供や保護者に会って話ができる場合はよいのですが、そうでない場合もあります。不登校の子供が担任の先生にも会いたくないという場合です。その場合は訪問しなくても手紙を書くなど別の方法でアプローチをしてみてください。何度か学校のお知らせと一緒に担任からの手紙をポストに入れているうちに不登校の子供から電話がかかってきたという例もありました。
不登校児童の場合、学校に来てもすぐに教室に入ることができない事例がほとんどです。保健室や図書室、場合によっては校長室登校などという事例もあります。私の仲の良い校長は校長室にプラスチック汽車・レールセットなど電車の模型を置き、教室に入れない子供の心をほぐしていました。
図書室には来ることができるという子供もいました。司書の方にお願いして、図書室に来たときに彼女の気持ちを聞いてもらいました。受験勉強で悩んでいるようでした。話を整理して、保護者とも面談をしました。志望校を変えただけで、その子供は登校できるようになりました。受験と学校への登校など関係がないように思えますが、子供ながらに何かを抱えている不安が大きいといろいろ影響もあると思います。スクールカウンセラーなどにも相談して、担任だけで不登校の問題を抱え込まないで対応していくことが大切です。
学ぶ場所は学校だけではない
1人1台のタブレット端末が普及し、家庭でオンライン授業が受けられるようになりました。出席停止の感染症で学校へ来ることができなくても授業の様子を知ることが容易になりました。私は、オンライン授業はよいことだと思います。もちろん対面のほうが小学校段階の子供にはよいでしょうが、不登校の場合もオンラインで授業の様子を知らせることも1つの手段です。授業が楽しそうであれば子供の興味も引くでしょう。場合によっては、話合いなどにもオンラインで参加してもらってもよいかもしれません。
また、昨今フリースクールなど私塾的な教室がたくさんあります。私の経験で、クラスの人数が少ない低学年のときには登校できたが、高学年になってクラスの子供の人数が増えてしまったら通えなくなった子供がいました。その子供はフリースクールに通っていました。その家庭には、学校からのお知らせは定期的に届けていました。保護者は学校だよりによく目を通してくれて、学校行事のあるときには不登校の子供を連れてきてくれました。行事にも部分的に参加できました。卒業式は残念ながら別室でしたが、無事に小学校を卒業することができました。
多様な形の学びの場が今はあります。もちろん学校に来てほしいのですが、それができない場合、学校側も視野を広げて不登校の子供と向き合うことが大切です。
みんなと一緒に学ぶ楽しさを大切に
学校行事は楽しいものが多いです。まず、子供は楽しいこととして「運動会」を挙げます。高学年になれば「移動教室」でしょうか。その他、「マラソン大会」や「子供祭り」「学習発表会」など学校で行われるイベントを嫌う子供は少ないです。これらの行事は1人ではできません。みんなで行うから大玉送りも玉入れもおもしろいのです。赤白と応援するから盛り上がるのです。みんなと一緒に同じ部屋で寝るから楽しいのです。
人と一緒に取り組む活動をイベントだけでなく毎日の授業の中にも取り入れていきましょう。例えば、学区域の危険な場所について学習するときなども、オンラインで話合い参加はできますが、実際に教室で学区域のマップに気付いたことを友達と話し合いながら付箋に書いて貼っていく活動のほうが、子供には楽しいのです。
ぜひ、友達と学ぶ楽しさを日々の授業に取り入れてください。クラスが楽しいとみんなが思えるような学級づくりをしてください。人は1人では生きられません。不登校の子供も何とかクラスに戻って、みんなと一緒に活動したいと思えるようなそんな学級づくりを目指したいものです。
構成/浅原孝子 イラスト/有田リリコ

