「教科書検定制度」とは?【知っておきたい教育用語】
4年に一度実施される各教科書の検定。とくに歴史教科書においては領土問題など、表記や表現に慎重にならなければならない教科書もあります。今回は「教科書検定制度」をテーマに、その内容や意義、歴史とこれからの課題について見つめ直していきます。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・宮崎猛
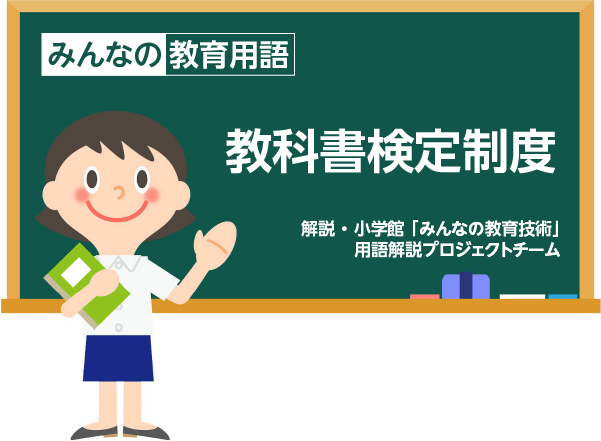
目次
教科書検定制度とは
【教科書検定制度】
文部科学省が教科書として使用される図書の内容や表現について審査し、学習指導要領に準拠しているかを判断する制度。小・中・高の公教育に用いる教科書は、この検定を経たものでなければ使用できない。
教科書検定では、民間の教科書会社が作成した教科書原稿を、文部科学省が設置する教科用図書検定調査審議会の専門委員や教科書調査官が審査します。審査の基準は、学習指導要領に準拠していること、教育上不適切な内容が含まれていないこと、記述の正確性や客観性が担保されていることなどです。
検定では、誤記や誤解を招く表現だけでなく、歴史や科学の記述における事実誤認や、偏った見解の押しつけ、差別的表現なども対象となります。指摘があった場合、教科書会社は修正を行い、再提出しなければなりません。
また、特定の価値観や政治的立場に偏らない中立的な視点が求められており、検定意見によっては表現の言い換えや削除が求められることもあります。検定の透明性と客観性を確保するため、意見や修正履歴は公表される仕組みが整えられています。
教科書検定制度の意義
教科書検定の最大の意義は、公教育における教育の質と中立性を確保することにあります。日本の教育は学習指導要領に基づいて行われており、教科書はその重要な教材です。検定制度を通じて、学習指導要領に準拠した内容が全国的に保障されることで、教育の機会均等が実現されます。
また、検定によって、教育内容が一定の客観性と信頼性をもって構成されることが期待されます。とくに歴史や公民といった日本国民としての立場や価値判断が関わる教科では、過度に一方的な見解や誤情報が含まれるリスクを防ぐ役割も果たしています。
さらに、学習者の発達段階に応じた適切な表現や配慮、差別的・不適切な記述の排除を促す点でも、検定の存在は意義深いものです。ただし、言論・表現の自由とのバランスを常に念頭においた、透明性のある運用が求められます。

