「子どもの幸福度」とは?【知っておきたい教育用語】
2025年5月14日にユニセフ(国連児童基金)から子どもの「幸福度」を調査した結果が公表され、日本は「先進国36カ国版」において、14位という結果でした。今回はこの結果をもとに、子どもの「幸福度」とは何を指標としているのか、調査から見えてくる日本の子どもの現状、これからの社会および教育のあり方について考えていきます。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴
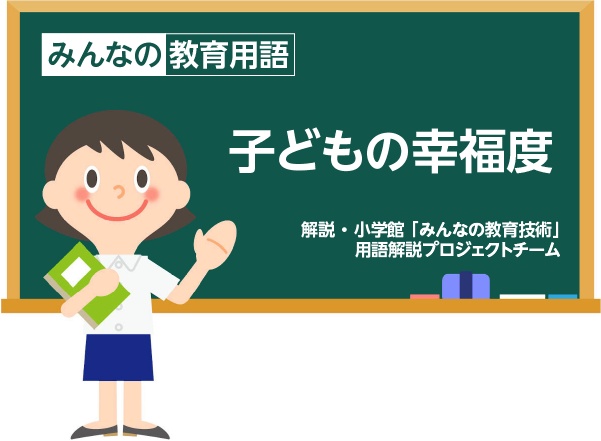
目次
「子どもの幸福度」とは
【子どもの幸福度】
ユニセフによって、身体的健康(Physical Health)、精神的幸福度(Mental Well-being)、スキル(Skills for Life)の3つの領域から調査測定し、それをエビデンスとして、子どものウェルビーイングの状態を表したもの。
ユニセフの子どもの幸福度調査(Report Cardシリーズ)は、2007年の第1版(Report Card 1)から始められました。その後、ほぼ5年ごとに改訂され、2025年に発表されたものが、最新版である「Report Card 19Child Well‑Being in an Unpredictable World(予測できない世界における子どものウェルビーイング)」です。
多くの先進国において、子どもの貧しさや危険な環境にいるといった課題は、途上国の問題だと思われがちでした。しかし実際には、先進国のなかでも、子どもが孤独・不安・貧困に苦しむ状況が深刻であるというデータが徐々に示されるようになり、その実態を明らかにする必要が認知されました。
そもそもユニセフとは、1989年に採択された「子どもの権利条約」を実現する、国際的な機関です。子どもの条約には、子どもの「生きる権利」や「健やかに育つ権利」、「保護される権利」、「意見を表明し、尊重される権利」などの基本的なものが含まれています。この抽象的な「権利」を、具体的で測定可能な形で実現・点検するための手段として幸福度指標が設けられ、経年的に測定していくことになったものが、ユニセフの「幸福度調査(「Report Card」シリーズ)」です。
幸福度調査は、信頼性の高い国際データをもとに、総合的なスコアを算出し、各国を比較して順位付けする形式になっています。これは単なるランク付けではなく、国ごとに「子どもにとっての社会の姿」を点検し、政治や教育制度の責任を明確にすることを目的としています。つまり、その国の政府や社会に「子どもにとってよりよい環境づくり」を促すための国際的な「圧力装置」として機能させる役割を果たしているといえます。
日本の子どもの現状
幸福度調査の結果は、ユニセフ・イノチェンティ研究所の報告書 「レポートカード19:予測できない世界における子どものウェルビーイング」として、2025年5月に発表されました。
調査の結果は、地球規模で発生した新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けたことを前提として考察されており、コロナ禍によって多くの先進国で、子どもの学力、心の健康(精神的幸福度)、身体的健康がいずれも悪化傾向にあると報告されています。とくに、一部の国や地域では、3〜12か月にわたる長期の休校が実施され、その結果、多くの子どもたちが学習の機会を失い、必要な学習レベルに達するのが難しくなっていると指摘されています。
このなかで、日本の子どもは、身体的健康の分野で第1位という高い評価を受けました。これは、乳児死亡率の低さ、予防接種の普及、平均寿命の長さなどの要因によるものです。一方で、精神的幸福度については深刻な課題が浮き彫りになっています。この分野は、子どもたちの生活満足度や自尊感情などの「主観的な幸福感」に関する指標で評価されます。日本は、この分野で調査対象37か国中32位と、非常に低い順位となっています。
例えば、「自分には価値がある」と感じている子どもの割合や、「自分の人生に満足している」と答えた割合が、他国と比較して、とくに低い結果でした。また、2025年度の小・中・高校生の自殺者数は過去最多となる527人(暫定値)にのぼっており、日本の子どもや若者の精神的なウェルビーイングの脆弱さを示す深刻な現実が明らかになっています。
さらに、学びに関するスキルや社会的スキルについては、日本の学力テストの平均点は高い水準にある一方で、学ぶ意欲や将来への希望といった側面においては消極的な傾向が見られます。「勉強が好きだ」と答える割合が低く、「学校の学習が自分の人生にどのようにつながるか」を実感できていない子どもも少なくありません。
このような調査結果から、「物質的に満たされていても、心理的・社会的には孤立している」という、日本の子どもの現状が浮き彫りになっているという見方もあります。いじめ、不登校、家庭内の孤立、進学や将来への不安といった複合的な要因が、幸福感の低さに影響しているのでしょう。

