子どもが自由に実験器具を選べる理科室作り【理科の壺】

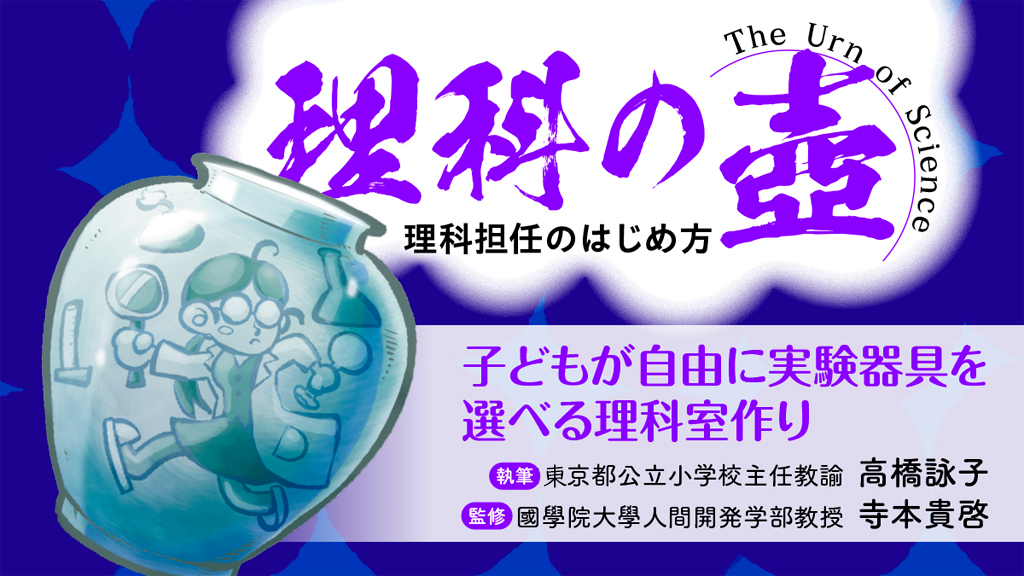
子どもたちに理科室を探検させたり、器具を触らせたりしていますか。子どもたちにとって理科室にあるものは、不思議な道具と感じるかもしれません。子どもたちに自分の力で実験をさせたいという気持ちは多くの先生がおもちだと思います。でも、実験器具がどこにあるか教えないといけないとか、子どもたちに触らせた大丈夫? と不安もあるかもしれません。でもそれは余計な心配かも。意外に先生が不安に思っているだけで、子どもたちでもできることはありそうです。今回は子どもが自由に実験器具を選べる理科室作りです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/東京都公立小学校主任教諭・高橋詠子
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
実験準備が大変! だから理科の指導は苦手?
理科=準備が大変だと思う先生もいらっしゃるかもしれません。第6学年「ものの燃え方」を例に準備物を挙げると、底なし集気びん、集気びんのふた、ろうそく、ろうそく立て、粘土、マッチ、燃えがら入れ、濡れ雑巾…。これらを班の数分、マッチは、班の人数分準備をするだけで多くの時間が必要です。理科支援員に準備を依頼するケースもあるようですが、いざ授業を行おうとすると不足している物があり、慌ててその場で準備する…といったことも耳にします。理科の楽しさに気付くことなく、理科は大変だから苦手と思われていることがとても残念です。
理科室は主体的に学ぶための宝庫!
私が小学生のとき、理科室は見たことのない実験器具がたくさんあり、宝箱に入ったような気持ちになったことを今でも鮮明に覚えています。恐らく子どもたちも同じような感覚ではないでしょうか。しかし、「先生が用意したもの以外には触ってはいけない」といった暗黙のルールが理科室にはあり、子どもたちは宝物を目の前にじっと見つめているのが現状です。私はこのルールこそ先生を苦しめていると考えています。当然、薬品や火を扱うものは安全上むやみに触らせることはしませんが、例えばビーカーはどうでしょうか。ガラス棒は?スポイトは?子どもが棚から取り出しても何も問題はありません。ビーカーを例に挙げると、50mLから1000mLの物があります。どの大きさが適切か、個数はいくつ必要か、子どもが選択することにより、見通しをもって観察、実験を行い、わくわくした気持ちをもちながら学ぶことができます。
理科室で宝探し!
子どもが必要な実験器具を考え、準備をするためには実験器具の適切な使い方や収納場所を知っている必要があります。私は、理科室での一回目の授業で「理科室開き」を必ず行います。はじめに、理科室の約束を一つ一つ丁寧に話をします。長い髪は束ねること、机上は常に整理すること、実験は立ってすることなど、理由と共に話をします。次に、宝探しと題し、理科室にある実験器具を5つほど黒板に書きます。実際にその学年で使用する実験器具だと有用性があります。第6学年の場合、ビーカー、試験管立て、シャーレ、駒込ピペット、集気びんなどを例に挙げるのがよいでしょう。時間を決め、班ごとに実験器具を集めさせます。たったそれだけで、子どもは夢中になって引き出しや戸棚を開け、実験器具を探そうとします。最後に答え合わせをする際、教師が収納場所から実験器具を取り出し、適切な使い方を子どもに伝えます。
この1回の授業で、子どもたちは実験器具の収納場所を大体把握することができます。また、出したら元に戻すこと、必要なものは必要なときに出していいことなどが印象に残り、子どもが自由に実験器具を選ぶことができる素地ができるのです。


