学級崩壊を未然に防ぐには?【伸びる教師 伸びない教師 第56回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

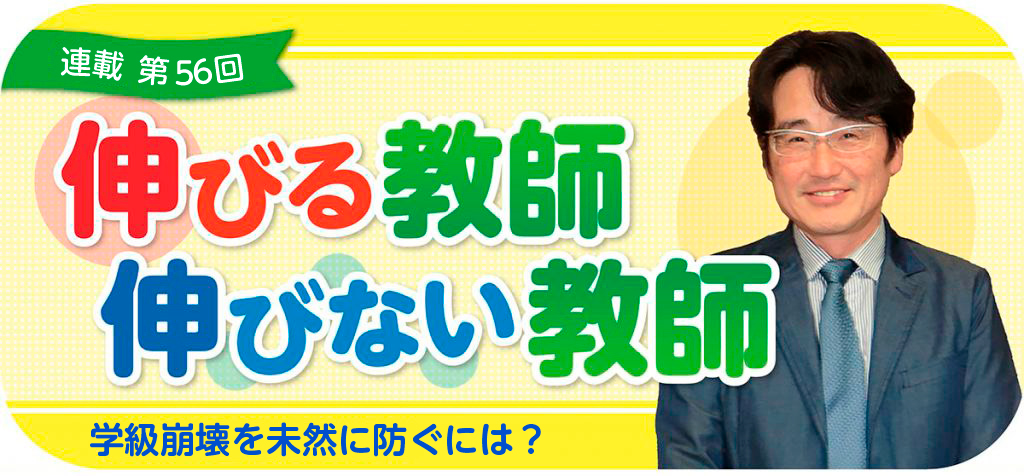
豊富な経験によって培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載。今回のテーマは、「学級崩壊を未然に防ぐには?」です。学級崩壊は小さなことから始まります。その兆候を見逃さないで、未然に予防するにはどうするかという話をお届けします。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県公立小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を務める。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
目次
学級崩壊は小さなことから
今から25年くらい前に、学級崩壊について特集しているテレビ番組を見ました。学級崩壊という言葉が世間で広まり始めた頃です。番組では、子供が授業中に紙飛行機を飛ばす、机の上を歩くなど、とにかくひどい状態が映し出されていました。
学級崩壊という言葉が広まり始めてから25年がたった今、学級崩壊は依然としてあります。当時、学級崩壊が少なかったベテラン教師の学級でも、今は1つ間違えれば学級崩壊の状態になってしまう危険性があると私は思っています。それくらい子供たちの変化には著しいものがあります。
学級崩壊は、そのほとんどがとても小さなことから始まります。例えば、進級などで担任が替わると学級のやんちゃな子たちが教師を試してきます。教師が「教科書を出して」と言ってもわざと出しません。教師がそのことに気付かずそのままにすると、「この先生が言ったことをやらなくても大丈夫だな」と子供たちの中にインプットされます。
担任のお試し期間
子供たちの「お試し期間」は、担任が替わると1週間は続きます。
給食の配膳1つとっても、前学年のときの学級でそれぞれやり方が違います。子供たちはそのたびごとに聞いてきます。
「おかわりは何回までですか?」「マスクはいつ外しますか」
全体のルールに関わることについては、
「ちょっと待っていて。そのことは大切なことだからみんなに言うから」
と言って、その子だけでなく学級全体へ伝えます。
これをしないと、次から次へ同じ質問がきます。一人一人それぞれに答えていると、教師も人間ですからそのときの気分によって答えが変わるときがあります。すると、子供たちは、「あれ、〇〇さんに言ったことと違う」ということになります。
それぞれ言われたことが違うのですから学級のルールは崩れていきます。
それと同時に、教師に対する信頼もなくなっていきます。こうした学級は荒れやすくなります。
一事が万事、こうして子供たちは新しい担任がどういう教師なのか試してきます。
はじめは教科書を出さない程度のお試しだったのですが、月日が過ぎるとだんだんエスカレートしていきます。
教師の指示に「なんで教科書、出さなくちゃいけないんですか~」など、言い返してくることもあります。この子供たちの行動に対し教師がある一定のルール、または信念をもって毅然と対応していかなければさらに反抗的な態度を強くしてきます。やがて、一部の子供たちが授業中に出歩いたり、大声で話したりするなど授業の妨害を始めます。それを見ていた周りの子供たちもまねをし始めます。
こうなると、教師がいくら注意をしても子供たちは聞きません。


