よくわかる教育委員会〜指導主事の仕事を中心に|第6回 公文書作成と稟議書の基本
連載「よくわかる教育委員会」、今回は指導主事が身につけるべき公文書作成と稟議書の基本について解説いたします。公文書は役人の世界で流通する文書であり、学校現場とは勘所が明らかに異なるものです。しかし扱うのは学校出身の指導主事。そのギャップを埋めるために、公用文作成の基本原則から稟議書の書き方、さらには決裁を円滑に進めるためのポイントまで、実務に直結する知識・技能をお伝えします。
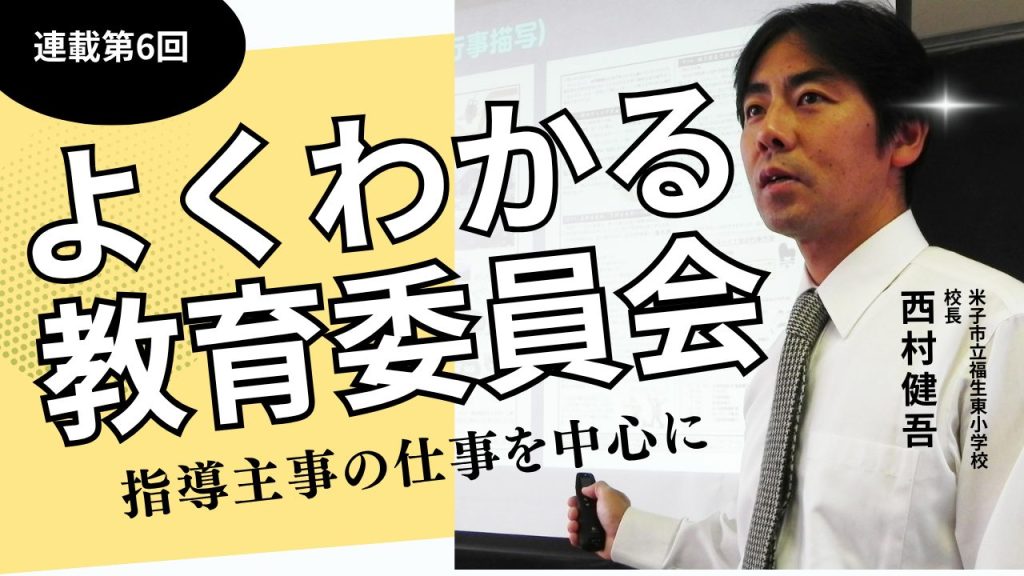

西村健吾(にしむら・けんご)
1973年鳥取県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、鳥取県の公立小学校および教育委員会で勤務。「マメで、四角く、やわらかく、面白い…豆腐のような教師になろう!」を生涯のテーマにしている。学校教育に関わる書籍を多数執筆。近著は『学校リーダーの人材育成術』(明治図書)。現在、米子市立福生東小学校長。本コラムは、10年間の教育委員会事務局勤務の経験を元に執筆している。
目次
公文書作成の留意点
公文書を作成するには、いくつかの守るべきポイントがあります。それらが押さえられていない文書を流通させてしまうと、学校をはじめとする関係部署の業務を停滞させてしまうことにもなりかねず、その影響は計り知れません。ただ、公文書は役人の世界で流通している文書ですから、教育関係者が作成する文書とは勘所が明らかに異なるものです。しかし扱うのは学校出身の指導主事……。そのギャップを埋める努力が必要です。まずこの点を、はっきり肝に銘じておきましょう。
ここを理解せず、よく言えば個性豊かな、悪く言えば我流で適当な文書を作成してしまう指導主事が散見されます。これではいけません。さらに言えば、指導主事は学校から提出された文書を適切に確認し、不備があれば指導しなければならない立場です。こうしたことからも公文書の基本的な知識・技能は、指導主事にとって必ず身に付けておかなければならない事項なのです。
公文書を作成するにあたって、次の点に留意する必要があります。
正確であること
- 文字や数字、日付や人の名前の誤植がないこと
- 内容に間違いがなく、 誤解を生じる危険性のある、あいまいな(玉虫色の)表現がないこと
平易であること
- 見た目にも内容的にも分かりやすいこと
- 文章が分かりやすく構成されていること
- 適切に段落分けされていたり、箇条書きされていたりすること
- 一文が短いこと
- 難しい語句や抽象的な語句が少ないこと
簡易であること
- 伝達すべき内容に過不足がなく、簡潔であること
- 冗長ではなく、要点を簡潔明瞭に述べてあること
目的に適切な形式であること
- 発信者・相手・日付・件名・内容の述べ方などが、公用文の作成要領に基づいて形式が整っていること
公用文作成の基本
公用文とは、国や地方公共団体などの公的機関が作成する文書や法令などの文書のことです。公的機関が発信する正式な文書として、正確で分かりやすいことが求められます。自治体によって多少異なりますが、おおむね以下のように作成します。
様式はA4サイズ
公用文に限らず、現在のビジネスシーンでは基本的にA4サイズの用紙を使います。 これは、1993年に厚生労働省が各省庁の行政文書の規格をA4にすると通達したことがきっかけです。現在ではすっかり定着しました。
文書番号と日付
文書番号は、その文書をすぐに検索できるように付与するものです。用紙の右肩に、文書番号と日付を記します。特に、教育長印を押印する文書については、文書番号(発番)をつけるのが一般的です。文書番号をつけることができなかったり、文書に教育長印(所属長印)が押印できない場合は、鑑をつけて対応します。
宛先名
宛先名は、日付下の行の左側に記します。役職者に宛てた場合、団体名や会社名と、職・氏名はずらして書き、職名と氏名は同一行に書きます。敬称は、「様」「御中」などを用います。
発信者名
発信者名は、宛名の下の行の右側に書きます。教育委員会名とともに、教育長名(所属長名)を書きます。職印を押すような文書の場合、発信者名と印影が重ならないようにします。
件名
件名は、 本文の内容を簡潔な言葉で表現した見出しのことです。左側から3マス空け、4マス目から記します。
主文
主文は簡潔に書きます。外部に出す文書では、頭語、時候の挨拶、結語などを記します。
別記
「下記のとおり」の「記」の部分です。別記は、「日時」「場所」「内容」「その他」など箇条書きします。

