地域の図書館と協働することで、 より豊かな学びを行う 【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #36】
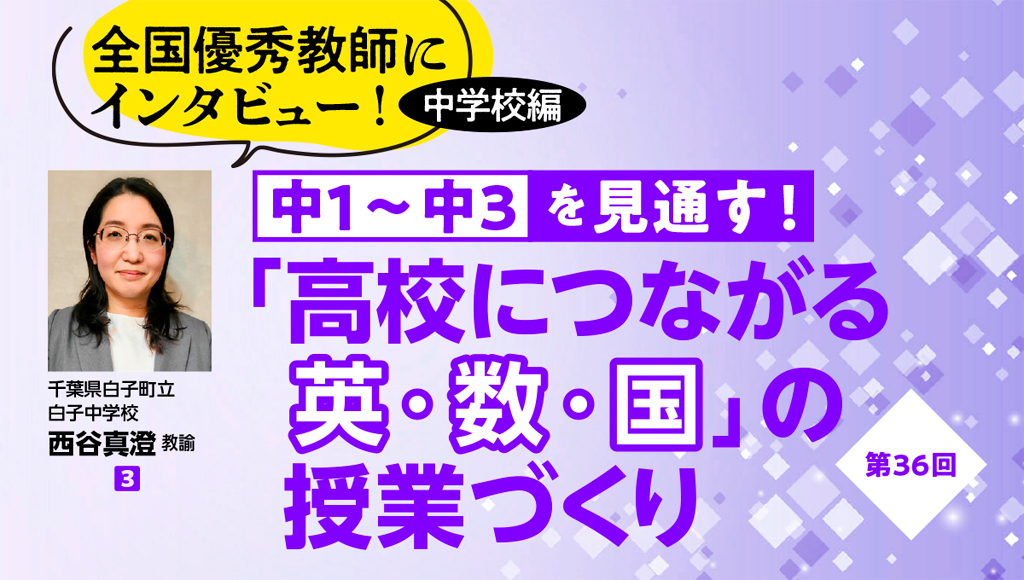
前回は、千葉県の「授業づくりコーディネーター」である、白子町立白子中学校の西谷真澄教諭に、国語の単元・授業づくりの意図や、それを通して育みたい力についてお話を伺いました。3回目となる今回は、読書を通して文章の型や語彙を身に付けさせるだけでなく、地域の図書館とも協働することで、 より豊かな学びを行っていく3年生の読書単元「読書生活をデザインしよう〜本のCMを作ろう〜」(全6時間)を紹介していただきます。

西谷真澄教諭
目次
本を完全に読み切っていなくてもCMを作ることができる
まず、西谷教諭は、このような単元構成を行った意図について次のように話します。
「この単元は、各自が主体的に選書して読んだ本に関して、自身の考えや解釈を意図した対象向けにCM(スライド)にまとめて、地域図書館で流すというものです。最近は、書店などで本のCMを流しているようなところもありますから、書店になりきってCMを作ろうというような少し遊び心のある感覚で取り組みました。それを地域図書館で行えば、地域の方も子供たちのお家の方も見に来てくださるからということで、学校司書さんと図書館の方と話をしている中で構想して行ったのです。
単元目標としては、『伝えたい相手を意識して、適切な叙述を引用したり、表現の効果や構成を工夫したりして、自分の考えが伝わる資料を作ることができる』(思考力、判断力、表現力等)などがありますが、その他に、『本のCМを作ることを通して、自分や社会との関わり方を支える読書の意義と効能について理解すること』(知識及び技能)も示しています。
ただ極端に言えば、この単元では本を完全に読み切っていなくてもCMを作ることができるような構造になっています。当然それに対して、『本を読み切っていなくてもよいのか』との批判があることは承知の上で取り組んだものです。
実はこの単元を行ったのは、あまり本を読んだことがない子供たちが多くいる学年でした。ですから、まずはたくさんの中から本を選ばせる経験をさせたかったのです。実際、私たちが本を選ぶときには、本のカバーやタイトル、さわりを少し読むくらいで『おもしろそうかな』と選びます。この単元でも、そのように気軽に本を選ぶ体験をさせたかったので、熟読して読解力を付けるというよりも、選書するとか本に親しむことが主なねらいなのです。
当然選ぶ本も、絵本や短い本などいろいろあります。それに対し、読解力育成がねらいであれば、『中学生なのにこの絵本?』『この短い本?』と思うかもしれません。しかし、選書して推薦することが目的ですから、子供たちも『お母さん向けだから絵本にしました』『小学生向けの短い本です』と言いわけが付けられます。そのようにして、どんな本であってもまず手に取ってもらいたかったのです。
ですので、読書活動を推進してきた学校にはフィットしない単元でしょう。しかし、『うちも本を読んでいる子供があまり多くない』という学校・学級では、やってみられてもおもしろいのではないかと思いますし、このときは実態に応じて3年生を対象に行いましたが、入学したばかりの1年生を対象に行ってみるとよいでしょう。もちろん『読むこと』に力を入れるなら、そこに時間を割いて活動を行えばよいわけで、使い勝手のよい単元だと思います」
初回に紹介した、「走れメロス」と他の本を比較して英雄論を書く単元では、読書量の多い子供が活躍する単元であるのに対し、こちらの単元は、あまり本を読まない子供でも、推薦する対象と本の選び方で活躍することができる単元なのだと西谷教諭は話します。

