自分を客観的に見るとは?【伸びる教師 伸びない教師 第54回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

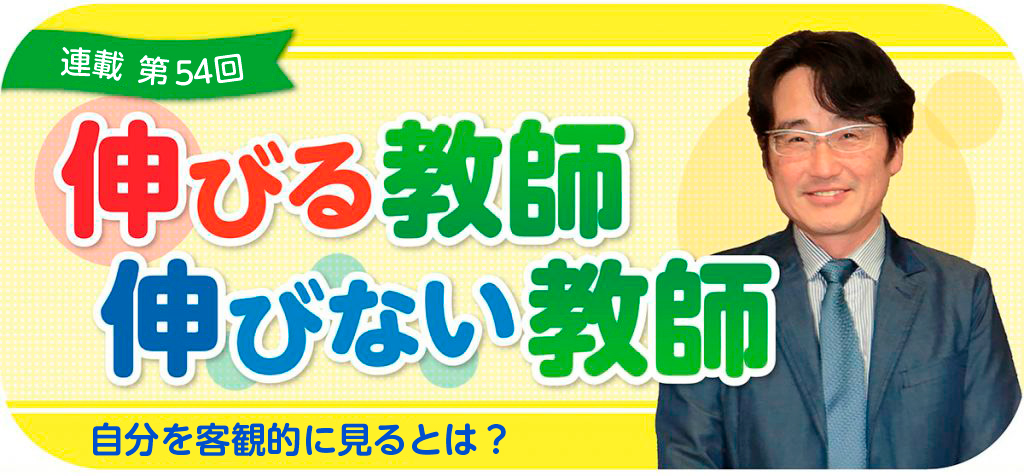
豊富な経験によって培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載。今回のテーマは、「自分を客観的に見るとは?」です。力のある教師は、自分の強みと弱みをきちんと把握し、自分の得意なことでは人を助け、自分の苦手なことでは人に協力してもらい、感謝をすることができるという話をお届けします。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県公立小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を務める。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
目次
自分を客観的に見る力
放課後、教室で仕事をしていた2学年担任の若い教師に声をかけました。
「1年は早いね。どうでしたか、この1年間は?」
「はじめは、席に座らせるだけで大変だったのですが、だんだん落ち着いてきて自分の話を聞いてくれるようになりました。子供たち、ずいぶん成長したと思います」
4月の初め、この学級には授業中に離席をしてしまう子供が何人かいて落ち着かない状態でした。そのため、私たち管理職もその子たちの指導に当たりました。それから1年、担任が真摯に子供たちと向き合った結果、教師が話し始めると「しーん」と静まり返り教師の話に耳を傾ける、そんな学級になりました。
私が「子供たちが話を聞くようになったのはどうしてなの?」と質問しようとした瞬間、その教師は、続けてこんなことを話し始めました。
「ただ、今でも私の話が長かったり分かりにくかったりするときは、途中で飽きてしまって話を聞かなくなるので、子供たちが興味を引くような内容や抑揚のある話し方に気を付けながら話をしています。でも、自分は抑揚のある話し方が苦手なのでいろいろ勉強中です」
この話を聞いて、この教師はこれからどんどん成長していくのだと感じました。自分を客観的に見て分析し、自分を変えようとしているからです。自分を客観的に見ること、これは簡単そうでとても難しいことです。
特に教師は、初任者のときから「先生」と呼ばれ、学級担任になると「学級王国」とも揶揄されるくらい他人が入り込みにくい人間関係を子供とつくっていきます。そのため、自分がすることに他人から意見を言われたり反対されたりすることが、他の職種に比べて極端に少なくなります。自分の考えがいつでも通る環境で長年過ごしていくと、いつの間にか自分の考えることはすべて正しいという錯覚に陥ります。
また、教育の成果は、すべてを明確に数値で表すことが難しいため、成果が出ていなくても「自分は頑張ったから成果が上がった」と勘違いしてしまうことがあります。
このようなマイナスの経験の積み重ねが、自分を客観的に見ることを難しくしています。
自分の欠点に気付かない
ある学級の担任は、「自分の学級の子供たちはすばらしい」といつも自慢げに語っていました。ただ、それだけでなく、「自分の学級に比べて隣の学級の子供たちは育っていない」と、他の学級の悪口を言うこともありました。
実際には、自慢している教師の学級の子供たちは、「自分たちの話を聞いてくれない」「ひいきがひどい」「怒り出すと止まらない」「自分に甘く、児童に厳しい」など、その教師に対する不満を前の担任や保健の教師に相談しているような状態でした。
ただ、そのことをその教師に伝えると誰が言ったのかを詮索したり学級全体につらく当たったりする可能性があったので、相談された教師も子供たちの本当の気持ちを伝えることはしませんでした。
このように、周りの人は言わないだけで、実は、その教師だけが自分の欠点や間違いに気が付いていないということが往々にしてあります。また、最近は、相手を否定しない風潮が見られ、ますますこの傾向が強くなってきていると感じています。
さらに、年齢が上がってくると、自分を客観的に見ることが難しくなってきます。周りで言ってくれる人が少なくなってくるからです。若いときには、先輩の教師が「ちょっとそれはおかしい」と言ってくれることもありますが、年齢が上がってくると、そうした先輩も少なくなってきます。


