保護者の心をわしづかみにする!最初の授業参観&保護者会ガイド

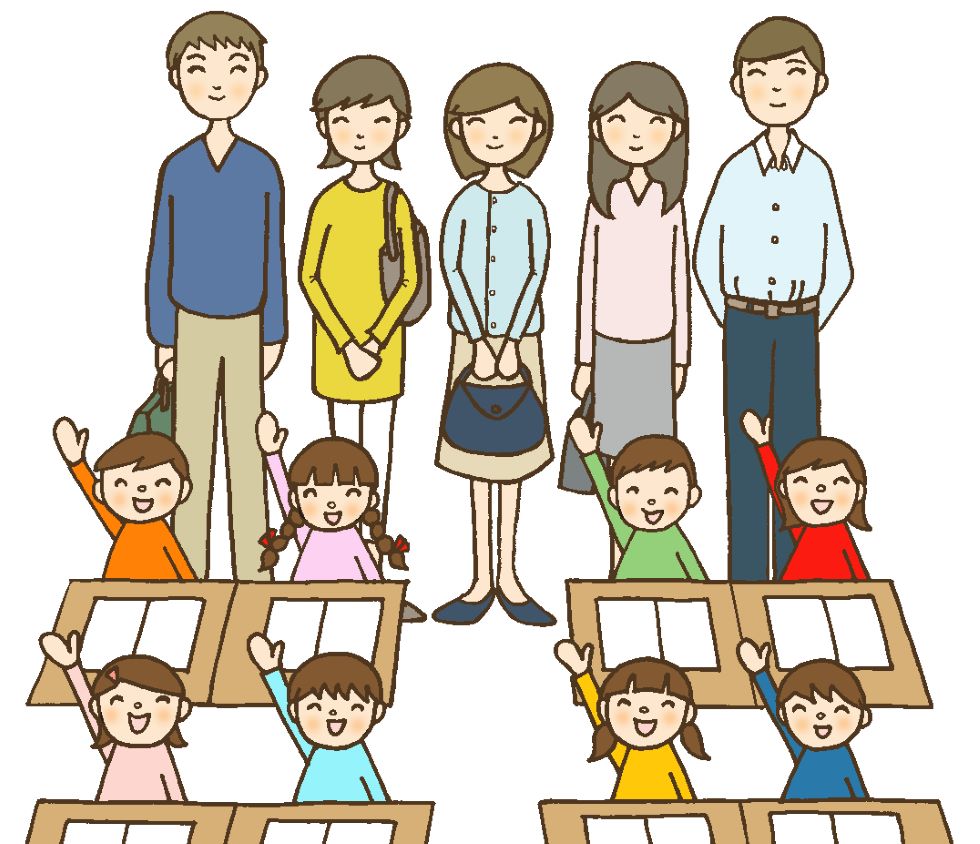
年度はじめの授業参観と保護者会で保護者の心をつかめたとしたら……、保護者たちは担任の味方となり、その後の学級経営を進めやすくなること請け合いです。それほど、最初の授業参観と保護者会は重要なものと言ってよいでしょう。特別支援教育の視点を取り入れた学級経営や、愛のある言葉がけで定評のある山田洋一先生が解説します。
執筆/北海道公立小学校教諭・山田洋一
目次
【授業参観編】はじめに~保護者は何を見に来るか~
保護者が授業参観で注目するのは、①担任とのやり取り、②子供同士のやり取り、③教室環境です。
①担任とのやり取り
授業参観の際、保護者は子供たちがどのように担任とやり取りしているかに注目します。先生の指導方法やコミュニケーションスタイルを観察しながら、子供たちがどのように学び、成長しているのかを見ているのです。
【好ましいと思えるコミュニケーションスタイル】
・明るくはっきりとした声で呼名する。
・微笑みかけて、その子の話を最後まで聞く。
・前向きなフィードバックを与える。
(「教えてくれてありがとう」「賛成できるよ」「素敵な考え方だと思うよ」など)
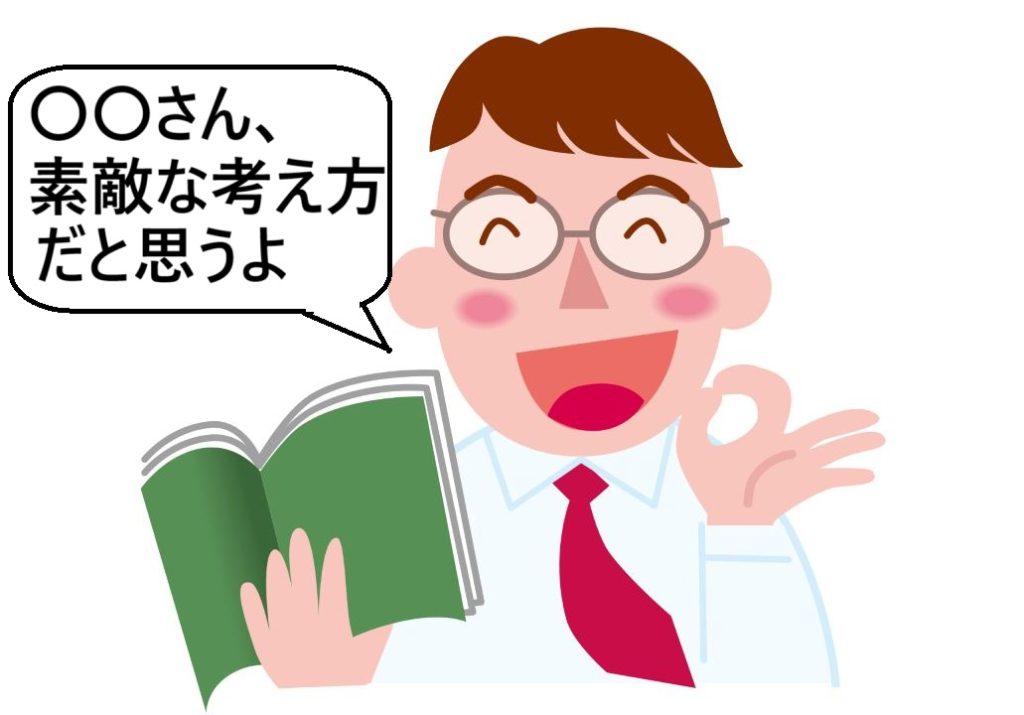
【避けたほうがよいコミュニケーションスタイル】
・「正しいか、正しくないか」をすぐに断定する。
・子供の話を途中で遮る。
・皮肉っぽい、あるいは否定的なフィードバックを与える。
(「〇〇さんにしてはよくできた」「やればできるじゃないか」「それは違うな」「やり直し!」「できてない」など)
②子供同士のやり取り
保護者は子供同士の関わり方や協力の様子にも関心をもっています。友達との協力活動やグループワークを通じて、子供たちの社会性や協調性が育まれているかを保護者は確認します。
下記のような、小刻みなペアワークやグループワークを授業に取り入れると効果的です。
●教師の説明+質問確認
教師が説明を終えたら、「隣の人に、『今の説明で分からなかったところはなかった?』と尋ねてみて」と呼びかける。
●問題を読む+内容確認
問題文を読んだ後に、「隣の人に、『大まかに言うと、どんな問題?』と尋ねてみて」と呼びかける。
●発問+意見交換
教師が発問する。→時間をとって自分で考えてみる。→「隣の人に、『どう考えた?』と尋ねてみて」と呼びかける。
③教室環境~教室に入っただけで「日常」が見える~
授業参観では、教室の環境を整えることが重要です。保護者が教室に入った瞬間から、子供の日常の学びや活動が感じられるような工夫が求められます。机や壁の掲示物、作品の展示などを通じて、子供の努力や成果を見せることが大切です。
●用具の整理、整頓をしておく
まずは、整って見えることが大切です。子供たちが使う鍵盤ハーモニカ、体育帽子、絵の具セット、ペン類、画用紙、折り紙などが種別にかごや棚などに収まっているか。またその際、サイズがそろっているか、向きがそろっているかなどにも配慮します。
例えば、体育帽子は紅白の2色が、表裏になっているものが多いのですが、かけるときには全員が「赤」か「白」の同色を表側にしてフックにかけるようにします。これだけで、教室は落ち着いて見えます。こうしたことは、保護者に対する単なる「見え方」の問題ではありません。整っているということは、子供たちにとっては不要な刺激が少ないということを意味します。つまり、整った教室環境は、落ち着いたクラスの雰囲気の必要条件なのです。
●作品にメッセージを貼付する
例えば、その子の書写や絵画作品に他の子供からのメッセージを添えて掲示します。
授業参観の数日前に、1人に1枚、付箋を配付します。それに、「お隣さんの作品のよいところをたくさん書いてね。『書けない』と思ったら、お隣さんに『気に入っているところは?』『集中したところは?』って、質問しながら書いてみてね」と言います。それを、作品に添えて、そのまま掲示するようにします。
参観に来た保護者は、必ず我が子の作品に注目します。その際、自分の子供が周囲の子からどのように受容されているのかにも気付けるようにしておくことが大切です。
【授業参観編】アイデア① 1人1台端末を活用して授業と家庭学習を結ぶ

学校では、1人1台の端末が普及しており、授業参観でもその活用方法を紹介することが効果的です。家庭学習と連携した取組や、デジタル教材を活用した学びの様子を保護者に示すことで、学校と家庭が一体となって子供たちをサポートする必要があることを保護者に感じてもらいましょう。
●デジタル教材を活用しよう
例えば、国語なら、漢字のフラッシュカードをスライドを活用して作っておきます。それを、授業参観で使って、「漢字の読み」を確認したとします。ひと通り終えた後に、「これは、みなさんにもシェアしてあるからね。家で読み方の練習をするときに、使えるからね」とひと言添えて伝えます。
算数なら、デジタル教科書を使って授業を進めていき、途中で「この問題の練習問題は、□番をするといいよね。○か×かをすぐに教えてくれるから、勉強しやすいよね」と、子供たちに伝えます。こうすれば、参観に来た保護者の参考になることは言うまでもありません。
また、デジタル教科書だけでは、子供の理解を十分に引き出せないと感じるときに、教員がオリジナル教材を作ることもあると思います。それらも、子供たちにシェアして、家庭学習のオプションとして備えましょう。併せて、そうした教材の一部に学習内容を理解するための優良なYouTubeサイトや、確認や練習に役立つサイトへのリンクを貼ると、子供たちにとって学びの幅が広がることでしょう。

