「体験格差」とは?【知っておきたい教育用語】
近年、親子の新たな社会問題として注目されている「体験格差」。体験格差が広がる背景を解説するとともに、子どもの頃の体験活動が重視される理由や解消のための取組などを紹介します。
執筆/「みんなの教育技術」用語解説プロジェクトチーム
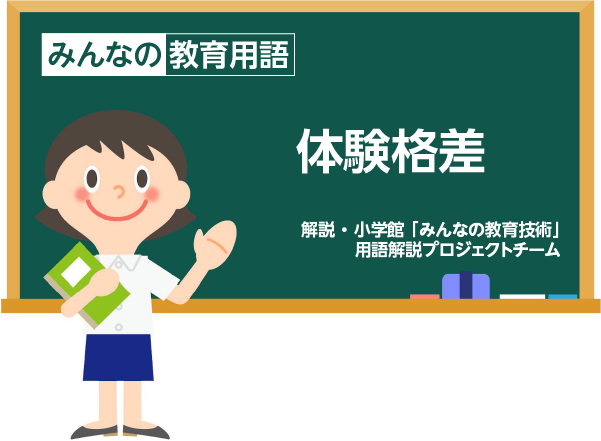
目次
体験格差とは
【体験格差】
「体験の貧困」とも呼ばれ、家庭や地域によって子どもが得られる学校外での体験活動の機会に格差が生じること。学校外における体験には、放課後に子どもが行う遊びや習い事のほか、旅行といった宿泊体験もある。
公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンが2022年に実施した調査によると、年収300万円未満の低所得世帯の小学生の3人に1人が1年間のなかで習い事や旅行といった「体験活動」を何も行っていないことがわかりました。
スポーツや文化芸術活動をはじめとした学校外の体験活動がない子どもの多くが「家庭の経済的事情」を要因としており、やりたくてもできない、させてあげられないという状況を背景にしています。また、家庭の経済的事情以外にも以下のようなことが体験格差の要因として挙げられています。
①保護者の時間的余裕(送迎など)
②地理的条件(選択肢の格差)
③保護者の体力的・精神的余裕
④情報の格差
⑤家庭や地域の文化資本
体験活動の機会の提供は保護者にかかる負担が大きく、また地域によっても格差が生じることがわかります。では、体験活動は子どもの成長にどのような影響をあたえるのでしょうか。
「体験」の重要性
文部科学省「令和2年度『体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクト』」によれば、小学生の頃の体験活動によって、以下のような影響があることがわかっています。
21世紀出生児縦断調査で回答されたデータを再分析したところ、小学生の頃に体験活動(自然体験、社会体験、文化的体験)や読書、お手伝いを多くしていた子どもは、その後、高校生の時に自尊感情(自分に対して肯定的、自分に満足している、など)や外向性(自分のことを活発だと思う)、精神的な回復力(新しいことに興味を持つ、自分の感情を調整する、将来に対して前向き、など)といった項目の点数が高くなる傾向が見られました。また、小学生の頃に異年齢(年上・年下)の人とよく遊んだり、自然の場所や空き地・路地などでよく遊んだりした傾向のある高校生も同様の傾向が見られました。
文部科学省(PDF)「令和2年度『体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクト』」
上記のことから、子どもの頃の体験活動は中高生以降の精神的な成長に好影響をあたえることがわかります。そして、自己肯定感やコミュニケーション能力、自分の感情をコントロールする力といった、子どもの精神的な成長は「非認知能力」の発達にも関わり、子どもの将来の進路や職業の選択、ウェルビーイングの向上にもつながっていきます。

