いいクラスの第一歩は机の中から!~整理整頓でこんなに変わる学級経営~

学級経営が思うようにいかない原因として、「整理整頓のシステムがあいまいだった」というケースは意外と多いものです。机やロッカーをきちんと整えるだけで、児童の学習意欲が高まり、学級全体の落ち着きも増していきます。少しの工夫と継続で、学級は大きく変わる、そんな整理整頓の秘訣を、ぜひいっしょに探ってみましょう。
【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~
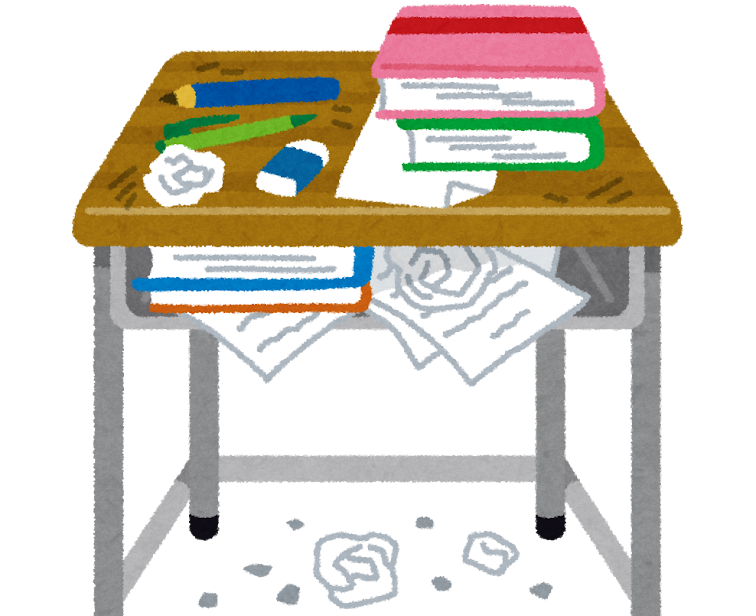
目次
整理整頓が学級づくりを左右する理由
研修を終えたある初任者教員が、「1年を振り返ってさまざまな悩みがあったが、特に整理整頓の指導がうまくいかなかった」と語っていました。
これは実に良い気づきだと思います。整理整頓とは、正しい生活習慣を身に付けることであり、集団生活にとっては欠かせない基本的な要素だからです。
4月は学級づくりのシステムを整えるうえで重要な時期ですので、ぜひ整理整頓のルールをしっかりと導入していきませんか?
散らかった環境は思考も散らかす
「整理整頓など些細なこと」と軽視しがちですが、実は教室環境が乱雑だと、必要なものを探す時間が増え、授業のテンポや集中力を乱します。反対に、必要なものをスムーズに取り出せる環境を整えれば、学習効率が上がり、授業のリズムも向上します。
生活習慣を整える “最初の一歩”
整理整頓を徹底することは、児童の生活習慣づくりの基礎にもつながります。朝登校してまず机の中を整えることで、一日のスタートスイッチが入り、行動をコントロールしやすくなります。加えて、身の回りを清潔に保つ習慣が育つと、「自分の行動に責任を持つ」という意識の芽生えにも結びつきます。
学級経営全体への波及効果
整理整頓が行き届いた教室では、指導者としての声かけが的確になり、児童もスムーズに動けます。「片づけなさい!」と叱る時間を減らせるため、より教育的なコミュニケーションや学習活動にエネルギーを注げるようになるのです。その結果、学級全体の雰囲気が好転し、指導がしやすくなるという好循環が生まれます。
視覚に訴える! “お手本” の示し方を工夫する
画像やイラストのインパクト
特別支援学級などでは、写真やイラストを活用した“視覚的支援”がよく行われています。
① 実際の机の中を撮影し、理想的な配置例を写真で掲示する
② イラストで「教科書はここ」「ノートはここ」といった“位置マップ”を作る
文字の説明だけでは理解しにくい児童も、ひと目で「このように片づければいいのか」とイメージできる点が大きな利点です。片づけが苦手な児童でも、この方法なら一定の成果が期待できます。
ラベル・色分け・区画分け
ファイルや収納ケースにラベルを貼ったり、教科ごとに色を決めて仕分けをしたりと、色や文字を使った“区分”を設けるのも効果的です。机の中を区画として認識しやすくなることで、「ここに入れる」「ここには入れない」というルールを自然に守りやすくなります。
「児童自身が作る」掲示物
担任が一方的に作るのではなく、児童自身が模範的な整理整頓をした机を撮影し合い、掲示物として完成させる方法もおすすめです。自分たちで作ったものには愛着が湧きやすく、当事者意識も高まります。その結果、掲示物への注目度が上がり、実際の行動にもつながりやすくなります。また、タブレットが一人一台になった現在、こうした写真の撮り合いを通じて学び合う機会も充実させることができます。

