探究のすすめ方~探究学習の担当になったあなたへ~ 小学校・中学校・高校対応

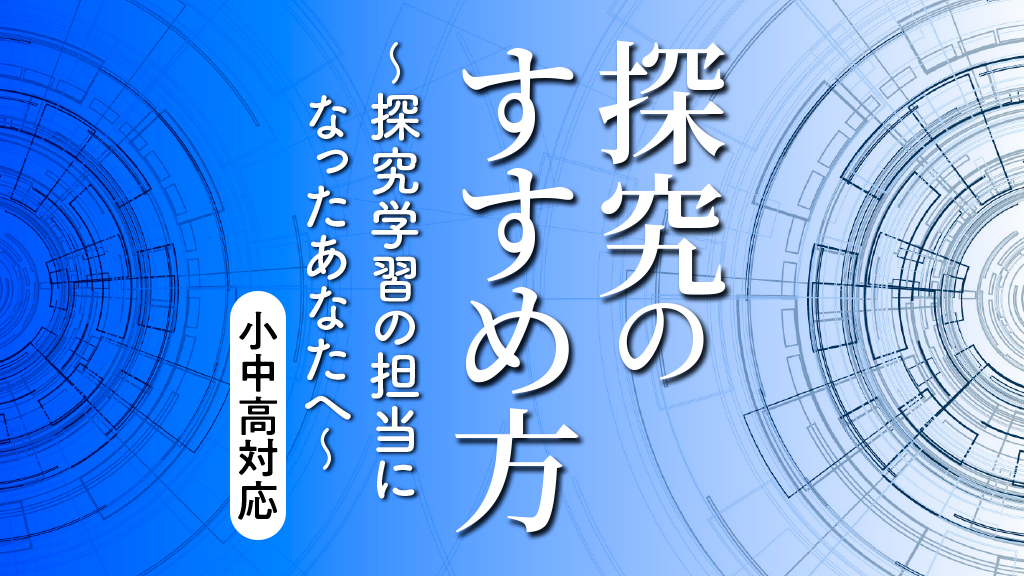
新しい学びとして注目を集めている探究。新年度をむかえ、皆さんの学校でも新たな学校教育目標のもと、探究のテーマや担当ぎめが行われているのではないかと思います。ただ、探究は、まだまだ実践例も少なく、どのような考え方でアプローチしていけばいいのか、お悩みの先生も多いはず。そこで、長年探究学習の研究に取り組んでいる四天王寺大学教育学部准教授の仲野先生に、楽しく分かりやすく、探究のすすめ方をガイドしていただきましょう。
執筆/仲野純章
目次
探究が求められる社会背景
「探究」という言葉自体は比較的古くからありますが、最近は、この言葉を教育現場の至るところで聞くようになってきました。この背景にはいったい何があるのでしょうか。
例えば、小・中・高等学校の学習指導要領解説・総則編には、共通的に次のような文章があります⑴⑵⑶。
今の子供たちやこれから誕生する子供たちが、成人して社会で活躍する頃には、我が国は厳しい挑戦の時代を迎えていると予想される。生産年齢人口の減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により、社会構造や雇用環境は大きく、また急速に変化しており、予測が困難な時代となっている。また、急激な少子高齢化が進む中で成熟社会を迎えた我が国にあっては、一人一人が持続可能な社会の担い手として、その多様性を原動力とし、質的な豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新たな価値を生み出していくことが期待される。
学習指導要領解説・総則編より
ここで述べられているような社会では、技術や社会サービスの進化や社会構造の変化などが加速度的に起こる中、それを受けた新たな課題も矢継ぎ早に生まれ続けます。今の子供たちが社会を創り、生き抜いていくには、「既に分かっていること」を習得するだけでは、対応していくのは難しいことは明らかです。問題の本質に潜む課題を捉え、あるべき状態へ向けて変革や価値創造を図るためには、学校段階でそうした力をしっかり養っていく必要があり、そのためのアプローチとして探究が益々重視されるようになってきました。
学校での探究
小・中・高等学校を問わず、学習指導要領には探究という言葉が多用され、学校段階を問わず、探究を重視する姿勢が窺えます。探究の要素を含んだ学び(以下、探究的な学び)は、総合的な学習の時間や総合的な探究の時間は勿論のこと、理科や社会といった各教科の授業でも求められています。そして、これらがばらばらに機能するよりは、有機的に繋がり、機能し合うことが期待されます。探究的な学びは、既に様々な形で実践がなされていますが、そうした中、例えば高等学校で実施されている様々な探究を厳密に類型化・定義しようとする試みも見られます⑷。しかし、探究という概念をできるだけ広く、そして気楽に捉え、課外活動などを含め、探究的な学びには多様な形があってよいと考えます。


