【連載】坂内智之先生の 愛着に課題を抱えた子が伸びるアプローチ~学級担任にできること~#3 あなたも愛着障害なのかもしれない
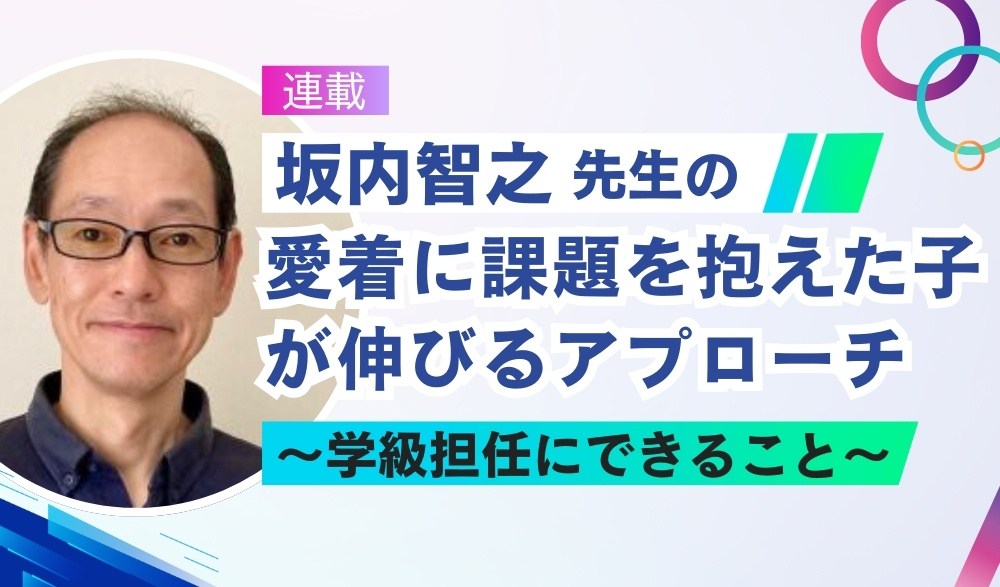
近年、教員たちが対応に苦慮し、学校現場を根底から揺るがしている「愛着障害に苦しむ子どもたち」。そうした子どもたちによって荒れた学級を何度も立て直してきた坂内先生が、今、学級担任に何ができるのかを提案し、これからの学級のあり方について考えていく連載第3回。今回は愛着障害についての基礎知識を解説し、当事者の子どもたちが激増している社会的要因について、担任としての実感に基づいて分析していきます。
執筆/福島県公立小学校教諭・坂内智之
目次
はじめに
この連載では、近年、学校現場で問題行動や不登校が増加し、対応に苦慮されている先生方が多いことを解説してきました。その背景には、愛着の問題が深く関わっていると思われます。
第3回では、愛着障害の基礎知識として、気になる子どもの問題行動と愛着の課題との関連性について理解を深められるようにしていきたいと思います。
1.「愛着障害」との出会い
最初の事例は20年以上前にさかのぼります。私がまだ若い頃に、拒食症になってしまった高学年の男の子がいました。学校での成績は良く、とても真面目でよく努力する子でした。彼はどう促しても給食に手をつけず、その理由を尋ねても、はっきりとした答えが返ってきません。両親は優しく家庭環境も良好ですので家庭に問題があるようには思えませんでした。彼の体はどんどん痩せていき、ついには入院することになりました。しばらく入院した後、学校に戻ってきた彼は次第に回復していきます。お母さんにその経過を尋ねてみると、精神科の医師から次のようなアドバイスを受けたと教えていただきました。
「優しい彼は、弟のためにお母さんに甘えることをずっと我慢してきました。ですから、もう一度お母さんが彼を抱っこすることから関わりをつないでみてください」。
お母さんはアドバイスされた通りにしてきたと言います。
卒業後しばらくして、お母さんからお手紙をいただきました。手紙では、彼が中学校ですっかり元気になって、部活動に励んでいることを教えてもらいました。あれこれと食べるよう説得してきた私には、「抱っこすることで回復するなんて…」と、不思議な気持ちしかありませんでした。今では、何が起こっていたのかよく分かる事例ですが、当時はこの状況を全く理解できていませんでした。
それから時が流れ、今から7年前、私は若手が担任するクラスで子どもたちが起こす様々な問題行動のサポートに追われていました。担任の対応の仕方が悪いのではないか、家庭問題の影響が大きいのではないか等、その理由をいろいろと考えて対処してきましたが、なかなか解決には結びつきません。それどころか問題はどんどん大きくなってきます。
しかも、問題を起こしている子どもは特定のクラスだけにいるのではありません。学校全体に気になる子どもが増えていきます。はっきりとした因果を捉えることができないまま、対応に追われるばかりでした。
そんな中、ある教育雑誌で問題行動の事例紹介と対応についての連載を見つけました。読んでみるとまさに今、日々問題行動にあたっている子どもたちの姿とピッタリと重なります。その連載をされていたのが、和歌山大学の米澤好史教授でした。米澤先生は、愛着障害という切り口から、子どもの問題行動の分析、対応の仕方などについて、学校現場の先生方へのサポートを行なわれています。
「愛着障害」という言葉は、もちろん私もそれまでに聞いたことがあり「家庭での虐待などで子どもの心が正常に発達できていない」そんなイメージをもっていました。
ところが、米澤先生の理論によると、そうした虐待とは関係なく、どんな家庭にも起こりうることや、両親がそろっている家庭でも起こりうることを解説されています。今ある学校の子どもたちによる問題行動は、間違いなくこの「愛着障害」が原因だろう、そう確信できた瞬間でした。
2. 自分も愛着障害だったのではないか
米澤先生の愛着障害のご著書を読んで、真っ先に思い浮かんだのは学校で問題行動を起こしている子どもたちでしたが、そうした子どもたちのことを考えるうちに、ふと「ひょっとして自分も愛着障害を起こしていたのではないか」と自分の過去の記憶がよみがえってきました。
あの時、なぜたくさんのトラブルを抱えていたのか、なぜ「誰も自分のことを分かってくれない」と怒りを抱えていたのか、なぜ毎日のように保健室に行っていたのか……そんな子どもの頃の感情がよみがえります。
しかし、私は末っ子で、母親をはじめ、家族皆から十分に愛されて育ってきたという自覚があります。それなのに「もっと分かってもらいたい」「悪いのはあいつだ」「自分はもっとすごい」のだと、いつも心の中で叫んでいたことを思い出します。そうした心の叫びが原因で、友達との関係、先生との関わりにおいて、多くのトラブルを起こしてきました。
今では、自分が愛着障害を起こしていたのだとよく分かります。なぜ愛の中で育った自分が愛着障害を起こしていたのか。その原因は私が求めた愛と親の愛とのすれ違いがあったこと、米澤先生が提唱されているように「愛情の器」に穴が空いていて、愛を溜めにくい性質だったことにあったのだと理解できます。
今回読者のみなさんにお伝えしたいのは、愛着の課題は、このように誰にでも起こること、そして近年の学校現場では、すごい勢いで愛着の課題を抱える子どもが増えてきているという事実です。そして、今の私がそうであるように、それは必ず回復できるのだという希望です。
3.「愛着障害」という言葉

坂内智之プロフィール
ばんない・ともゆき。1968年福島県生まれ。 東京学芸大学教育学部卒業。福島県公立小学校教諭。協働学習の授業実践家で「学びの共同体」から『学び合い』の授業を経て、20年以上にわたり、協働学習の授業実践を続ける。近年では「てつがく」を取り入れた授業実践を行う。 共著に『子どもの書く力が飛躍的に伸びる!学びのカリキュラム・マネジメント』(学事出版)、『放射線になんか、まけないぞ!』(太郞次郎社エディタス)がある。

