子供とともに学ぶ授業づくりとは?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #23

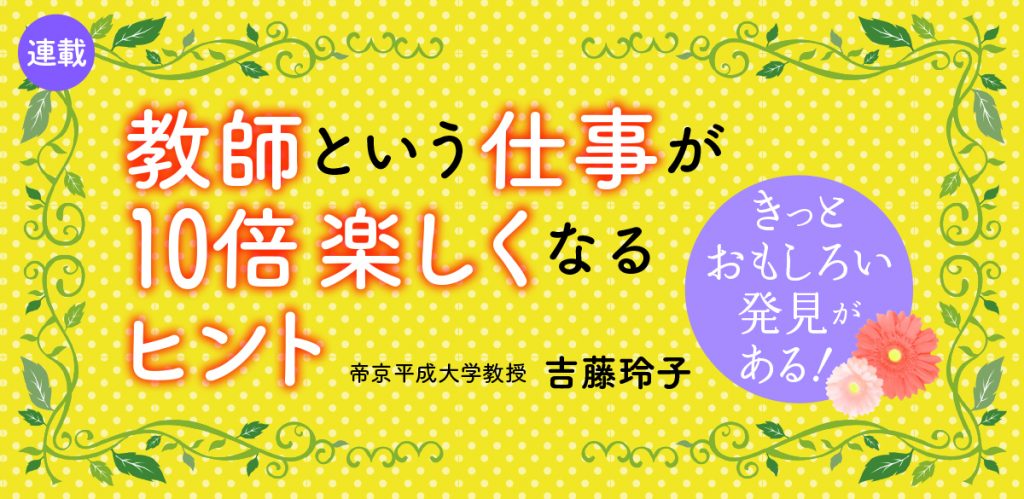
「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」の23回目のテーマは、「子供とともに学ぶ授業づくりとは?」です。子供の心を引き付けるには授業づくりが大切です。授業づくりをどうするか。子供が楽しくなるような授業の組み立て方や授業づくりのヒントなどを紹介します。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等、様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
子供が楽しめる授業づくりを
子供にとって、学校で過ごす1日の多くは授業です。もちろん休み時間や帰りの時間も大切ですが、子供が多く時間を過ごす授業がつまらないと学級は荒れ出すことが少なくありません。教師の話術で何とかなるというのは思い上がりです。教師の説教など子供は大嫌いです。授業を大切にしないことは子供を大切にしないことにつながります。逆を考えてみてください。もしも、自分が1日6時間の授業を受ける立場になったら、つまらない授業ほど苦になることはありません。だからといって毎日スーパーティーチャー的な授業をしなさいと言っているのではありません。1日に1時間でもよいので、子供が楽しめる授業づくりを実践してみましょう。

どうやって授業を組み立てたらよいのか
やりたいことはたくさんあっても1時間の授業は45分間です。そこに社会科であれば「つかむ」⇒「調べる」⇒「まとめる」の展開を入れて、子供が集中して主体的に授業に取り組めるように組み立てなくてはいけません。若手もベテランも授業づくりは悩むところです。
まず大切なのが実態の把握です。教える相手である子供がどの程度の内容ならついてくることができるかを把握することです。クラスの半分以上が塾へ行っている場合と、家ではほとんど勉強しないという場合とでは、子供の理解度も違ってきます。また、集団の特性もあります。クラスの集団の特徴をきちんと捉えることが大事です。ただどのような実態であってもクイズや体験を取り入れた授業を行えば子供は喜びますので、子供の実態に合わせて工夫してみましょう。
次に、授業の入り口と出口を教師がきちんと押さえておくことです。これは、何をこの1時間の授業で教えるか、どんなことを理解させるかが分かっていないとはっきり見えてきません。
例えば5年生の社会科の授業において、授業のはじめは、高い土地の暮らしの様子がまったくイメージできなかった子供も1時間目の授業が終わった後で、高い土地の高さや気候の様子(自分たちの住んでいる地域と比べられると、さらによいでしょう)、特産物などに気付き、これから時間をかけて調べていこうという意欲をもち、学習問題、学習計画などが立てられることをゴールとします。
そうすれば、どのような流れで授業を進めたらよいかが明らかになってきます。教師用の指導書などを活用して、何をこの1時間で子供に分からせたらよいのか、箇条書きにして流れを考えてみましょう。
授業のパターンはいろいろあります。1枚の資料からたくさんの意見を子供から出させる授業、自分たちの住んでいるところとの比較資料を出して子供に検討させる授業、グラフや表から事象を読み取る授業など様々です。学習問題も子供から出た発言を集約して作成する場合もあれば、教師のほうで示す場合もあります。私はどちらもよいと思っています。子供が何について追究していくのか追究課題が明確であれば次に進むことができます。調べる方法については、子供だけでできるように、ここで具体的なヒントを示すことも大切です。よく[調べ活動……インターネット]と板書されている授業を見ることがありますが、調べるときに迷う子供に対して検索キーワードなども用意しておくとよいでしょう。
私は、自分の研究に関する異文化理解の授業を小学校現場で行う場合、「パフォーマンス課題と評価」を取り入れています。授業の最初に「あなたには、日中親善友好大使になってもらいます。日本と中国は同じアジア圏の隣国であり、様々な交流があります。しかし、長い歴史の中での出来事によって、互いによいイメージをもっていない人々も多くいます。日中のつながりをどうしたら解決できるでしょうか。今回、2つの国を知るきっかけとして、日本と中国の同じような年中行事を調べてみましょう。何らかのつながりやこれからの関係の解決策がないか、アイデアを出して、考えてみてください。あなたの提案は、中華学校の先生たちに見てもらう予定です」とこれからの授業を進めて終えるゴールをまず先に示します。
提案の時間も含め、毎時間、どこまでできたらどの程度の評価とするか、パフォーマンス評価表を作成して、子供の到達度を記録していきます。子供にとっては、ゴールがはっきりしているので調べやすいですし、自分の考えを誰かにアウトプットできることも魅力です。

