good enoughな毎日を! ~今考えたい、先生と子どもたちのための「自尊感情」~

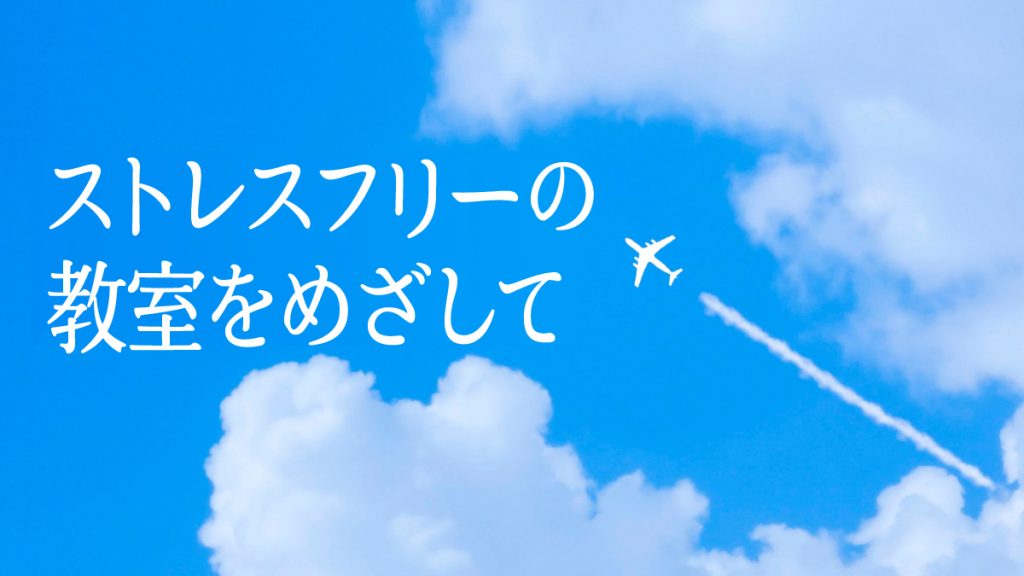
「自尊感情って、高い方がいいですか?」
たびたび耳にする「自尊感情」という言葉。これは、人間が成長していくための下支えとなる、大変重要な概念だと言えます。それは、ただ高ければ高い方ほどよい、というものではなく、その質が大切だと言われているのをご存知ですか? 今回は、教育に関わる先生方と、子どもたちにとっての自尊感情について、考えてみたいと思います。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #19
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
自尊感情は、自己評価
この記事を読んでいるあなたは、自分自身のことをどう評価していますか?
自分自身を自ら価値あるものとして評価する感情のことを、「自尊感情」といいます。自尊感情は、「自尊心」「自己肯定感」などという似た言葉で表現されることもありますが、概念としてはほぼ同じ意味で扱われることが多いようです。教育現場だと、自己肯定感という言葉が有名だと思います。各自治体が公表している教育振興基本計画などにも、よく自己肯定感という言葉は載っていますね。
繰り返しますが、自尊感情とは「自己評価」です。他の誰かが評価するものではありません。
自尊感情は、高ければ高い方がよい?
自尊感情は、「高ければ高いほどよい」というものでもないようです。アメリカの例から考えてみましょう。1980年代、アメリカのとある州では犯罪・暴力・薬物乱用といった社会的問題や、学業的失敗などが問題とされていました。そこで行政は、自尊感情が高まればこうした問題は解決するだろうと考え、約3年間に及ぶ「自尊感情を高めるプログラム」を実践したのです。しかし結果は行政の目論見からは外れ、社会的問題は特に改善せず、むしろ教育水準が低下するなどの弊害まで生まれてしまったそうです。
この例は、自尊感情の「高さ」だけが重要ではなく、むしろ「質」が問われるのではないかという視点を私たちに与えてくれたように感じます。では、自尊感情の「質」とはどのようなものでしょうか。

