生成AI【わかる!教育ニュース #61】
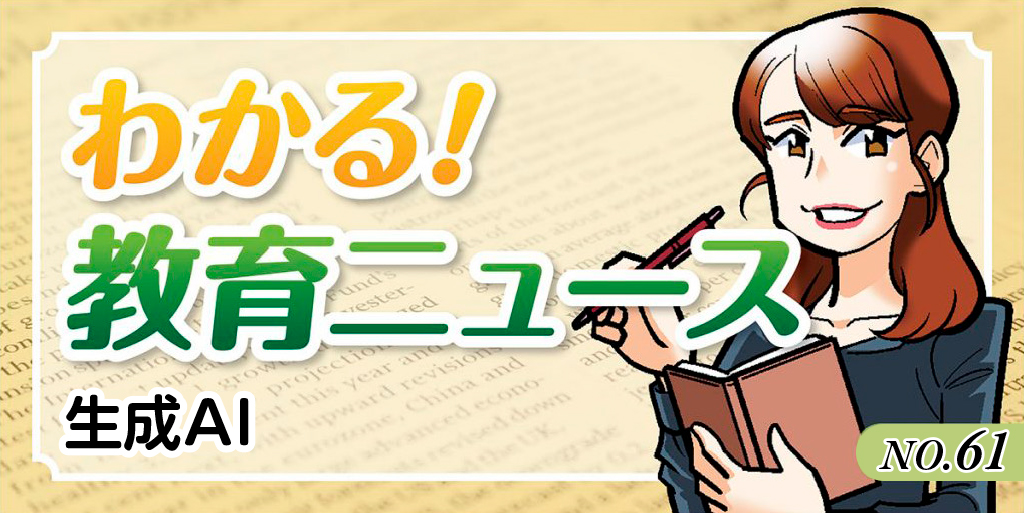
先生だったら知っておきたい、様々な教育ニュースについて解説します。連載第61回のテーマは「生成AI」です。
目次
AI利用は、資質や能力の育成、学びへの効果を吟味するのが前提
人間と会話するようにやり取りをし、文章や画像なども作りだす生成AI(人工知能)は、便利でおもしろい半面、警戒すべき点も多いもの。学校で活用しようにも、AIとの距離感がつかみにくいのではないでしょうか。
文部科学省がこのほど、学校での生成AIの利用を巡る考え方を示した指針を改訂しました(参照データ)。使い方次第で「有用な道具になり得る」としつつ、リスクもはらむことを踏まえ、人間が最終責任を担う視点でまとめています。教育での利用も、資質や能力の育成、学びへの効果を吟味するのが前提で、利用自体が目的ではない、と釘を刺しました。
生成AIに関する学びは、構造やリスクなどの仕組み、ファクトチェックや対話スキルといった使い方、教科学習での活用方法などを挙げています。情報活用能力の一部として日常使いも想定していますが、小学生については「発達段階を踏まえた、より慎重な見極め」を求めています。
具体的にどう使うかも例示しました。グループで考えをまとめたり、アイデアを出したりする時、足りない視点を見付けるためにAIに問いかけるといった、学習での活用。誤りや偏りを含むAIの回答を基に、AIの「限界」を理解させる情報モラル教育。外国人の子の日本語学習や勉強の補助などです。
好ましくない使い方も示しています。まず、情報活用能力が不十分な段階での使用。その他、AIが作ったリポートや小論文などを自作として出したり、詩や俳句の創作、美術の感想など感性や独創性に関わるものに使ったりするのも不適切だとしました。
一方、校務での利用は効率化につながると期待し、授業準備、時間割案の作成、行事報告など学校からの情報発信に使えると見込んでいます。ただし、AIの出力結果は教職員が推敲し、責任をもつことが前提です。

