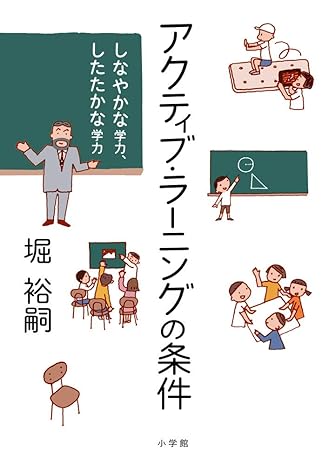【連載】堀 裕嗣 なら、ここまでやる! 国語科の教材研究と授業デザイン ♯3 教材解釈における「初動」の大切さ~「文脈」を読む力について・その3~

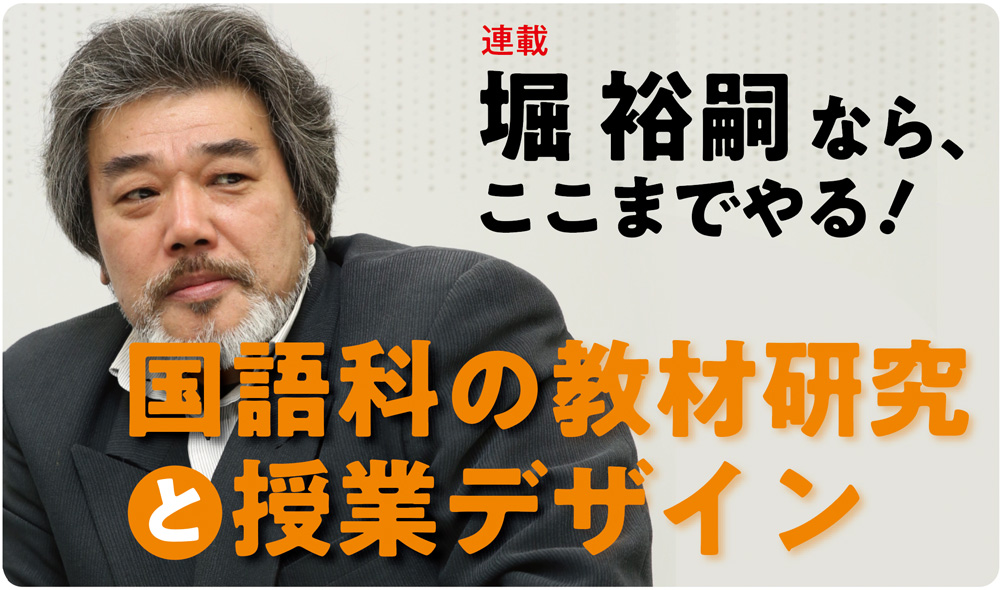
国語科・道徳科において、理論的裏付けに基づくクリエイティブな教材開発、教材研究、授業実践に定評のある堀 裕嗣先生の連載第3回。モーニング娘。と生成AIに関する話題を枕に、今回もディテールにこだわる教材研究について考えていきます。
目次
1.日本の未来は Wow Wow Wow Wow?
昨夜、YouTubeでモーニング娘。の「LOVEマシーン」の映像を観た。いつのものかよくわからないが、同窓会的な意味合いで初期メンバーが集まり、「LOVEマシーン」を中心としたヒット曲を何曲か歌う、そんな映像だった。「LOVEマシーン」のヒットは1999年だから私は33歳。教員生活としては9年目、札幌市内中央区の伝統校にして研究校に勤めていた(ちなみにこの学校は、当時のメンバー石黒彩の出身校でもある)。モーニング娘。に当時は何の興味も抱かなかったが、生徒たちが大騒ぎしていた記憶だけは残っている。
しかし、それから30年近くが経った現在(いま)になって聴くと、この曲はさまざまな意味で象徴的であり、示唆的であったとの感慨を強くした。そんなフレーズを挙げてみるとこんな感じだ。
どんなに不景気だって 恋はインフレーション
明るい未来に 就職希望だわ
日本の未来は(Wow×4) 世界がうらやむ(Yeah×4) 恋をしようじゃないか!(Wow×4)
モーニング娘。も(Wow×4) あんたもあたしも(Yeah×4) みんなも社長さんも(Wow×4)
1999年というとバブル崩壊から6~8年といったところだろうか。おそらくまだ、「失われた10年」という言葉もなく、だれもがすぐに日本は復活すると信じていた時代だった。しかし、周知の通り、日本は下降線を辿り続け、「失われた10年」は「失われた20年」を経て「失われた30年」に至る。この先だって「失われた40年」「失われた50年」と続くのではないかと思われるほどに復活の兆しは見えない。いや、もう30年が経っている段階で既に「失われた」という形容をつけるのが不遜なのかもしれない。
もうあの当時の空気を肌で感じる経験をもっているのは四十代以上という時代になってしまったが、90年代は「バブルが崩壊した」「不景気だ、大変だ」と言いながら、それは融資や投資の世界でのことであり、国民全体の気運としてはバブル景気で形成されたメンタリティがずーっと残っていた。バブル崩壊は一般に1993年と言われるが各種データがバブルの崩壊を示したのは1991年のことである。バブルの象徴とも言われる「ジュリアナ東京」の開店は1991年、1994年に閉店しているから、実はバブル崩壊後が最盛期である。その後も「ジュリアナ」に代わるディスコがしばらくブームを巻き起こしていたから、間違いなく「ジュリアナ」的気運は90年代を通して継続していたのである。
そんな中、政治・経済の世界では「小選挙区制」の導入、「護送船団方式」の解体、「官官接待」批判などが展開され、これらの改革で日本の未来は明るいと私たちは思い込まされていた。昨夜、「LOVEマシーン」を聴いたとき、私にはこの曲の歌詞がそうした90年代の「錯覚」の象徴のように思われたのである。
2.「失われるもの」を想定できる?
私は当時、札幌市内中央区の伝統校にして研究校に勤めていた、と述べた。この学校に赴任したのは1998年4月のことである。
1998年と言えば、1995年に阪神大震災及びオウム真理教地下鉄サリン事件、前年に山一證券と拓銀の破綻、酒鬼薔薇聖斗事件が起き、不穏な空気が漂い始めた時期でもある。事実、私の勤務校には拓銀の社宅があった関係で、北洋銀行に再就職できなかった保護者の子どもたちがたくさん在籍していた。つい先日まで年収1,000万円以上あった保護者が再就職先では250万円前後なんていうこともよく見聞きしたものである。
しかし、こんなにも近くに、こんなにも悲惨な事例があったにもかかわらず、私たちの周りには「浮かれた空気」を戒める言説はほとんどなかった。「小選挙区制」の導入その他の改革がこの度の失敗の反省から生まれ、日本は再び「Japan as No.1」の座に立ち返る。だれもがそう信じていたのだと思う。
しかし、それから30年近くが経って、「小選挙区制」を改めようという主張が高まってきている。「護送船団方式」や「官官接待」は日本的な経済システムとしてよくできたシステムだったのではという懐古趣味的な主張まで現れる始末だ。なぜあのとき、もっと冷静に、この国は変革によって何を失おうとしているのか、この度の改革によって失われ得るものは何かと検討しなかったのか。いまさら嘆いても仕方ないのだが、こうした後悔が私の中には確固とした存在感をもって横たわっている。
この構図は国語教育界においても同じことが言える。それは本連載の第1回で詳説したので未読の方はご笑覧いただきたい。
現在の状況に即して言えば、いま光の速さで進化している生成AIのもと、来るべき「生成AI時代」に便利さや改革の興奮と引き換えに我々が失おうとしているものは何なのかと検討すべきとき、それが現在(いま)なのではないか。私は直観的にそう感じるのだ。それはおそらく「生成AIネイティブ」が教育期間を終え、社会に出始めた頃に顕在化し、それから数十年経ってその世代が社会の実権を握った頃に絶望的な展開を見せるように思う。ちょうど戦争体験者のほとんどが亡くなって語り継ぐ者が時代から去り、戦後生まれが社会の実権を握るようになってこの国にあった思想的前提が失われてしまったように。
しかも時間は不可逆であるから、絶対に元の状態に戻すことはできない。その悪影響に気づき、どんなに後悔しても、その「元の状態」があった地盤(=前提)を既に解体してしまっているので、「元の状態」に回帰することは原理的に不可能なのである。ある意味で、人の営みはこうしたことの連続であったと見ることができる。その悪弊を打開するには、変革の初動で慎重な姿勢で「その改革で失われるもの」を想定し、吟味し、精査するしか方法がない。それが「現在(いま)」だと言っているわけだ。
ただし、その悪影響が目に見えてこの国を脅かす時代、おそらく私は生きてはいまい。私のこの心配が杞憂であることを祈るばかりである。
3.全文読むのに何分かかる?
さて、冒頭の余談が長くなった。
実は、私は今回、教材(=文章)を読む場合にも、何より「初動」が大切なのだと主張したいのである。
堀 裕嗣 先生のご著書、好評発売中です!
↓「スクールカーストの正体ーキレイゴト抜きのいじめ対応―」
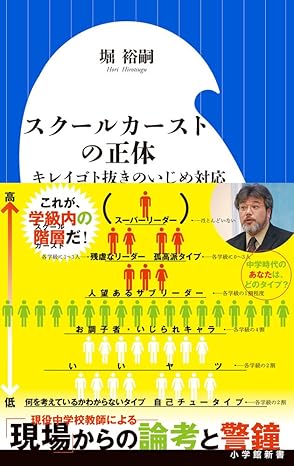
↓「アクティブ・ラーニングの条件ーしなやかな学力、したたかな学力-」